土地売却の完全ガイド|流れ・費用・税金対策から高く売るコツまで徹底解説
最終更新日: 2025-10-03
.png)
- もくじ
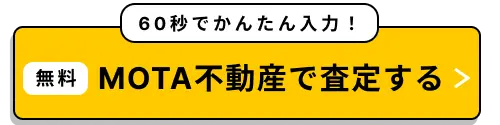
土地売却をスムーズに進めるには、売却の手順や税金対策などを覚えておく必要があります。
今回は、土地売却に関する知識が今すぐ必要な方向けに、売却の流れや不動産会社の選び方などを分かりやすく解説します。
土地の売却における主な流れ

まずは土地売却の手順について、契約前の準備から契約後の販売活動の流れまでひと通り解説します。
STEP1. 土地の現状を調べる
土地を売却するには、「いくらで売れるか」という以前に、まず売却そのものが可能か否かを確認しておく必要があります。
売却可否の判断に必要な情報は2つあり、1つは土地の名義、もう1つは隣接地との境界です。
土地の名義
土地の名義に関しては、法務局より登記簿謄本を取得するか、登記情報提供サービスにて登記事項証明書を取得することで確認できます。
登記簿謄本を取得する場合は、以下のいずれかの方法で請求・受取を行いましょう。
請求・受取方法 | 所要期間 | 手数料 |
窓口請求・窓口受取 | 10~15分程度 | 600円 |
オンライン請求・郵送受取 | 数日 | 500円 |
オンライン請求・窓口受取 | 最短即日 | 480円 |
登記事項証明書を取得する場合は、登記情報提供サービス上で一次利用者登録を行ったのち、マイページの「不動産請求」より画面の指示に従ってください。
名義人情報だけが載った「所有者事項」を請求する場合、手数料は142円です。
隣接地との境界
一方、隣接地との境界に関しては、「確定測量」によって調べられます。
確定測量とは、調査対象の土地と、道路や隣家といった周辺の土地を明確に線引きする作業です。
境界が曖昧なままでは、土地を巡るトラブルのリスクがあることから、なかなか買い手がつかなくなります。
確定測量を行う際は、必ず「土地家屋調査士」が在籍する測量会社に依頼し、確定測量図と境界確認書を作成してもらいましょう。
確定測量には一般的に2〜3か月を要し、費用の相場は50〜100万円程度です。
STEP2. 売却に必要な書類を準備する
土地を売却するにあたって、主に必要な書類は以下の通りです。
- 登記識別情報(登記済証)
- 確定測量図および境界確認書
- 固定資産評価証明書および固定資産税納税通知書
- 抵当権抹消書類
- 住民票・印鑑証明書・その他本人確認書類
登記識別情報
登記識別情報とは、土地の所有権を証明する書類であり、土地購入時に法務局から交付されています。
万が一紛失した場合、再発行は行えないため、司法書士に本人確認情報を作成してもらうなどの代替手段が必要になります。
確定測量図および境界確認書
確定測量図および境界確認書は、確定測量の際に土地家屋調査士が作成してくれます。
固定資産評価証明書・固定資産税納税通知書
固定資産関連の書類に関しては、固定資産評価証明書のみを市区町村役場で取得しておきましょう。
固定資産税納税通知書の方は、毎年自動的に送付されていますから、最新のものを探し、用意しておくだけで大丈夫です。
抵当権抹消書類
抵当権抹消書類についてですが、抵当権は住宅ローンを提供する金融機関が持つ権利であり、返済が滞った際に担保となる住宅を競売にかけることができます。
住宅ローン完済後も抵当権自体は残るため、土地を売却する際は必ず抹消しておかなければいけません。
とはいえ、弁済証書や委任状など、抵当権抹消に必要な書類の多くは、ローン完済時に金融機関から送付されてきます。
自分で用意しなければいけないのは、抵当権抹消に関する登記申請書くらいです。
住民票・印鑑証明書など
最後に、住民票や印鑑証明書といったお馴染みの本人確認書類を揃えたら、いよいよ土地の売却プロセスに進みます。
市役所などで必要書類を準備しておくと売却の手続きがスムーズに進められます。
STEP3. 査定を依頼する
土地の査定は原則、不動産会社に依頼して実施します。査定方法には簡易査定と訪問査定の2種類あり、このうち訪問査定は必須です。
訪問査定は、担当者が現地で周辺環境を詳しく確認することにより、より厳密な査定額が算出されます。
一方、簡易査定はインターネット上で完結し、立地条件や路線価などから大まかな査定額が算出されます。
簡易査定は省略可能であるものの、複数の不動産会社を比較検討する場合は積極的に依頼したいところです。
簡易査定においては、査定金額だけでなく、対応の早さや丁寧さにも着目しておくと、信頼できる不動産会社をより一層見極めやすくなります。
まずはできるだけ多くの不動産会社に簡易査定を依頼したのち、対応や査定額が良好な2〜3社に絞って訪問査定を依頼しましょう。
なお、ここでは単に査定額が高い会社を選べばいい、というわけではありません。正しい不動産会社の選び方については、記事後半にて解説します。
STEP4. 不動産会社を選んで媒介契約を結ぶ
土地を任せたい不動産会社が決まったら、次に媒介契約を結びます。
媒介契約とは、販売状況の報告義務や成約時の報酬など、どのような条件で売却活動を行うのかをあらかじめ取り決める作業です。
媒介契約には、「一般」「専任」「専属専任」の3種類があり、それぞれ契約内容に下表のような違いがあります。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
|---|---|---|---|
販売状況の報告 | 義務なし | 14日に1回以上 | 7日に1回以上 |
レインズ(※)への登録 | 義務なし | 契約後7日以内に登録 | 契約後5日以内に登録 |
複数の不動産会社との重複契約 | あり | なし | なし |
自分で見つけた買い手との直接契約 | あり | あり | なし |
(※)国土交通省指定の不動産流通機構。全国の業者間で物件情報を共有することで、早期の売買につなげる仕組み
どの契約が適しているかは、地域によって異なります。
僻地(へきち)や狭小地といった人気の低い土地をスムーズに売却するには、レインズを通じた全国への情報発信が欠かせません。
販売状況を定期的に把握できる安心感も考慮すれば、売却に苦労しそうな土地は専任系の媒介契約で売り出すのがベストといえるでしょう。
逆に、買い手に困らないような人気エリアの土地を売却する場合、レインズの重要性はそれほど高くありません。
であれば、複数の会社と契約を結べ、かつ自分でも買い手を探せる一般媒介契約の方が、よりスムーズな売却を見込めるはずです。
STEP5. 売り出し価格を決めて売却を始める
媒介契約が成立すると、土地の売り出し価格を決定したのち、実際に販売活動が始まります。
契約上、売り出し価格は売主が自由に決められるものの、特に基準もなく決めるのは推奨しません。
大抵の土地は数百万円〜数千万円クラスの資産であるため、売り出し価格が相場より高すぎると買い手がつかず、逆に安すぎると大損を被ります。
その点、実績十分な不動産会社が出す査定価格は限りなく適正価格に近いため、基本的には査定価格をそのまま売り出し価格として採用するのが無難です。
なお、土地売買における適正価格とは、一般的に「3か月ほどで売れる価格」を指します。
売り出し価格が概ね査定通りであれば、多少の期間売れない程度で、すぐに価格を見直す必要はありません。
ただし、購入希望者が現れた後、値引き交渉が行われる場合もあるので注意しましょう。
STEP6. 契約・引渡しをする
値引き交渉などを経て、最終的な販売価格が決まったら、いよいよ売買契約まで進みます。
契約当日は、契約に関する重要事項の説明を不動産会社が行ったのち、売主・買い手の双方が売買契約書に捺印します。
その後、買い手から土地代の数パーセントにあたる手付金(売買契約において、あらかじめ支払われる違約金)を受け取りつつ、不動産会社に仲介手数料の一部を支払うのが基本的な流れです。無事に引渡し終えれば取引は終了となります。
もちろん、仲介手数料の残りも、同様のタイミングで支払わなければいけません。最終的に、不動産会社による土地所有権の移転登記が行われれば、土地売却は無事完了となります。
STEP7. 確定申告をする
土地売却の利益は税法上の「譲渡所得」にあたり、同所得が発生した翌年には必ず確定申告を行わなければいけません。
申告作業を自身で行う場合は、国税庁ホームページ内の確定申告書等作成コーナー、もしくは民間の確定申告ソフトを利用するのがおすすめです。
ウェブ上で申告書を作成した後は、印刷して税務署に持参するか、e-tax経由で電子申告を行いましょう。
e-taxの利用にはマイナンバーカード、および同カードを読取可能なスマホなどが必要です。
確定申告の時期について
譲渡所得税の確定申告は、所得が確定した年の翌年2月16日〜3月15日の間に済ませなければいけません。
これは普段、源泉徴収や年末調整によって確定申告を免除されている給与所得者も同様です。
申告が遅れてしまうと無申告加算税の対象となり、50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の追徴課税が加わります。
ほかにも、不正確な申告に対しては過少申告加算税、申告後に納期限を超過した場合は延滞税が課されるので注意してください。
関連記事:不動産売却後の確定申告ガイド|いつ必要?やり方は?節税の特例まで徹底解説
土地売却にかかる税金や費用について

土地を売却する際には、手続き上で必要となる費用と、売却によって得た利益に対してかかる税金が発生します。主な内訳は以下の通りです。
1. 売却にかかる費用
売却手続きをサポートしてくれた不動産会社や専門家へ支払う費用の目安は以下の通りです。
売却活動を行う上で必要となる実費や手数料がこれにあたります。
費用の種類 | 内容 | 金額の目安 | 支払うタイミング |
|---|---|---|---|
仲介手数料 | 売却を仲介した不動産会社に支払う成功報酬 | (売買価格 × 3% + 6万円)+ 消費税 ※上限額の速算式 | 決済・引渡し時 |
測量費用 | 土地の境界を確定させるための測量費用 | 35万円~80万円程度 (隣接地の状況や土地の広さによる) | 測量完了後や決済時など、測量会社との契約による |
司法書士への報酬 | 抵当権抹消などの登記手続きを依頼した場合の報酬 | 1万円~3万円程度 | 決済・引渡し時 |
建物の解体費用 | 古家付きの土地を更地にして売る場合の解体費用 | 100万円~300万円程度(建物の構造や規模による) | 解体工事完了後など、解体業者との契約による |
その他 | 廃棄物の撤去費用、交通費、書類取得費など | 実費 | ケースバイケース |
仲介手数料
売却を仲介した不動産会社に支払う成功報酬です。売買価格に応じて上限額が法律で定められています。 (例:売買価格400万円超の場合、速算式は「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」)
測量費用
土地の境界が確定していない場合に、隣地との境界を明確にするための測量にかかる費用です。
その他
・司法書士への報酬: 抵当権抹消などの登記手続きを依頼した場合に支払います。
・建物の解体費用: 古家付きの土地を更地にして売却する場合に必要となります。
2. 売却にかかる税金
土地の売却に際して国や地方自治体に納める税金もいくつかあります。
主に、売却で得た利益に対して課税されます。
税金の種類 | 課税対象 | 税率・税額の目安 | 支払うタイミング |
|---|---|---|---|
譲渡所得税(所得税・住民税など) | 売却によって得た利益(譲渡所得) | 【所有期間5年超】利益の 約20%【所有期間5年以下】利益の 約40% | 売却した年の翌年の確定申告時 |
印紙税 | 不動産売買契約書 | 契約金額に応じて 数千円~数万円<(例:1,000万円超5,000万円以下なら1万円) | 契約時 |
登録免許税 | 抵当権の抹消登記 | 不動産1筆あたり 1,000円 | 決済・引渡し時 |
譲渡所得税(所得税・住民税)
土地を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。これは売却の翌年に確定申告を行い納税します。税率は土地の所有期間によって大きく異なります。
長期譲渡所得
所有期間が5年を超える場合。税率が低く抑えられます。
短期譲渡所得
所有期間が5年以下の場合。税率が高くなります。
印紙税
不動産売買契約書に貼付する印紙代です。契約書に記載される売買金額に応じて税額が決まります。
登録免許税
売却する土地に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合に、その抵当権を抹消するための登記にかかる税金です。
土地売却の税金について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。
土地売却の種類・売却する際の注意点

ひと口に土地売却といっても、貸借地や農地など、土地にはさまざまな種類があります。ここからは、土地を売却する際の細かな注意点を、土地の種類別に見ていきましょう。
家が建っている土地を売却する
家が建っている土地を売却する場合、売り方は主に以下の3つです。
- 中古住宅
- 古家付き土地
- 更地
中古住宅
中古住宅と古家付き土地を比較すると、より高値が付きやすいのは中古住宅です。
その代わり中古住宅として売却する場合は、内装や基礎部分に問題がないことを保証し、購入後に欠陥が発見された際には補修費用などを負担する「瑕疵担保責任」が発生します。
古家付き土地
一方で、古家付き土地には瑕疵担保責任がなく、解体する場合の手間や費用も買い手に一任されます。3つの中でもっとも楽に売却できる方法ですが、売却価格にはあまり期待できません。
更地
更地に関しては、シンプルに買い手を見つけやすいのが一番のメリットといえます。
あらかじめ地盤や土壌を調査し、必要に応じて改良しておけば、新築住宅を建てたい人が比較的早期に買い手となってくれるでしょう。
ただし、更地は固定資産税計算において住宅用地の特例(※)が適用されないため、万が一売れない状態が長引くと、大きな負担がのしかかることになります。
(※)住宅が建っている土地にのみ適用される制度。面積200㎡までの部分は固定資産税が通常の6分の1、200㎡を超える部分は3分の1になる
賃貸中の土地を売却する
賃貸中の土地を売却する場合、売り方は主に以下の2パターンです。
- 入居者がいる状態で、投資用物件として売却
- 入居者を退去させたのち、居住用物件として売却
投資用物件として売却する場合、特に査定価格に影響するのが、投資金額に対する収益割合を示す「利回り」です。
例えば、購入金額が2億円で年間家賃収入が500万円の場合、利回りは2.5%となります(500万÷2億=0.025)。
経費を考慮した実質利回りが、地域の相場より少しでも高い場合には、投資用物件としての売却を検討するといいでしょう。
逆に、投資運用の旨味が少ない低利回りの物件は、部屋を空けてから居住用として売却するのがおすすめです。
一般的に、土地を買う人は投資家よりも自宅購入者の方が多いため、できるだけ早く換金したい場合にも居住用としての売却が選択肢に入ります。
ただし、土地を売却する目的で、入居者を強制退去させるのは法律上不可能です。売却理由などを入居者に丁寧に説明し、同意を得られるよう努めるほかありません。
相続した土地を売却する
故人から相続した土地は、相続開始後3年10か月以内に売却すると、譲渡所得に対して「取得費加算の特例」が適用されます。
取得費加算の特例とは、土地の相続に際してすでに納付した相続税の一部を、譲渡所得計算における取得費に加算できる制度です。
土地売却における取得費加算額は、以下の式で求められます。
取得費加算額=相続税額×土地の相続税評価額÷(相続財産の合計額+債務控除額)
土地の相続税評価額の算出には、路線価方式や倍率方式といった方法があり、詳細は国税庁ホームページ内「土地家屋の評価」に記載されています。
なお、取得費加算の特例を適用する場合は、確定申告の際に「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」の添付が必要です。
共有名義の土地を売却する
土地の共有名義とは、1つの土地を2人以上で共同所有することです。
二世帯住宅の土地を親子で共有したり、相続した土地を兄弟姉妹間で共有したりと、土地を共有名義にするケースは少なくありません。
共有名義の土地全体を売却するには、共有者全員の同意が必要です。
一方で土地の一部、具体的には自身が持つ所有権割合(共有持分)の範囲内であれば、誰に連絡せずとも自由に売却できます。
とはいえ、土地の一部だけを売ったところで需要はほとんど見込めないため、現実的には専門の買取業者に安値で売却する可能性が高くなります。
また、いずれかの共有持分が売却されると、ほかの共有者にとっては、見知らぬ購入者と土地を共有している状態になります。
これが無断で行われたとなれば、大なり小なりトラブルは避けられないでしょう。
そもそも共有名義を設定しないのが一番ですが、時すでに遅しという場合は、共有状態の解消法について早めに弁護士に相談してください。
農地・山林など山地を売却する
農地売却には、農地のまま売却するか、宅地転用して売却するかの2パターンがあります。
農地のまま売却する場合
農地のまま売却する場合は、地域の農業委員会から許可を得た上で、同委員会が認定した農家に売却するのが基本の流れです。
売却にあたって農業委員会の斡旋を受けると、「農地を売った場合の課税の特例」として800万円の特別控除が適用されます。
宅地転用して売却する場合
一方、宅地転用して売却できるのは、原則として市街化区域内の「第3種農地」のみです。
市街地近郊農地や未整備農地を指す「第2種農地」に該当する場合は、第3種農地が周辺にないときのみ転用を許可されます。
また、宅地転用においては区分条件の他にも、関係権利者の同意や周辺への被害防除処置(土砂の流出防止、排水機能の保全など)といった一般基準に注意が必要です。
一般基準を満たした第3種農地に関しては、農業委員会へ転用の届出を提出すれば、受理通知が届き次第、売却活動を始められます。
第2種農地に関しては、農業委員会経由で都道府県への許可申請が必要な関係上、売却活動開始まで数か月待たされることも珍しくありません。
山地の売却は農地と異なり、公的な許可を要さずに始められます。
ただし、土地部分が譲渡所得なのに対して立木部分が山林所得に分類されるなど、確定申告が多少複雑になることは覚えておきましょう。
一般的な不動産会社の中で、山地の測量や立木の査定を正確に行える会社は少ないため、山地売却においては山林専門の仲介業者を頼るのがおすすめです。
土地をより良い条件で売るための4つのコツ

土地売却の利益を左右するのは、不動産会社の手腕だけではありません。
相場の調査や売却時期の見極め、事前の土地の手入れなど、売主自身でもやれることは多々あります。以下で詳しく見ていきましょう。
1.事前に相場を調べておく
土地価格の指標には、主に「公示地価」や「実勢価格」といったものがあります。
公示地価
公示地価とは、都市部や都市近郊における標準的な土地の価格です。
国土交通省管轄の土地鑑定委員会が、同一の標準値を毎年鑑定していることから、地価の変動傾向を知る上で非常に信頼性の高い指標といえます。
例えば、公示地価の上昇が直近数年続いていることが分かれば、翌年を見越して多少強気な価格で売り出すといった選択肢も生まれるでしょう。
公示地価は、国土交通省ホームページ内の地価公示ページより確認可能です。
実勢価格
実勢価格とは、売買が成立した土地における実際の取引価格です。
国土交通省が提供する不動産情報ライブラリにて、「不動産価格の情報をご覧になりたい方へ」より確認できます。
実勢価格のデータには、土地の形状や前方道路の幅員といった様々な情報が記載されていますから、まずは自身が所有するものに近い条件の土地を探してみましょう。
その土地の㎡単価に、自身が所有する土地の面積を掛け算すれば、取引価格の目安が簡単に求まります。
不動産会社に査定を依頼すれば、いずれの指標も徹底的に調べてもらえるはずです。
ですが、あらかじめ自分でもある程度調べ、査定金額の妥当性を判断できるようになっておくことは、より高値での売却を目指す上で大いに役立ちます。
関連記事:土地価格の調べ方は?価格の種類や値段が決まる要因まで解説
2.土地を売るタイミング
土地を売るタイミングを見極める上で、特に重要なのは「市場のニーズ」と「土地の所有年数」です。
市場のニーズ
まず、土地をはじめとした不動産のニーズが高まるのは、一般的に引っ越しシーズンと呼ばれる2〜3月の新年度付近です。
土地売買における適正価格が、売買成立に3か月程度かかる想定ということを考えると、引っ越しシーズンを狙うなら遅くとも年末には売り出すべきでしょう。
高速道路の開通や大型商業施設のオープンなどで、土地の利便性が大きく向上すると見込まれる場合は、そこにタイミングを合わせて売り出すのも一手です。
土地の所有年数
土地の所有年数に関しては、以下3つに分類されます。
- 5年以下
- 5年以上〜10年以下
- 10年以上
それぞれ譲渡所得にかかる税率が大きく異なるため注意してください。
所有期間 | 5年以下 | 5年超10年以下 | 10年超(軽減税率の特例) |
|---|---|---|---|
税率(居住用区分) | 39.63% | 20.315% | 課税所得6,000万円以下の部分:14.21% 同6,000万円超の部分:20.315% |
(税率は所得税と住民税の合算)
土地の所有年数が5年以内の場合、5年以上と比べて2倍近くの税率がかかります。できれば5年以上になるまで土地を所有されることをおすすめします。
3.土地を綺麗にしておく
満足のいく価格で土地を売却するには、地面の凹凸を平坦にし、雑草や埋設物などを取り除く「整地」が欠かせません。
整地工事は解体業者やリフォーム業者などが提供しており、工事プランは以下の4種類に分けられます。
- 粗仕上げ
- 砕石舗装
- 真砂土舗装
- コンクリート舗装
粗仕上げ
粗仕上げは、地面の凹凸や雑草等の障害物を除去する最低限の整地であり、相場は1㎡あたり500円前後です。
砕石舗装
砕石舗装は、整地後の土地に砕いた石を敷き詰める作業であり、相場は1㎡あたり5,000円前後です。
砕石舗装で予め建造物の基礎を作っておけば、直ちに住宅工事が可能な状態になる上、アルカリ性の砕石を用いれば除草対策としても役立ちます。
真砂土舗装
真砂土舗装は、整地後の土地に花崗岩由来の真砂土を敷き詰める作業であり、相場は1㎡あたり5,000円前後です。
真砂土には吸水性の高さや表面温度の上がりにくさといった強みがある上、他の舗装に比べて単純に見栄えが良いというメリットもあります。
コンクリート舗装
コンクリート舗装は、砕石舗装の上からコンクリートを敷いて補強する作業であり、相場は1㎡あたり1万円弱です。圧倒的な耐久性に加え、デザインの自由度が高いというメリットもありますが、一度舗装すると簡単には撤去できません。
4.土地の売却に強い不動産会社を選ぶ
土地の売却においては、相場の調査や売却タイミングの見極めなど、売主自身でやれることも多々あります。
それでも、信頼できる不動産会社や関連業者を選ぶことが、土地を良い条件で売るために必須であることに変わりはありません。
その不動産会社が土地の売却に強いか否かを見極める具体的な方法については、次の見出しで解説します。
土地売却における不動産会社の選び方

土地売却に強い不動産会社を見極めるポイントは、土地や周辺地域に関する知識量、および過去の取引実績などです。
また、土地をより良い条件で売るための方針について、担当者がどこまで親身にアドバイスしてくれるかも、売却の利益を左右します。以下で詳しく見ていきましょう。
土地売却に精通している
まずは検討対象の不動産会社が、土地売却にどこまで精通しているかを見極めましょう。
土地を良い条件で売却するためには、土地そのものの知識だけでなく、利便性や交通量といった地域の特色に関する情報も必要になります。
また、同一地域内での取引情報や、条件が類似した土地の取引情報などを、どれほど豊富に抱えているかも重要です。
肝心の見極め方については、不動産会社に訪問査定を依頼したのち、査定の根拠を詳しく聞くのが基本となります。
地域の情報や類似の取引事例について、どこまで詳細に説明がなされるかで、不動産会社のおおよその手腕が見えてくるでしょう。
なお、不動産会社は売買成立後の仲介手数料によって利益を得ているため、査定の段階で費用が取られることはありません。
土地売却の実績が豊富
土地売却の実績は、不動産会社にとってもっとも分かりやすいアピールポイントです。
不動産会社の広告やウェブサイトを見れば、「累計取引件数〇万件」「顧客満足度No.1」といった煽り文句がほぼ必ず目に入ることでしょう。
しかし、土地を売る側にとって大事なのは、あくまでも自分の土地がスムーズに売れるかどうかです。
同じ地域の土地や、地形条件が似た土地の取引実績のみを検討材料としてください。
また、単純な実績数だけでなく、取引1件1件の中身を精査することも重要です。
売れるまでの期間や購入者の属性、売り出し価格と成約価格のギャップなどをチェックしておけば、当該不動産会社を利用した販売活動をより深くイメージできることでしょう。
これらの情報に関しては、訪問査定時に直接聞いてもいいですが、最初からウェブサイト等に掲載されている方がより信頼できます。
担当者が誠実
信頼できる不動産会社を見極める最後の決め手は、担当者の営業の仕方です。
誠実な担当者であれば、市場の傾向や売主の状況を十分考慮し、場合によっては売却以外の選択肢も提示してくれます。
また、みだりに専門用語を使わず、不動産に詳しくない相談者でも容易に理解できるような説明を行うのも、優秀な不動産会社の特徴です。
注意すべき担当者の特徴として「とにかく契約を急ぐ」が挙げられます。
「すぐに売却すべき理由」ばかりを熱弁される場合や、デメリットに関する質問に曖昧な回答しかもらえない場合は、その場で契約せず、一度熟考されることを強くおすすめします。
また、査定価格を無駄に高くつけたり、ホームページ等に全く記載のないキャンペーンを突然紹介してきたりするのも、怪しむべき不動産会社の特徴です。
なお、過剰な査定価格に関しては、事前に相場を調べておくことで避けることができます。
不動産の一括査定なら「MOTA不動産査定」がおすすめの理由
「MOTA不動産査定」には、選ばれる3つのポイントがあります。
Point 01:優良企業を厳選
独自の審査基準をクリアした信頼できる不動産会社だけをご紹介。安心して査定を依頼できます。
Point 02:最大6社を比較
複数の査定額を比較できるから、相場を把握しやすく、より高く売れるチャンスが広がります。
Point 03:60秒でかんたん依頼
面倒な手続きは不要。スマホやパソコンから、簡単入力ですぐに査定依頼できます。
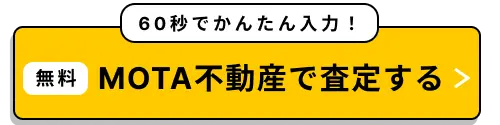
まとめ
土地の売却は、土地の現状調査や必要書類の用意を経て、不動産会社に査定および仲介を依頼するのが基本的な流れです。
また、相続する土地の種類に応じて、どのような売り方が一番お得かを検討するとともに、利用可能な税制上の特例がないかも確認しておきましょう。
あとは相場の事前調査や土地の舗装などを経て、慎重な不動産会社選びを心がければ、土地売却で損をする心配はなくなります。
土地に関する関連記事:
土地にかかる固定資産税はいくら?種類や計算方法、節税対策を紹介
