相続した不動産、どうする?売却のメリットから税金までわかりやすく解説
最終更新日: 2025-08-04
.png)
- もくじ
「親から家を相続したけど、兄弟でどう分ければいい?」「遠方にある実家が空き家になっていて、管理が大変…」
相続した不動産の扱いは、多くの人が直面する悩みの種です。そのまま持ち続けると、固定資産税や維持費の負担、空き家トラブルのリスクがのしかかります。
そんな問題を解決する有効な手段が「売却」です。売却して現金化すれば、財産を公平に分配でき、管理の負担からも解放されます。
本記事では、相続した不動産を売却するメリットから、複雑な手続きの流れ、知っておきたい税金の話、そして最大3,000万円の節税につながる特別控除まで、専門家が分かりやすく解説します。後悔しない相続のために、知っておくべきポイントを一緒に確認していきましょう。
相続した不動産を売却する4つのメリット

相続した不動産を売却することには、多くのメリットがあります。
ここでは、代表的な4つのメリットをそれぞれ詳しく解説していきます。
1. 現金化により、相続財産を公平・平等に分配できる
相続した不動産を売却する最大のメリットは、財産を平等に分配できることです。
不動産は物理的な資産であり、分割が難しいため、相続人が複数いる場合には売却して現金化することで、全員が公平に取り分を受け取ることが可能になります。
共有で起こりがちなトラブルを回避
例えば、相続人が兄弟姉妹である場合、ひとつの不動産をそのまま共有することは難しいでしょう。
誰がどの部分を使用するのか、管理費用はどのように分担するのか、使用の頻度や方法に違いが出ることもあり、トラブルの原因となることが多いです。
これに対して、不動産を売却して得た現金を分割すれば、各相続人が自由にそのお金を使うことができ、公平かつ平等に分配することができます。
相続税の支払いにも充当できる
また、不動産の売却により得られる現金は、相続税の支払いにも充てることができます。
不動産は相続税の評価額が高いため、相続税の負担が大きくなることがありますが、現金化することで相続税の支払いもスムーズに行うことができます。
このように、相続不動産を売却することで、相続人全員に対して公平かつ適切に財産を分配することが可能となります。
これにより、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができ、相続手続きを円滑に進めることができるのです。
2. 固定資産税や修繕費などの「維持費」が不要になる
不動産を所有していると、維持費がかかります。例えば、固定資産税や管理費、修繕費用などです。
これらの費用は、相続人にとって大きな負担となることがあります。しかし、不動産を売却すれば、これらの維持費を支払う必要がなくなります。
毎年発生する固定資産税や管理費
固定資産税は、毎年課される税金であり、不動産を所有している限り支払わなければなりません。
特に、土地や建物の評価額が高い場合、固定資産税が高額になることがあります。
また、マンションなどの共有部分がある不動産では、管理費や修繕積立金も毎月必要です。
これらの費用を長期間にわたって支払うことは、相続人にとって大きな経済的負担となることが多いです。
関連記事:
固定資産税はいくら?戸建て・マンションの計算シミュレーションと賢い軽減方法
土地にかかる固定資産税はいくら?種類や計算方法、節税対策を紹介
将来にわたる経済的負担を軽減
さらに、不動産の管理には定期的な修繕やメンテナンスも必要です。
これらの費用も積み重なると大きな金額になり、相続人全員で負担する必要があります。
しかし、不動産を売却すれば、これらの維持費や管理費を支払う必要がなくなり、経済的な負担を軽減することができます。
前述のように不動産を売却して得た現金は、相続人がそれぞれの用途に応じて自由に使うことができます。
3. 手間と時間のかかる「管理負担」から解放される
不動産の管理は、時間と労力を要する作業です。
特に、複数の相続人が共同で所有する場合、誰がどの部分を管理するのか、どのように管理費用を分担するのかといった問題が生じることが多いです。
誰が管理するのか? 相続人の間の新たな火種に
例えば、賃貸物件の場合、入居者の募集や契約手続きや家賃の管理、修繕やメンテナンスなど、さまざまな管理業務が必要です。
これらの業務を相続人全員で分担することは現実的には難しいため、専任の管理会社に依頼することが多くなりますが、それでも相続人としての責任は残ります。
一方、不動産を売却すれば、これらの管理業務から解放されます。
相続人は、それぞれの生活や仕事に専念することができ、管理業務によるストレスや負担を感じることがなくなります。
また、管理に関するトラブルや問題が発生することもなくなり、相続人間の関係も円滑に保つことができます。
遠方に住んでいる場合は特に大きな負担
さらに、遠方に住んでいる相続人にとっては、不動産の管理は特に大きな負担となります。
不動産の現地に頻繁に行くことが難しい場合、管理が行き届かず、物件の価値が下がることもあります。
このようなリスクを避けるためにも、不動産を売却することは有効な手段です。
4. 放置すれば危険な「空き家トラブル」を未然に防げる
相続不動産が空き家となっている場合、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
防犯・防災・景観悪化など近隣トラブルの原因に
雑草が生い茂り、外観が荒れることで景観を損なうことにもつながりますし、不法侵入など防犯上のリスクも高まるでしょう。
また、空き家は災害時に倒壊の危険があるため、自治体からの指導や命令を受けることもあります。
これに対して、不動産を売却することで、空き家に関するトラブルを回避することができます。
売却すれば、新しい所有者が物件を適切に管理・利用することが期待でき、近隣住民とのトラブルも防ぐことができ、防犯面でも安心です。
放置することで資産価値が下落するリスク
さらに、空き家を長期間放置すると、不動産の価値が下がることがあります。
建物が老朽化し、修繕費用がかさむため、売却時に得られる金額が減少するリスクも上がります。
早期に売却することで、このようなリスクを回避し、適切な価格で売却することが可能になるでしょう。
このように、相続不動産を売却することで、空き家に関するさまざまなトラブルを未然に防ぐことができ、安心して相続手続きを進めることができるのです。
相続した不動産を売却する流れ

相続した不動産を売却する際には、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。
これらのステップを順に進めることで、スムーズかつ効率的に売却手続きを完了することができます。
STEP1.相続の確認と手続き
相続した不動産を売却するためには、まず相続の確認と手続きを行う必要があります。この段階では、相続人が誰であるかを確認し、相続登記を完了させることが求められます。
相続の確認
相続の確認とは、相続人が誰であるかを確定する作業です。遺産分割協議書や遺言書がある場合は、その内容に基づいて相続人を特定します。
また、法定相続分に従って相続人を決定する場合もあります。この確認作業は、相続不動産を売却する際の基礎となる重要なステップです。
相続人が確定したら、次に行うのは遺産分割協議です。遺産分割協議は、相続人全員が集まり、相続財産の分配方法を話し合う場です。
ここで不動産の売却についても議論し、全員の合意を得ることが必要です。この合意が得られない場合、あとあとの手続きに支障をきたす可能性があります。
相続登記を行う
相続登記とは、不動産の所有者名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。
この登記を行うことで、相続不動産が正式に相続人の所有物となり売却が可能となります。相続登記を行わない限り、不動産を売却することはできません。
相続登記の手続きには、遺産分割協議書や被相続人の死亡証明書、相続人全員の印鑑証明書などが必要になります。
これらの書類を揃えて法務局に申請することで、相続登記が完了します。
相続登記は専門的な知識が必要な場合もあるため、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
STEP2.不動産会社へ査定を依頼する
相続した不動産の売却を進めるためには、まず不動産の価値を知る必要があります。
そのため、不動産会社に査定を依頼し、相場を把握することが重要です。
相場がどれくらいか把握する
不動産の相場を把握するためには、複数の不動産会社に査定を依頼することが有効です。
複数の査定結果を比較することで、より正確な不動産の価値を知ることができます。
査定は無料で行ってくれる会社が多いため、気軽に依頼することができます。
なお、査定の際には、不動産の立地や築年数、状態などが評価のポイントとなります。また、周辺の市場動向や近隣の取引事例も参考にされます。
これらの情報をもとに不動産会社は適正な価格を提示してくれます。
売却に必要な書類を準備する
不動産の売却には、多くの書類が必要です。主な書類には、権利証や登記簿謄本、固定資産税納税通知書、建物図面や間取り図などがあります。
これらの書類を事前に準備しておくことで、売却手続きをスムーズに進めることができます。
また、相続不動産の場合は、相続登記が完了していることが前提となります。
相続登記が完了していない場合は売却手続きが進められないため、早めに手続きを完了させる必要があります。
さらに、売却活動を始める前に、不動産の状態を整えることも欠かせません。
必要に応じてリフォームや修繕を行い、物件の魅力を高めることで、より高い価格で売却できる可能性が高まります。
関連記事:不動産売却はどこがいい?選び方の基準や売却のコツを解説
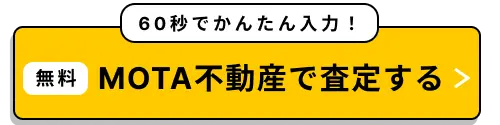
STEP3.売買契約書を締結する
売却活動を通じて買い手が見つかったら、次に売買契約書を締結します。売買契約書は、不動産の売買条件を詳細に記載したとても重要な書類です。
契約書には、売買価格や引渡し日、支払い方法、手付金の額などが記載されます。契約書を締結する際には、双方が内容を十分に理解し、合意することが必要です。
また、契約書の内容に不明点がある場合は、事前に不動産会社や弁護士に相談することをおすすめします。
売買契約書が締結されると、買い手から手付金が支払われ、契約の証としての意味合いがあり、売買代金の一部として充当されます。
STEP4.決済・引渡しを行う
売買契約が締結された後は、決済と引渡しを行います。決済とは残りの売買代金を受け取り、物件の所有権を買い手に移転する手続きです。
決済の際には、買い手から残りの売買代金が支払われ、同時に不動産の所有権移転登記が行われます。登記手続きは、司法書士が代行して行うことが一般的です。
また、固定資産税や管理費の清算もこの段階で行われます。
引渡しが完了すると、相続不動産の売却手続きは終了です。買い手に対して物件の鍵や関連書類を引き渡し、正式に物件の所有権が移転します。
STEP5.利益が出た場合は確定申告を行う
相続した不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税や住民税が課されるため、必ず「確定申告」を行う必要があります。
確定申告とは、1年間の所得とそれに対する税額を計算し、国に報告・納税するための一連の手続きです。
- 申告期間:不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日
- 申告内容:売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」を計算して申告
- その他:手続きが複雑で不安な場合は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
詳しい申告方法や必要書類、使える控除については、下記の記事で徹底解説しています。
不動産売却後の確定申告ガイド|いつ必要?やり方は?節税の特例まで徹底解説
相続した不動産を売却する際にかかる税金について
相続不動産を売却する際には、さまざまな税金がかかることがあります。
相続税や譲渡所得税などが代表的なものです。これらの税金について理解しておくことで、適切な税務対策を講じることができ、最終的な手取り額を最大化することが可能です。
現物分割
現物分割とは、相続財産をそのままの形で相続人に分配する方法です。
不動産を売却せずにそのまま保有する場合、この方法が適用されます。
この場合でも、いくつかの税金が発生することを理解しておく必要があります。
相続税
相続税は、被相続人が亡くなった時点での不動産の評価額に基づいて計算されます。
この評価額は、路線価や固定資産税評価額を基に決定されます。
相続税の申告と納付は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。
固定資産税
次に、不動産を保有している間に発生する固定資産税です。これは毎年課される税金で、所有者が支払う義務があります。
相続によって不動産を取得した場合、その年の固定資産税は相続人が支払うことになります。この税金は、不動産の評価額や利用形態によって異なります。
さらに、不動産を共有する場合には、共有者全員で管理費用や修繕費用を負担する必要があります。
これらの費用は、長期的に見て大きな負担となることがあります。
現物分割は、相続人全員が不動産を共同で所有するため、管理や費用の分担について事前に明確にしておくことが重要です。
このように、現物分割を選択する場合には、相続税や固定資産税、管理費用などのコストを考慮する必要があります。
また、相続人全員が協力して不動産を管理しなければならないため、相続人間の信頼関係や協力体制が求められます。
換価分割
換価分割とは、相続財産を売却して現金化し、その現金を相続人に分配する方法です。
換価分割は、不動産を複数の相続人で分けることが難しい場合や、公平に分配することが求められる場合に有効です。
しかし、換価分割にはいくつかの税金がかかることを理解しておく必要があります。
譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却することで得られる利益に対して課税される税金です。
譲渡所得は、売却価格から取得費用と譲渡費用を差し引いた金額で計算されます。
この所得に対して、一定の税率が適用されます。
譲渡所得税の税率は、保有期間によって異なり、短期保有の場合は高く、長期保有の場合は低くなります。
住民税
次に、住民税です。譲渡所得に対しては、住民税も課税されます。
住民税は、譲渡所得の金額に対して一定の税率が適用され、納税義務者の居住地に基づいて計算されます。
住民税の申告と納付は、確定申告と同時に行う必要があります。
さらに、不動産の売却に際しては、不動産会社に支払う仲介手数料や、登記費用などの諸費用も発生します。
これらの費用も考慮した上で、売却後に手元に残る金額を計算することが重要です。
換価分割を選択する場合、相続人全員が売却に同意し、適切な売却手続きを行うことが求められます。
売却益を公平に分配するためには、相続人間の合意と信頼関係が必要です。
また、売却後の税金対策についても事前に計画を立てることが重要です。
このように、換価分割には譲渡所得税や住民税、仲介手数料などのコストがかかりますが、不動産を現金化することで、相続人全員が公平に財産を受け取ることができます。
この方法は、相続人間のトラブルを避け、公平かつ円滑な相続を実現するために有効な手段となります。
相続した不動産の売却における節税対策・特別控除

相続不動産を売却する際には、節税対策や特別控除を活用することで、税負担を軽減することができます。
特に大きな節税効果が期待できるのが、3,000万円特別控除です。この特別控除を適用することで、譲渡所得税の負担を大幅に減らすことができます。
自宅を売ったときの3,000万円特別控除
自宅を売却する際には、3,000万円特別控除を適用することができます。
この特別控除は、譲渡所得から3,000万円を差し引くことができるため、譲渡所得税の負担を大幅に軽減することが可能です。
まず、特別控除を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
売却する不動産が自宅であること、売却価格が適正であること、そして売却した年の1月1日時点でその不動産を所有していることが条件となります。
また、過去にこの特別控除を適用したことがない場合に限り、再度適用することができます。
計算シミュレーション
例えば、1億円で自宅を売却し、その取得費用が5,000万円であった場合、通常は5,000万円の譲渡所得が発生します。
しかし、3,000万円特別控除を適用することで、譲渡所得が2,000万円に軽減されます。
この軽減された譲渡所得に対してのみ、譲渡所得税が課されるため、大幅な節税効果が期待できます。
特別控除を適用するための手続きには確定申告が必要です。申告の際には、売買契約書や登記簿謄本などの書類を提出する必要があります。
これらの書類を事前に準備しておくことで、スムーズに手続きを進められるでしょう。
このように、自宅を売却する際の3,000万円特別控除は、譲渡所得税の負担を大幅に減らす効果的な節税対策です。
条件を満たしている場合は、積極的に活用することをおすすめします。
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する際にも、3,000万円特別控除を適用することができます。
これは、相続財産の有効活用を促進するための制度であり、相続人にとって大きなメリットがあります。
この特別控除を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、相続開始日から3年以内に売却することが条件となります。
また、売却する空き家が相続開始時に被相続人が住んでいた住宅であること、売却価格が1億円以下であること、空き家の状態が維持されていることなどが条件です。
計算シミュレーション
例えば、相続した空き家を5,000万円で売却し、その取得費用が1,000万円であった場合、通常は4,000万円の譲渡所得が発生します。
しかし、3,000万円特別控除を適用することで、譲渡所得が1,000万円に軽減されます。
この軽減された譲渡所得に対してのみ譲渡所得税が課されるため、大幅な節税効果が期待できます。
また、特別控除を適用するためには確定申告が必要です。
申告の際には、相続関係を証明する書類や売買契約書、登記簿謄本などが必要です。
このように、相続した空き家を売却する際の3,000万円特別控除は、譲渡所得税の負担を大幅に減らす効果的な節税対策です。
条件を満たしている場合は、積極的に活用することをおすすめします。
参考:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
特別控除を利用する場合は3年以内を目安に
特別控除を利用するためには、タイミングも重要です。
特に相続した不動産については、相続開始から3年以内に売却することが求められます。
これにより、特別控除の適用を受けやすくなります。
相続開始から「3年後の年末」が売却期限
相続不動産の売却を計画する際には、まず相続開始日を確認し、そこから3年以内に売却手続きを完了させるように計画を立てましょう。
この期間を過ぎると、特別控除の適用を受けることが難しくなるため、注意が必要です。
例えば、2018年1月1日に相続が開始された場合、2021年12月31日までに売却を完了させる必要があります。
この期間内に売却を行うことで、3,000万円特別控除を適用し、譲渡所得税の負担を大幅に軽減することができます。
市場の動向や物件の状態も考慮しよう
また、売却のタイミングを見計らう際には、市場の動向や不動産の状態も考慮することが重要です。
不動産市場が活発な時期に売却することで、より高い価格で売却できる可能性があります。
さらに、売却前に必要な修繕やリフォームを行い、不動産の価値を高めることも有効です。
控除の適用には確定申告が必須
特別控除を適用するための確定申告は、売却後に行います。
税務署に対して正確な情報を提供し、適切に手続きを行うことで、特別控除の適用を受けることができます。
このように、特別控除を利用する場合は、相続開始から3年以内に売却することを目安に計画を立てることが重要です。
タイミングを見計らい、適切な手続きを行うことで、譲渡所得税の負担を大幅に減らすことができます。
まとめ
相続不動産の売却には多くのメリットがあることを解説しました。
ですが、売却して利益が発生した際は、税金などが複雑に絡み合うので、お金の計算などはとくにややこしく感じるかと思います。
手続きが大変になるので、税理士など専門家に依頼されることをおすすめします。
また、不動産を相続する場合はさまざまな手続きも発生します。
手間と時間がかかる作業でもあるので、申請する際はできるだけ書類に不備がないようしっかりと必要書類を揃えてから手続きを始めるといいでしょう。
関連記事:
土地の相続税はいくら?計算方法から節税の特例まで分かりやすく解説
