不動産売却で税金はいくらかかる?計算方法や節税対策を紹介
最終更新日: 2025-07-30
.png)
- もくじ
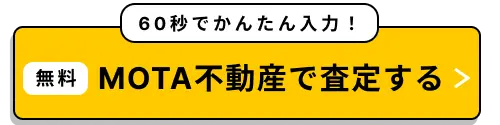
不動産を売却する際、税金がいくらかかるのか気になる人も多いでしょう。
仕組みが複雑なこともあり、税金への知識が不足していると、思わぬ税負担を負う可能性もあります。
この記事では、不動産売却にかかる税金について、分かりやすく解説します。
確定申告のポイントや特例・控除の活用方法も紹介していますので、不安や疑問を解消し、不動産売却をスムーズに進めてください。
不動産を売却すると税金はいくらかかる?

不動産を売却する際には、多くの税金が関わってきます。
売却益が出た場合には、住民税や所得税、復興特別所得税がかかります。
また、売却手続きに関連する税金や費用も無視できません。
【家を売却するとかかる税金】 ・住民税 ・譲渡所得税 ・復興特別所得税 ・登録免許税 ・印紙税 ・仲介手数料の消費税 |
|---|
ここでは、各税金の詳細について紹介します。
売却益が発生するとかかる税金
不動産を売却した際に、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益(譲渡所得)が発生した場合、以下の税金がかかります。
住民税
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、住民税が課されます。
住民税の税率は、給与所得にかかる税金とは税率が異なります。
売却した不動産を保有していた期間が5年以下の場合は短期譲渡所得が9%、5年超の場合は長期譲渡所得となり5%の税率になります。
譲渡所得税
住民税と同様に、譲渡所得に対して所得税も発生します。
所得税の税率も売却した不動産を保有していた期間によって異なります。
税率は5年以下の短期譲渡所得では30%、5年超の長期譲渡所得では15%になります。
復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興を支援するために導入された税金です。
この税金は、平成25年(2013年)から令和19年(2037年)までの期間に不動産を売却した場合に適用されます。
その税率は所得税に対して2.1%がかかります。
売却の手続きにかかる税金
不動産を売却する際には、売却益にかかる税金だけでなく、売買手続きそのものに関連するさまざまな税金がかかります。
これらの税金は、不動産の所有権移転や契約締結といった手続きを進める上で必ず発生するため、売却を検討する際には知っておく必要があります。
税金の種類 | 費用相場 | 支払いのタイミング |
|---|---|---|
登録免許税 | 2,000円程度 | 抵当権抹消登記の申請時 |
印紙税 | 10,000円〜30,000円程度 | 不動産の売買契約書交付時 |
登録免許税
不動産の売買が成立し、所有権が新しい所有者に移転する際には、必ず「所有権移転登記」という手続きが必要です。
この登記を行う際に、国に支払う税金が登録免許税です。
不動産を売却した場合には、登録免許税は「不動産の価額」の2%です。
なお、土地の売買の際の名義変更の税金は、令和8年(2028年)3月31日までに登記をする場合は、1.5%に軽減されます。
この「不動産の価額」は不動産の売却額ではなく、「市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格」という点に注意が必要です。
固定資産課税台帳に登録された価格がない場合、登記官が認定した価額になります。
この登録免許税ですが、買主側が支払うのが一般的です。
ただし、不動産に銀行の抵当権を設定している場合は、登録免許税を支払う必要があります。
不動産売却の際に住宅ローンを完済し、抵当権の登記を抹消してもらうための費用がかかります。
印紙税
不動産を売却する際に『不動産売却契約書』を作成しますが、収入印紙(印紙税)の貼り付けが必要となります。
契約(売却)金額によって、次の通り印紙税の金額が定められています。
なお、平成26年(2014年)年4月1日〜令和9年(2027年)3月31日までの期間は、軽減税率が適用されます。
不動産売却価格 | 税率 | 軽減税率 |
1万円以下 | 非課税 | 非課税 |
1万円超~10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超~1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円超~5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5千万円超~1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超~5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超~10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超~50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
仲介手数料の消費税
不動産会社に売買の仲介を依頼した場合、仲介手数料が発生しますが、その仲介手数料に対しても消費税が発生します。
消費税の税率は、売買契約を結んだ時点の税率で、2025年7月現在は10%です。
※最新の消費税率については、国税庁などでご確認ください。
仲介手数料は法律で上限が定められており、400万超の売買価格の場合には『不動産の売買価格(税抜)3% + 6万円』が上限額です。
例えば、税抜き2000万円の不動産の場合、仲介手数料の上限は2000万円×0.03+6=66万円で、消費税として10%の6万6千円が発生するため、合計72万6千円になります。
関連記事:【早見表付き】不動産売却の仲介手数料はいくら?安くなるカラクリや注意点まで解説
譲渡所得税は物件の所有年数で変わる
不動産を売却した際に発生する譲渡所得税は、その不動産を所有していた期間によって税率が大きく変わります。
これは、長期にわたって資産を保有していた場合と、短期的に売却した場合とでは、経済的な状況や税負担が異なるため、税制上も異なる扱いを受けるためです。
譲渡所得税は、以下の2つの期間に分けられます。
- 短期譲渡所得:不動産を所有していた期間が5年以下の場合
- 長期譲渡所得:不動産を所有していた期間が5年を超える場合
それぞれの期間における譲渡所得税の税率は、以下のようになります。
住民税 | 所得税 | 復興特別所得税 | 合計税率 | |
|---|---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 9% | 30% | 0.63% | 39.63% |
長期譲渡所得 | 5% | 15% | 0.315% | 20.315% |
ただし、保有期間の「5年」は「不動産を売却した年の1月1日」が基準となります。
例えば、2017年1月20日に所有した物件を2022年12月10日に売却した場合には、実質6年弱保有しています。
しかし、基準上は5年保有となるため、短期譲渡所得の税率になります。
不動産売却にかかる税金の計算方法

不動産を売却する際には、今回紹介したさまざまな税金が発生します。
その計算は複雑で、専門知識がないと戸惑ってしまうでしょう。
ですので、不動産売却にかかる税金の計算方法を具体的例でわかりやすく解説します。
まず、不動産を売却した際に得られる利益である「譲渡所得」を計算します。
譲渡所得は、以下の式で算出されます。譲渡所得に税率(39.63% または 20.315%)を掛けた金額が税金となります。
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 |
|---|
- 売却価格:不動産を売却した金額です。
- 取得費:不動産を購入した際に支払った金額、仲介手数料、登記費用などの合計です。
- 譲渡費用:不動産を売却する際に支払った仲介手数料、広告費、司法書士費用などの合計です。
【不動産売却にかかる税金のシミュレーション】
例えば、以下のような条件で不動産を売却したケースを考えてみましょう。
前提条件
・購入価格(取得費):1,000万円(約10年前に購入)
・売却価格:2,000万円
・仲介手数料:40万円
・その他譲渡費用(登記費用・測量費など):10万円
・所有期間:10年以上(※長期譲渡所得に該当)
- 譲渡所得の計算
譲渡所得は、以下の式で算出されます:
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
したがって、
譲渡所得 = 2,000万円 −(1,000万円+40万円+10万円)= 950万円
- 税率と税額の計算
所有期間が 10年超(※長期譲渡所得) の場合、以下の税率が適用されます:
所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%(15%×2.1%)
合計税率:20.315%
これを元に計算すると、
納税額 = 950万円 × 20.315% ≒ 約193万円 |
|---|
この場合、約193万円が譲渡所得税として課税されることになります。
残る手取り額は、約2,000万円 − 約193万円 = 約1,807万円 となります。
「取得費が不明な場合」には、売却価格の5%を概算取得費とする「概算取得費課税」が適用される可能性があります。
また、長期譲渡所得か短期かで、税率は大きく異なります。
不動産売却で活用できる特例・控除について

計算の実例で紹介したように、不動産を売却する際に発生する税金は、大きな負担となることがあります。
しかし、税金を軽減できるさまざまな特例・控除が設けられています。
これらの制度を活用することで、大幅な節税が可能になるケースもあります。
ここでは、不動産売却で活用できる主な特例・控除について解説します。
3,000万円の特別控除
マイホームを売却する際に最もよく利用される特例です。
一定の要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円まで控除できるため、大幅な節税が期待できます。
適用条件は次の通りです。
- 現在、主に住んでいる自宅であること。
- 以前住んでいた家の場合、住まなくなって3年経過した年の12月31日までに売ること。
- 建物を解体している場合、[2]に加えて土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、その土地を賃貸していないこと。
- 過去2年間で、マイホームの買い替えや交換の税金控除を受けていないこと。
- 過去2年間にこの特別控除や、マイホームの売却損に関する税金控除を受けていないこと。
- 売り主と買い主が親子や夫婦、同族会社などの特別な関係でないこと。
- 災害で家が壊れた場合は、住まなくなった後3年経過した年の12月31日までに敷地を売却した場合。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続や遺贈によって相続した、亡くなった人が住んでいた家や土地を売却した場合、条件を満たせば最大3,000万円※まで税金から控除することができます。
(※相続人の数が3人以上である場合は2,000万円まで)
この特例は、適用期限が令和9年(2027年)12月31日までとなっています。
まず、この特例を適用する建物には次の条件が定められています。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物
- 区分所有建物登記がされている建物(マンションや区分登記した2世帯住宅)ではない
- 相続した段階でほかに住んでいる人がいない
次に、この特別控除を受ける要件を紹介します。
- 相続または遺贈で空き家を取得した
- 相続して3年経過した年の12月31日までに売る
- 売却時まで、空き家である(住んだり事業などに利用していない)
- 譲渡時に一定の耐震基準を満たしている
- 空き家を取り壊している場合、建物を建てたり賃貸業などの用途に使っていない
- 売却額が1億円以下である
- ほかの特例控除を受けていない
- 亡くなった方から複数の建物を相続した場合は、空き家特例は1建物のみになる
- 売り主と買い主が親子や夫婦、同族会社などの特別な関係でない
建物の条件と適用される要件が細かく定められているため、注意が必要です。
参考:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
所有期間が10年以上の軽減税率の特例
10年超所有軽減税率の特例は、自分の住んでいた建物を売却する際に、10年超所有していたら長期譲渡所得の税額に軽減税率を適用できる特例です。
譲渡所得が6,000万円以下の部分について、長期譲渡所得の税率20.315%が、14.21%に軽減されます。
6,000万円超の部分については、通常の20.315%になりますが、大幅な節税になります。
「10年超所有軽減税率の特例」を受ける要件は次の通りです。
- 売却年の1月1日から計算して自宅の所有期間が10年以上である
- 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却する
- 建物を解体している場合、譲渡契約の締結日まで賃貸業などの用途に使っていない
- 売り主と買い主が親子や夫婦、同族会社などの特別な関係でない
この特例は、「3,000万円特例控除」と併用が可能なため、両方が利用できれば大幅な節税となるでしょう。
ただし、10年超の計算には注意してください。
この「10年超」は「売却した年の1月1日で10年を超えている」ということです。
例えば、2010年2月取得で2020年9月売却は10年超にはなりません。
この場合、2021年1月1日で10年超となります。
お正月を11回迎えていたら適応されるというイメージが分かりやすいと思います。
特定の居住用財産の買い換えによる特例
特定の居住用財産の買い換えによる特例とは、住宅を売却して新しい住宅を購入する場合に一定の条件を満たせば、売却によって生じた譲渡所得の課税を将来に繰り延べることができる制度です。
つまり、売却した分の税金を今支払う代わりに、新しい住宅を将来売却する際に、今回の売却益と合わせて支払うという仕組みです。
売却時の負担は軽減されますが、将来に繰り越しているため、新しい家を売却する際の税負担が大きくなる可能性が高くなります。
この特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 売却する家の条件
- 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
- 以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売ること
- 売却額が1億円以下であること
- 売却先が親子や夫婦、同族会社などの特別な関係でないこと
2. 買い換える家の条件
- 買い換える建物の床面積が50平方メートル以上であること
- 買い換える土地の面積が500平方メートル以下であること
- 新しい家が日本国内にあること
- 新しい家が建築後使用されたことのない住宅である場合、一定の省エネ基準を満たすこと
3. そのほかの条件
- 売却した年、その前年および前々年にほかの特例(3,000万円の特別控除など)を受けていないこと
- 売却した年の前年から翌年までの3年の間に新しい家を購入し、その家に住むこと
譲渡損失になった場合の特例
譲渡損失の特例とは、不動産を売却した際に損失が生じた場合、その損失をほかの所得と相殺したり、翌年以降の所得から控除(繰越控除)したりすることができる制度です。
これにより、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
この特例のうち、繰越控除を利用するには「マイホームを買い換えた場合」と「住宅ローンの残高が残っているマイホームを売却し、損失が生じた場合」があり、それぞれに条件が違います。
マイホームを買い換えた場合の条件は次の通りです。
なお、2024年現在の法律では、旧自宅を2025年12月31日までに売却することが条件になっています。
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
- 合計所得金額が3000万円以内であること
- 旧自宅を売却した年の前年の1月1日から翌年の12月31日までに新居を取得すること
- 取得した年の翌年12月31日までに入居するか、入居する見込みであること
- 新居の床面積が50m2以上であること
- 返済期間10年以上の住宅ローンを借りること
- 自宅を売却した年の前年と前々年にほかの特例(3000万円特別控除など)を受けていないこと
住宅ローンの残高が残っているマイホームを売却し損失が生じた場合は、マイホームを買い替えなくても以下の場合に繰越控除が受けられます。
- 売却した自宅を売却の前日に返済期間10年以上の住宅ローンの残高がある
- 自宅の売却価格がその住宅ローン残高を下回っている
損益通算しても譲渡損失が残ったときは、翌年以降に繰り越して課税対象額を減らせます。
繰越控除は最大3年間おこなえますが、確定申告をおこなう必要がありますので知っておきましょう。
参考:マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁
参考:住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁
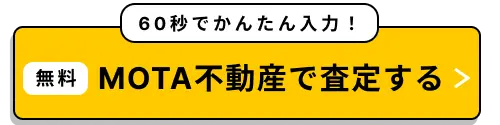
不動産売却における確定申告について
不動産を売却した場合は、原則として確定申告が必要となります。
売却によって得られた利益(譲渡所得)に対して、所得税や住民税が課されるためです。
確定申告が必要なケースは次の通りです。
譲渡所得が発生した場合
不動産を売却して利益が出た場合は、必ず確定申告を行う必要があります。
特別控除を利用する場合
住宅の売却など、特定の条件を満たす場合は、特別控除を受けることができます。
この特例を利用するためにも、確定申告が必要です。
青色申告を行っている場合
事業所得や不動産所得など、ほかの所得と合わせて確定申告を行う必要がある場合もあります。
確定申告の方法について
不動産を売却した際には、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。
- 税務署や国税庁のホームページから、確定申告書を入手します。
- 譲渡所得の計算に必要な書類を揃えます。
- 入手した確定申告書に、必要事項を記入します。
- 申告書と必要な添付書類を税務署に提出します。提出方法は、郵送、税務署への持参、またはe-Taxを利用した電子申告の3つがあります。
確定申告書類作成は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用することで、インターネットを通じて簡単におこなうことができます。
確定申告に必要な書類
確定申告を行う際には、以下の書類が必要となります。
確定申告書B様式(第一表、第二表)
通常の確定申告で記載する書類です。
確定申告書第三表(分離課税用)
不動産譲渡で得た所得の場合、ほかの所得とは別に課税されますので、そのために提出する書類です。
本人確認書類
マイナンバーの記載と本人確認書類の提出が必要です。
マイナンバーカードや免許証、保険証、住民票などが該当します。
登記簿全部事項証明書
自分が所有していた不動産を売却したことを示す為の書類で、法務局で入手できます。
譲渡所得の内訳書
土地・建物を譲渡した場合の確定申告において、申告書のほかに提出が義務づけられている書類です。
購入時・売却時の不動産売買契約書
不動産売買契約書に書かれている物件価格を基に税金が計算されます。
不動産を取得した際の取得費用が確認できる書類
不動産購入金額、仲介手数料、印紙税、登記費用、不動産取得税、測量費用が確認できる書類です。
不動産の譲渡費用が確認できる書類
不動産取得時と同様の書類が必要です。
リフォーム費用や解体費用も経費として申請できるため、関係する書類は全て添付しましょう。
2019年までは、自営業以外の給与所得者は、確定申告時に源泉徴収票の原本が必要でしたが、2020年分以降、源泉徴収票の添付が不要となりました。
ただし、確定申告の書類を記載するために、源泉徴収票に記載されている内容が必要となるため、準備しておきましょう。
まとめ
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税という税金がかかります。
この税金の額は、売却価格から購入費や売却にかかった費用を引いた金額(譲渡所得)と、物件を持っていた期間によって変わってきます。
売却手続きには、ほかにも税金がかかるので、不動産を売る際は、これらの費用も考えておきましょう。
税金を安くする方法として、「3,000万円の特別控除」や「10年以上持っていた場合の税率軽減」といった制度を活用するのがよいでしょう。
不動産の売却は、税金に関する知識が必要で、少し複雑な手続きです。
どの制度が使えるのか、どのくらいの税金がかかるのかなど、あなたの状況に合わせて税理士など専門家に相談することをおすすめします。
関連記事:
不動産売却の基本ガイド|流れ・注意点・成功のコツをわかりやすく解説
