農地を売却する方法は2つ!売却の手続きや流れを紹介
最終更新日: 2025-10-06

- もくじ
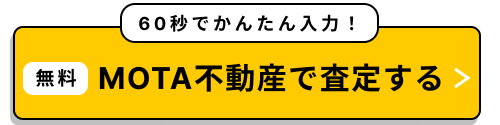
農地売却を考えているなら、まずは基本的な知識と流れを理解することが重要です。
この記事では、売却する際のポイントと気を付けるべき注意点について解説します。
農地の売却が難しいとされる理由
農地売却は、住宅や商業用地のように容易には進まないことが多くあります。なぜなら農地特有の法規制や市場の特性から、売却に多くの課題が生じるためです。
なぜ農地の売却が難しいのか、その背景にはさまざまな要因が存在します。
農地法によって購入者が制限される
農地法は、農地を守り農業生産の維持を目的として制定された法律です。この法律により、農地の購入者が厳しく制限されています。
農地を取得するためには、購入者が農業従事者であること、または農業を営む法人であることが求められます。
そのため、一般企業や投資家が農地を購入することは難しいとされています。
農地法第3条:購入には農業委員会の許可が必要
まず、農地法第3条では、農地を購入する者は農業委員会の許可を得なければなりません。
この許可が下りるためには、購入者が農業に従事する意思と能力があることが求められます。また、購入者が農業に従事するための具体的な計画を提出する必要があり、その計画が実現可能であるかどうかも審査されます。
農地法第4条:農地転用には知事の許可が必要
さらに、農地法第4条では、農地の所有者が農地をほかの用途に転用する場合にも、都道府県知事の許可が必要とされています。
この許可は、転用後の土地利用が農地法の目的に反しないかどうかを判断するためのものであり、許可が下りない場合は土地の転用は不可能です。
農地法の理念と売却の困難さ
このように、農地法は農地の売買において、購入者の選択肢を大幅に制限し、農業を目的としない者が農地を取得することを事実上難しくしています。
また、農地法には「農地を農地のまま守る」という理念があり、こういった背景から農地売却がさらに困難になっています。
たとえば、農地を購入しようとする人が、農地を宅地や商業用地に転用しようとする場合、その転用計画が農地保護の観点から適切でないと判断されれば、許可が下りない可能性が高いのです。
このような厳しい制限が、農地売却の難しさを大きくしている要因のひとつと言えます。
購入後にも続く制約
なお、農地を購入した後も、農地法に基づくさまざまな制約が存在します。たとえば、購入後に農地をほかの用途に転用することを考えている場合、その転用が認められるまでには多くの手続きと時間を要します。
このため、農業を目的としない購入者にとって、農地の購入は非常にリスクが高く、敬遠されがちです。
農地市場の狭さと売却困難の理由
結果として、農地の購入者が農業従事者に限定されることで、農地市場は非常に狭くなり、売却の難易度が高まるのです。
これが農地売却が難しいとされる大きな理由となっています。
農家の高齢化による需要低下
日本では農家の高齢化が進行しており、これが農地の売却において大きな課題となっています。
農業に従事する人口が減少し、特に若年層の農業従事者が少なくなっている現状は、農地の需要に直接的な影響を与えています。
まず、農家の高齢化により、新たに農業を始めようとする人が減少しています。
農業は長時間労働であり、収入が安定しないことも多いため、若い世代が農業に参入することの障壁となっています。
さらに、既存の農家も高齢化に伴い、農業を継続することが難しくなってきています。
多くの農家が後継者を見つけられず、農地を手放さざるを得ない状況にありますが、買い手がいないために売却が進まないケースも増えています。
また、農家の高齢化に伴い、農業技術や経営ノウハウの継承が進まず、これも農地の価値を下げるひとつの要因となっていることが考えられます。
新規参入者が農業を始める場合、これらの技術やノウハウを学ぶことが必要ですが、高齢化した農家からの継承が難しいため、農業を始めるハードルが高くなっており、農地の需要が低下して売却が困難になるのです。
地方の人口減少も大きな懸念点
さらに地方における人口減少も農地の需要低下に拍車をかけています。
特に若い世代が都市部へ流出しているため、農業を担う人材が不足しています。
このような人口動態の変化は、農地の需要に直接的に影響を与え、結果として農地の売却が難しくなっている要因です。
併せて、農地を所有することの経済的メリットが薄れてきていることも、需要低下の一因でしょう。
農業収入が不安定であることから、農地を所有しても十分な収益が得られない場合が多く、これが農地への投資意欲を低下させています。
このように、農家の高齢化は農地の需要に大きな影響を与えており、結果として農地の売却が難しくなっています。
需要が低下することで農地市場が縮小し、売却希望者が多いにもかかわらず買い手が見つからないという状況が続いているのです。
農地の転用基準が厳しい
農地を売却する際に、そのまま農地として売るのではなく、ほかの用途に転用してから売却することを考えるケースが多くあります。
しかし、この転用には非常に厳しい基準が設けられており、簡単には進まないのが現状で、これが農地売却の難しさを増す一因となっています。
まず、農地の転用には都道府県知事や市町村長の許可が必要です。
農地を宅地や商業用地など、ほかの用途に転用する場合、その転用が地域の農業にどのような影響を与えるかを慎重に審査します。
特に優良農地とされる区域内農地や第1種農地などは、転用が極めて難しいとされています。
これらの農地は、農業生産の維持に重要であると見なされているため、ほかの用途に転用することは原則として認められません。
また、農地転用の許可を得るためには、具体的な転用計画を提出する必要があります。
この計画には、転用後の土地利用の詳細や、転用が地域に与える影響についての分析が含まれていますが、計画が地域住民や農業委員会からの反対に遭うこともあり、この場合は許可が下りないこともあります。
転用には時間を要する
さらに、農地の転用には時間がかかる場合が多く、転用手続きが完了するまでに数年を要することも珍しくありません。
これは、許可申請から審査、そして最終的な許可取得までのプロセスが非常に複雑であるためです。
複数の関係機関の承認が必要な場合、各機関との調整や追加の書類提出が求められ、手続きがさらに長引くことになります。
なお、転用後の土地利用に関する規制も厳しく、たとえば住宅地や商業施設として利用する場合でも、一定の環境基準や建築基準を満たす必要があります。
これらの基準をクリアするために追加の費用が発生することが多く、これも農地転用の難しさを増す要因となっています。
このように、農地の転用には多くの障害があり、転用を前提とした売却が難航することが少なくありません。
転用が認められない場合や転用にかかるコストや時間が見合わない場合、農地のままでは需要が少なく売却が難しくなります。
農地は価格が安い
農地の売却が難しい理由のひとつに、農地の価格が安いことも挙げられます。一般的に、農地は住宅地や商業地と比べて価格が大幅に低いため、売却しても大きな利益を得ることが難しくなります。
まず、農地の価格が安い背景には、農地としての利用価値が限定されていることがあります。
農地の供給が過剰
農地は農業生産を行うための土地であり、その価値は農業から得られる収益に依存します。加えて、農地の供給が過剰であることも要因のひとつです。
農家の高齢化や後継者不足により、農地が次々と市場に出回っている一方で、需要は減少しているため、価格が下がります。
この過剰供給は、特に地方の農地で顕著であり、売却が難しくなる要因となっています。
また、農地の価格が低いことから、売主にとっても売却意欲が減退する場合があります。
低価格で売却しても得られる利益が少ないため、農地を売るよりも所有し続けることを選ぶケースが多く見られます。
このような状況では、農地が売りに出されること自体が少なくなり、売却の難易度がさらに高まるのです。
加えて、農地の価格は地域によって大きく異なります。
都市近郊の農地は比較的高値で取引されることがありますが、地方の農地は非常に低価格であることが一般的です。
この地域差も、農地売却の難しさを助長しており、地方の農地を所有している場合には、買い手が見つからず、長期間売却できないことが少なくありません。
このように、農地の価格が安いことは、売却を難しくする大きな要因のひとつです。
価格が低いために売却意欲が減退し、市場に出回る農地が少なくなるとともに、過剰供給の問題も解決されず、農地売却が一層困難になるという悪循環に陥る可能性があります。
農地を売却する方法は2つ
農地の売却を検討する際、どのように進めればよいか悩む方も多いでしょう。農地の売却には大きく分けて2つの方法があります。
ひとつは、農地をそのままの状態で売却する方法、もうひとつは、農地をほかの用途に転用してから売却する方法です。
それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらの方法が適しているかは、個々の状況や目的によって異なります。
農地のまま売却する
農地をそのままの状態で売却する方法は、手続きが比較的簡単であり、農業に従事している買い手を見つけやすいという利点があります。
この方法では、農地の利用目的が農業のままであるため、転用に関する法的な手続きや審査が不要となり、売却プロセスがスムーズに進むことが期待されます。
まず、農地をそのまま売却する際には、買い手が農業に従事する意思を持っていることが重要です。
農地法に基づき、農地を購入する者は農業委員会の許可を得る必要がありますが、この許可は農業を営む目的で農地を取得する場合に限られます。
そのため、購入者が農業従事者や農業法人であることが前提となります。
買い手を見つけるには条件も大切
次に、農地をそのまま売却する場合、買い手が見つかりやすい地域や条件を整えることが求められます。
たとえば、都市近郊の農地や、既に耕作が行われている農地は、需要が高い傾向にあります。
これに対して、地方や山間部など、アクセスが悪い地域の農地は需要が低く、売却が難しくなることが多いです。
また、農地の状態や管理状況も重要で、耕作が容易であるかどうか、また農地の形状や面積が適切かどうかが買い手にとっての判断材料となります。
さらに、農地をそのまま売却する際には、農業委員会への手続きが必要です。
農業委員会は、売却が地域の農業に与える影響を審査し、許可を与えるかどうかを判断します。
この手続きは通常、農地法第3条に基づいて行われ、許可が下りるまでに一定の時間を要しますし、売却契約を結ぶ前に、事前に農業委員会に相談することがよいでしょう。
これにより、手続きがスムーズに進み、予期せぬ問題が発生するリスクを軽減できます。
農地売却のデメリットは?
一方で、農地をそのまま売却する方法にはデメリットもあります。最大のデメリットは、売却価格が低くなる可能性がある点です。
農地は、住宅地や商業地と比べて価格が低く設定されがちであり、特に需要が少ない地域ではその傾向が顕著です。
このため、農地をそのまま売却する場合、思ったほどの利益が得られないことがあります。
また、農地のままでは需要が限られているため、買い手が見つかるまでに時間がかかることも考えられます。
このように、農地をそのまま売却する方法は、手続きの簡便さと買い手の見つかりやすさがメリットですが、売却価格や需要の面で課題があることを理解しておく必要があります。
売却をスムーズに進めるためには、農地の状態や地域の需要を十分に把握し、適切な買い手を見つける努力が求められます。
農地を転用して売却する
農地をほかの用途に転用してから売却する方法は、売却価格を高める可能性がある一方で、手続きや時間がかかる点に注意が必要です。
この方法では、農地を住宅地や商業地など、ほかの用途に変更してから売却することで、より高い価値を生み出すことが期待されます。
まず、農地を転用するには、農地法第4条または第5条に基づく許可が必要です。
この許可は、都道府県知事や市町村長によって審査され、農地転用が地域の農業に与える影響や、転用後の土地利用が適切であるかどうかが判断されます。
特に、優良農地や農業振興地域内の農地を転用する場合、許可が下りにくいことがあります。このため、転用が可能かどうかを事前に確認し、十分な計画を立てることが求められます。
農地を転用する場合は事前にスケジュールを組んでおく
次に、農地を転用する際には、転用後の用途に応じた計画を策定する必要があります。
例えば、住宅地として転用する場合は、土地の造成やインフラ整備が必要となることが多く、これには多額の費用がかかることがあります。
また、商業地として転用する場合は、建物の建設計画や、近隣地域との調整が求められることがあるとともに、これらの計画を具体化し、必要な資金を確保することが、転用を成功させるための鍵となります。
さらに、転用手続きには時間がかかることを理解しておく必要があります。
許可申請から実際の転用が完了するまでには、通常数カ月から1年以上を要することがあり、計画通りに進めるためにはスケジュール管理が重要です。
併せて、転用計画が地域住民や関係者からの反対に遭うことも考えられ、この場合は調整や計画の見直しが必要となることがあります。
転用後の売却価格については、転用の成功によって農地の価値が大幅に向上することが期待されます。とくに都市近郊での住宅地や商業地への転用は、非常に高い売却価格が見込まれるケースが多いです。
しかし、転用にかかるコストやリスクを考慮すると、必ずしも高い利益が得られるとは限らない点に注意が必要です。
また、転用が失敗した場合や、思ったほどの需要がなかった場合、かえって損失を被る可能性もあります。このように、農地を転用して売却する方法は、売却価格を最大化する可能性がある一方で、手続きの複雑さやリスクが伴います。
転用を成功させるためには、十分な準備と計画が必要であり、また転用後の需要を見極めることが重要です。
これらの点を考慮し、慎重に判断することで、農地売却を成功に導くことができるでしょう。
農地売却の具体的な流れ
農地の売却は、住宅や商業用地の売却とは異なり、特有の手続きや確認事項が多くあります。
適切に手続きを進めるためには、まず全体の流れを把握し、各ステップで必要な作業を確実に行うことが重要です。
農地の種類を把握する
農地売却を始める前に、まず自分の所有する農地がどの種類に該当するかを確認することが必要です。
農地の種類によって、売却時の手続きや転用の可否が異なります。
農用地区域内農地
農用地区域内農地は、農業振興地域に指定されている区域内の農地です。
この区域は、主に農業生産を維持・促進するために設定されており、農業以外の用途への転用が厳しく制限されています。
農用地区域内農地を売却する場合は、購入者が農業を営むことが前提となり、転用を検討する場合には、原則として不可能であることを理解しておく必要があります。
甲種農地
甲種農地は、特に優良な農地とされ、農業生産において重要な役割を果たすとされています。
これらの農地も農用地区域内農地と同様に、転用が極めて難しく、原則として農業目的でしか利用できません。
売却する場合には、購入者が農業を継続する意思を持っていることが求められ、甲種農地の売却は、農業委員会や都道府県知事の許可が必要です。
第1種農地
第1種農地は、農業生産に適した農地として評価されていますが、甲種農地ほど厳格な制限はありません。
転用は難しいものの、条件が整えば許可が下りることもあります。
第1種農地を売却する際は、農業を営む人を対象にすることが基本ですが、場合によっては転用も視野に入れることができます。
第2種農地
第2種農地は、農業には適しているものの条件によっては転用が可能な農地です。
周辺の土地利用状況や市街化の進展に応じて、住宅地や商業地に転用できる可能性があります。
売却を検討する際には、転用可能性を確認し、適切な手続きを踏むことが重要です。
第3種農地
第3種農地は、市街地や都市近郊に位置し、比較的転用が容易な農地です。
この種の農地は、住宅地や商業地に転用されることが多く、売却価格もほかの農地に比べて高い傾向にあります。
売却を検討する場合は、転用を前提とした計画を立てることが一般的です。
買い手を探す
農地の種類が把握できたら、次に行うべきは買い手を探すことです。
農地は特殊な不動産であり、一般的な住宅や商業用地に比べて買い手が限定されるため、効果的な方法で買い手を見つける必要があります。
まず、農業従事者や農業法人に対して売却を検討している旨を広く周知することが重要です。
地元の農業関連団体や農業委員会を通じて、農地の売却情報を提供し、関心のある買い手を探すことが有効です。
また、農地売買に特化した不動産業者や、農業法人とのコネクションを持つ仲介業者を利用するのもひとつの方法でしょう。
さらに、インターネットを活用して農地売却の情報を発信することも効果的です。
農業に特化したオンラインプラットフォームや、農地売買に関心のあるコミュニティに情報を掲載することで、広範な地域からの買い手を見つけることができます。
近年では、SNSを活用して直接的に農業従事者にアプローチするケースも増えています。
また、買い手が見つかった際には、その相手が農業委員会の許可を得る能力があるかどうかを確認することが重要です。
農地法に基づく許可が得られない場合、売買契約が成立しない可能性があるため、事前に買い手の資格や意図を確認しておくことがリスク回避に繋がります。
売買契約を結ぶ
買い手が見つかったら、次のステップは売買契約を結ぶことです。
農地売買契約は、通常の不動産取引とは異なり、農地法の規定に従った特別な手続きが必要です。
売買契約を結ぶ際には、以下の点に注意が必要です。まず、契約書の内容を詳細に確認することが重要です。
契約書には売買の条件、価格、引き渡し時期、支払い方法、そして農地法に基づく許可が得られない場合の取り決めなどが記載されます。
特に、許可が得られなかった場合の対応策については、双方が納得できる形で明記しておくことがトラブルを防ぐために重要です。
また、売買契約を結ぶ前に、買い手が農地法に基づく許可を得るための手続きを進めているかどうかを確認します。
農業委員会の許可が下りるまでに時間がかかることがあるため、契約書には許可が得られることを条件とした条項を含めることが一般的です。
これにより、許可が得られなかった場合に契約を解除できるようにすることで、リスクを管理します。
最後に、契約書が完成したら双方の署名捺印を行い、正式に契約が成立します。契約が成立した後は、農業委員会への許可申請手続きに進むことになります。
農業委員会に許可を申請する
売買契約を結んだ後は、農業委員会に対して売却の許可を申請します。この許可申請は、農地法に基づく重要な手続きであり、許可が下りなければ売買は無効となります。
農業委員会への申請には、売買契約書や土地の登記簿、農地の現況報告書など、必要な書類を揃えて提出します。
申請後、農業委員会は申請内容を審査し、売買が地域の農業に与える影響や、買い手が農業を継続できるかどうかを判断します。
審査には通常数週間から数カ月を要することがあり、審査結果が出るまでの間は、契約の履行が保留されます。
許可が下りた場合、次のステップに進むことができます。
都道府県知事から許可をもらう
農業委員会の許可が下りた後は、都道府県知事からの許可を取得する必要があります。これは農地を転用する場合に特に必要な手続きです。
都道府県知事は、農地の転用が地域の土地利用計画に適合しているかどうか、また転用後の土地利用が適切かどうかを審査します。
許可申請には、農地転用計画書や地域住民への影響に関する報告書などが必要です。審査には時間がかかる場合があり、許可が得られるまでに追加の書類や説明が求められることもあります。
都道府県知事の許可が得られた後、最終的な売却手続きに進みます。
決済・引渡し
すべての許可が得られたら、売買の最終段階である決済と引渡しに進みます。決済では、買い手から売買代金を受け取り、同時に土地の所有権が買い手に移転します。
所有権移転登記を行い、これをもって正式に売却が完了します。
引渡しの際には、農地の現況や引渡し条件に従って、買い手に土地を引き渡します。引渡し後も、必要に応じて登記の確認や書類の保管を行い、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。
農地売却にかかる税金や諸費用について
農地を売却する際、得られる収入だけでなく、それに伴う税金や諸費用をしっかりと把握しておくことが重要です。
これらの費用は、売却後に予想外の負担となることがあるため、事前に十分な準備が必要です。
税金
農地を売却する際には、さまざまな税金が発生します。
所得税・住民税
まず、所得税と住民税です。農地を売却して得た利益は、譲渡所得として課税されます。
譲渡所得は、売却価格から取得費用や売却にかかった費用を差し引いた金額に基づいて計算され、その金額に応じて所得税と住民税が課されます。
譲渡所得税の税率は、売却した年の所得状況や売却した土地の所有期間によって異なります。
一般的には、所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得として税率が低くなる一方、5年以内の短期所有であれば、税率が高くなります。
固定資産税
次に固定資産税です。
農地を所有している間は、毎年固定資産税が課されますが、売却の際には、その年度の税金を清算する必要があります。
売却日を基準に、売主と買主で税額を按分する形が一般的です。
また、農地の転用に伴って固定資産税の評価額が変わることがあるため、転用後の税負担についても注意が必要です。さらに、登録免許税も考慮しなければなりません。
農地を売却し、所有権を移転する際には、所有権移転登記を行う必要があり、その際に登録免許税が発生します。登録免許税は、土地の評価額に基づいて計算され、通常は評価額の0.4%が課税されます。
ただし、農地の評価額が高額な場合、この税金もかなりの金額になるため、事前に確認しておくことが重要です。
最後に、消費税が適用されることもあります。
農地そのものには通常消費税はかかりませんが、建物や設備などが付帯する場合や事業用地として売却する場合には、消費税が課されることがあります。
この点についても、売却前に税理士や専門家に相談して確認しておくことが賢明です。
諸費用
農地売却に際しては、税金以外にもさまざまな諸費用が発生します。これらの費用を正確に見積もり、売却計画に組み込むことで思わぬ出費を防ぐことができます。
まず、不動産仲介手数料です。農地の売却を不動産業者に依頼する場合、仲介手数料が発生します。
この手数料は、売却価格に応じて算出され、通常は売却価格の3%に6万円を加えた金額が上限となります。
不動産業者を利用することで、買い手の選定や交渉がスムーズに進むメリットがありますが、その分コストがかかることを理解しておきましょう。
次に、登記費用があります。売却に伴う所有権移転登記や、抵当権の抹消登記などを行う際に、司法書士に依頼するケースが一般的です。
登記に関わる費用は、司法書士の報酬や実際の登記手数料が含まれます。
これらの費用は、農地の評価額や登記手続きの内容によって異なりますが、通常は数万円から十数万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
また、測量費用も考慮する必要があります。
とくに農地の境界が不明確な場合や、隣接地との境界線を明確にする必要がある場合には、土地の測量が必要です。
測量費用は、土地の広さや形状、地形によって異なりますが、数十万円から場合によっては百万円以上かかることもあります。
測量が必要な場合は、早めに専門業者に依頼して見積もりを取得し、計画に反映させましょう。さらに、引越し費用や土地の整備費用も考慮する必要があります。
農地に建物や設備がある場合、それらを撤去して更地にするための費用や、不要な農作物や廃棄物を処分するための費用が発生することがあります。
また、売却後に新しい場所へ移転する場合には、引越し費用も必要です。これらの費用は、土地の状況や移転先の距離などによって異なります。
最後に専門家への相談料も発生します。税理士や弁護士、司法書士などに相談する際には、相談料や顧問料がかかることがあります。
これらの費用も見積もっておくと手続きがよりスムーズになるでしょう。
まとめ
農地の売却は、住宅や商業地の売却と比べて複雑な手続きや特有の制約が多く、慎重な計画と準備が求められます。
農地法に基づく許可申請や税金・諸費用の理解が必要であり、適切に進めることでスムーズな売却が可能になります。
農地の種類や売却方法、発生するコストをしっかりと把握し、専門家の助言を活用しながら進めることで、満足のいく結果を得ることができるでしょう。
