土地の相続税はいくら?計算方法から節税の特例まで分かりやすく解説
最終更新日: 2025-08-04
.png)
- もくじ
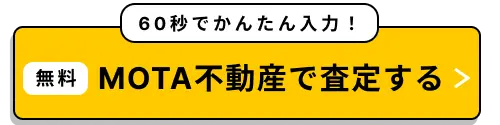
「土地を相続したけど、相続税はどれぐらいかかる?」と心配に感じる方は多いでしょう。相続税の計算方法や、控除・特例の適用条件は複雑で、初めて土地を相続する人は不安が大きいはずです。
しかし、相続税の仕組みを正しく理解し、使える制度をしっかり活用すれば、負担を大きく減らすことも可能です。
本記事では、土地の相続税の計算方法から、控除・特例の利用方法まで、分かりやすく解説します。
相続税の仕組みを理解し、余計な税負担を避ける具体的な方法を知ることで、相続手続きをスムーズに進めましょう。
土地の相続で相続税がかからないケース

まず知っておきたいのは、土地を相続したからといって、必ず相続税がかかるわけではないということです。
相続税には「基礎控除」という大きな非課税枠があり、遺産の総額がこの範囲内であれば、相続税は一切かからず、申告も不要です。
基礎控除額は、以下の式で計算されます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数) |
|---|
例えば、法定相続人が配偶者1人と子供2人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + (600万円 × 3人)) となります。
つまり、土地や預貯金などを含めた遺産の総額が4,800万円以下であれば、相続税は0円です。
また、基礎控除以外にも「配偶者控除」「贈与税率控除」などの控除や特例があり、それを使用することで相続税が発生しなくなるケースもあります。具体的な控除に関しては『土地を相続した際に使える控除や特例について』をご覧ください。
そもそも相続税とは?土地の相続における基礎知識
相続税がかかる可能性があると分かったところで、そもそも「相続税」がどのような税金なのか、基本を押さえておきましょう。
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、配偶者や子などの相続人が引き継いだ際に、その財産の価値に対して課される税金です。
- 誰が払う?
財産を相続した「相続人」が納税義務者となります。 - 何にかかる?
土地・建物といった不動産、預貯金、株式などのプラスの財産から、借入金などのマイナスの財産を差し引いた、正味の遺産総額に対してかかります。 - なぜかかる?
偶然性の高い「相続」という機会を通じて富が過度に集中するのを防ぎ、社会全体で再分配するという目的があります。
この後の章で解説する計算や特例を理解する上で、この「遺産全体に対してかかる税金である」という基本を押さえておくとスムーズです。
相続税の申告と納税の期間

相続税がかかる可能性がある場合、次に押さえるべきは「期限」です。手続きには厳格な期限が定められており、これを過ぎるとペナルティが発生する可能性があります。
申告・相続の期限
相続税の申告と納税は、原則として「相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税が発生するため、注意が必要です。
特に、相続人同士で遺産分割協議が長引いてしまった場合でも、申告期限の延長は原則認められません。
そのため、遺産分割協議がまとまらない場合でも、分割前に申告をおこない、のちに修正申告をおこなうなどの対応が必要です。
申告先
相続税の申告は、相続財産の詳細を記載した「相続税申告書」を作成し、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。
納税方法
納税は、金融機関や税務署の窓口で、現金一括払いが原則です。もし一括での納付が難しい場合は、「延納」や「物納」といった分割払いや不動産そのもので納める制度もありますが、利用には厳しい条件があるため、早めに税務署や税理士に相談しましょう。
土地の相続税評価額の計算方法
相続税を計算する上で最も重要なのが、財産の大部分を占めることが多い「土地の価値(評価額)」を算出することです。この評価額を間違えると、税額も大きく変わってしまうため、慎重に確認する必要があります。
土地の評価額は、主に以下の2つの方法で計算されます。
路線価方式(市街地などで採用)
道路に面する土地1㎡あたりの価格である「路線価」を基に計算する方法です。路線価は国税庁のホームページで確認でき、一般的に公示価格の8割程度の水準に設定されています。
土地の評価額=路線価×土地の面積(㎡) |
|---|
例えば、路線価が20万円/㎡の道路に面した100㎡の土地の場合、評価額は20万円 × 100㎡ = 2,000万円となります。
路線価の確認はこちら:財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
倍率方式(路線価が定められていない地域で採用)
土地の固定資産税評価額に、地域ごとに定められた「評価倍率」を掛けて計算します。固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。
土地の評価額=固定資産税評価額×評価倍率 |
|---|
例えば、固定資産税評価額が1,000万円で、倍率が1.1倍の地域なら、評価額は1,000万円 × 1.1 = 1,100万円となります。
相続税の計算方法

土地の評価額がわかったら、いよいよ相続税の総額を計算します。
相続税の計算方法は複雑ですが、基本的な流れは課税遺産総額を計算し、それをもとに相続税額を計算することで相続税が把握できます。
計算は以下のステップで進めます。
STEP1. 課税遺産相続を求める
まず、土地、預貯金などの遺産総額から基礎控除額を差し引き、税金の対象となる金額を算出します。
課税遺産総額=遺産の総額−基礎控除額 |
|---|
課税遺産総額とは、遺産の総額から基礎控除額を引いた残りの金額のことです。
遺産には、現金や預貯金、不動産、株式などが含まれ、これらの合計額を計算します。
例えば、総遺産額が1億円で相続人が配偶者1人と子供2人の計3人の場合、計算方法は下記になります。
基礎控除額:3000万円+600万円 × 3人=4800万円
課税遺産総額:8000万円ー4800万円=3,200万円
この3,200万円が相続税の対象となります。
生前贈与加算「7年ルール」のポイント
2024年からの税制改正で、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されましたが、その適用には以下の重要な経過措置があります。
- 対象は2024年1月1日以降の贈与から
新しい7年ルールは、2024年1月1日以降に行われた贈与にのみ適用されます 。2023年12月31日以前の贈与は、従来通り3年ルールが適用されます 。 - 加算期間は段階的に延長
加算期間はすぐに7年になるわけではなく、2027年以降に発生する相続から徐々に長くなります 。完全に7年間の加算期間が適用されるのは、2031年1月1日以降に開始する相続からです 。 - 延長された4年分には100万円の控除あり
延長された4年間(相続開始前3年超~7年以内)に行われた贈与については、その期間の贈与額の合計から100万円を控除した金額が、相続財産への加算対象となります 。
STEP2. 相続税額の総額を計算
次に、課税遺産総額を法定相続分で仮に分割し、各相続人の税額を計算した上で、それらを合計して「相続税の総額」を算出します。
相続税は累進課税方式であり、課税遺産額に応じて税率が上昇します。
具体的な税率は以下の表のとおりです。
課税遺産額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
法定相続人ごとに計算して合計したものが相続税の合計になります。
先ほどの計算例に当てはめて考えてみましょう。
【計算例】
- 遺産総額:8,000万円
- 相続人:配偶者、子2人(合計3人)
- 基礎控除額:4,800万円
- 課税遺産総額:8,000万円 - 4,800万円 = 3,200万円
この3,200万円を法定相続分(配偶者1/2、子それぞれ1/4)で分けると、
- 配偶者:1,600万円
- 子1人目:800万円
- 子2人目:800万円
それぞれの金額に税率を掛けて税額を計算します。
- 配偶者:1,600万円 × 15% - 50万円 = 190万円
- 子1人目:800万円 × 10% = 80万円
- 子2人目:800万円 × 10% = 80万円
これらを合計した190万円 + 80万円 + 80万円 = 350万円が、この相続における相続税の総額となります。
STEP3. 各人が実際に納める税額を計算する
最後に、算出した「相続税の総額」を、実際に財産を相続した割合に応じて配分します。ここから、さらに後述する各種税額控除を適用して、最終的な納税額が確定します。
土地を相続した際に使える控除や特例について
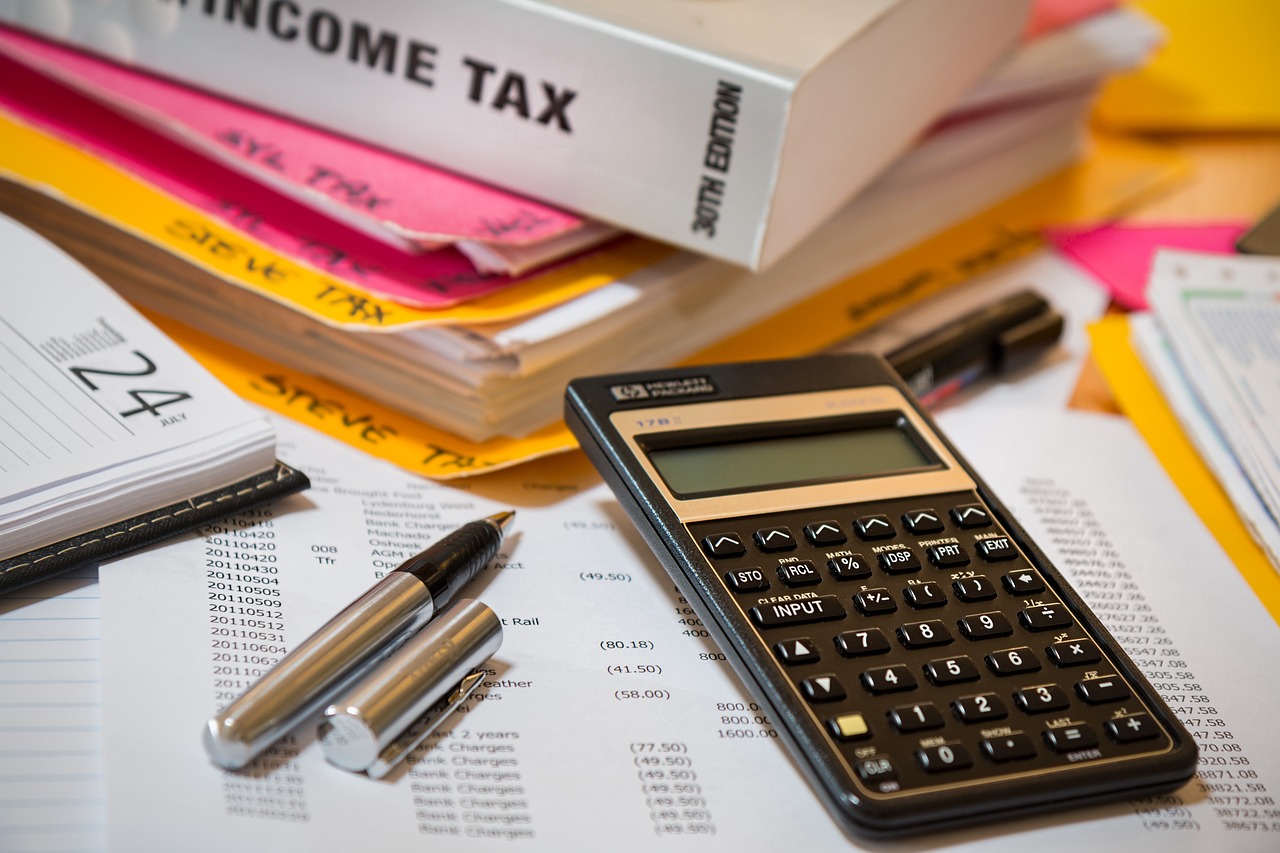
相続税は高額になることが多いため、税負担を軽減するための控除や特例制度をしっかり活用することが重要です。
以下に土地を相続した際に利用できる代表的な控除と特例を紹介します。
配偶者の税額控除
配偶者が相続した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからないという非常に強力な制度です。例えば、遺産総額が3億円で、配偶者がその半分である1億5,000万円を相続する場合、相続税はかかりません。
もし1億8,000万円を相続した場合は、1億6,000万円を超える2,000万円に対してのみ税金がかかります。
この特例を使えば、多くのケースで配偶者の納税額はゼロになります。
適用を受けるためには、相続税の申告が必要であり、申告を怠ると軽減措置が無効となるため、注意が必要です。
贈与税額控除
相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されますが、その贈与の際にすでに贈与税を支払っていた場合、その税額分を相続税から差し引くことができます。なぜこんな控除があるのかというと、一定の条件を満たす生前贈与は相続時に相続財産として足し戻す制度があるからです。つまり、二重課税を防ぐための制度です。
贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2種類の方法があります。
「暦年贈与」の場合は、相続発生から7年間さかのぼり、相続財産として足し戻す必要があります。
「相続時精算課税」は、基礎控除分の贈与税が非課税となる代わりに、相続時に贈与分を相続財産としてすべて足し戻す必要があります。
このため、すでに贈与税を支払っている財産も課税対象となってしまうため、二重課税を避けるために「贈与税額控除」として控除する仕組みがあります。
相次相続控除
相次相続控除とは、最初の相続(一次相続)から10年以内に次の相続(二次相続)が発生した場合、二次相続の税額から、一次相続で支払った相続税の一部が控除されます。短期間に相続が重なった負担を軽減する制度です。
一例ですが、祖父から遺産を相続した父が祖父の死後10年以内に亡くなった場合、祖父から相続時の相続税の一定部分が控除されます。
この控除は10年間の期間設定があり、100%から1年につき10%減少していきます。
2年経っていると80%(10年ー2年)、7年で30%(10年-7年)、10年で0%(10年ー10年)となって控除がなくなります。
参考:相次相続控除|国税庁
未成年者控除
相続人が未成年者の場合、「未成年者控除」を受けることができます。
相続人が18歳未満である場合に、年齢に応じた金額を相続税から差し引く制度です。
具体的には、未成年者1人につき「18歳までの年数×10万円」が控除額となります。
例えば、15歳の相続人であれば、18歳までの3年間に対して「3年×10万円=30万円」が控除されます。
また、相続税額より未成年者控除額が大きい場合、差し引けない分を扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
障害者控除
相続人が障害者の場合、その相続税を軽減する障害者控除が受けられます。
この控除は、障害を持つ相続人が生活を安定させるために、相続税の負担を減らすための制度です。
具体的には、85歳までの年数に応じて控除額が決まり、「85歳までの年数×10万円」が相続税額から差し引かれます。
例えば、50歳の障害者が相続人の場合、「85歳までの35年間×10万円=350万円」が控除額となります。
もし特別障害者である場合は、控除額がさらに大きくなり、「85歳までの年数×20万円」となります。
また、相続税額より障害者控除額が大きい場合、差し引けない分を扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
参考:障害者控除|国税庁
まとめ
土地の相続にともなう相続税は、しっかりと理解していないと、想像以上の税負担が発生することがあります。
しかし、基礎控除や各種控除、特例を活用することで、相続税の負担を大きく減らすことができます。
また、相続税の計算方法や土地の評価額の算出方法は複雑であるため、専門的な知識が必要となる場合が多いです。
相続手続きをスムーズに進め、無駄な税金を支払わないためにも、早めの準備と適切な申告が重要です。
税理士や弁護士などの専門家に相談し、計画的に相続を進めることをおすすめします。
関連記事:
相続した不動産、どうする?売却のメリットから税金までわかりやすく解説
土地にかかる固定資産税はいくら?種類や計算方法、節税対策を紹介
