土地にかかる固定資産税はいくら?種類や計算方法、節税対策を紹介
最終更新日: 2025-07-31
.png)
- もくじ
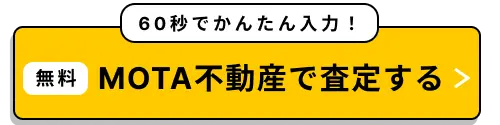
土地を所有する際に知っておくべき税金には、固定資産税と都市計画税があります。
これらは土地や建物などの不動産に対して課される税金で、毎年支払う必要があります。
固定資産税は土地の評価額や税率によって税額が毎年変動する可能性があるため、仕組みや計算方法を理解しておくことが重要です。
本記事では、固定資産税の基本的な仕組みから、計算方法、そして節税方法について紹介していきます。
土地にかかる税金は2種類
土地にかかる税金は大きく分けて「固定資産税」と「都市計画税」の2種類です。
どちらも毎年土地を所有している限り課せられますが少し性質が違うものとなります。
それぞれの税金について基本的な情報を確認していきましょう。
固定資産税
固定資産税は、土地や建物などの不動産に対して課される税金です。
毎年1月1日時点での所有者に対して課税され、市区町村が徴収します。
固定資産税の税率は基本的には1.4%ですが、自治体ごとに増減がある場合もあります。
固定資産税は、土地の用途や所有状態によっては特例措置が適用され、税額が減る場合もあります。
固定資産税の計算には、固定資産税評価額が用いられます。
この固定資産税評価額は3年ごとに見直されるため、評価替えの年には固定資産税が変動することがある点に注意が必要です。
固定資産税についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
固定資産税はいくら?戸建て・マンションの計算シミュレーションと賢い軽減方法
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業がおこなわれている都市計画区域内の土地や建物に対して課される税金です。
都市計画税の税率は自治体によって異なりますが、最大で0.3%と定められています。
土地の評価額に対して都市計画税が加算されるため、都市計画区域内の土地を所有している場合、この税金も固定資産税と合わせて考慮しておく必要があります。
2023(令和5)年4月1日現在、都市計画税を課税している市町村(東京特別区は1団体として)は639市町村です。
日本全国の市町村総数は1,719のため、約1/3の市町村が課税をしていることになります。
土地にかかる固定資産税の計算方法

土地にかかる固定資産税は土地の固定資産税評価額を基に計算されますが、その課税標準額は地域や土地の用途・特性によって異なります。
具体的な固定資産税評価額や、課税評価額の計算方法について確認していきましょう。
①固定資産税評価額を調べる
固定資産税の計算の第一歩は固定資産税評価額を調べることです。
この評価額は、土地や建物の市場価値を基に算出され、固定資産税の基準となる金額です。
評価額は市町村が定めるもので、3年ごとに見直されます。
時価の70%程度が目安
固定資産税評価額は、土地の市場価値に基づいて決定されますが、その評価額は通常「公示価格」の約70%程度が目安となります。
公示価格は、国土交通省が毎年発表する基準価格であり、土地の市場価格の指標として使われています。
この公示価格に基づき、自治体が土地の評価額を算出し、最終的な固定資産税評価額が決定されるのです。
たとえば、ある土地の公示価格が1,000万円の場合、その土地の固定資産税評価額はおおよそ700万円程度というように、固定資産税の大まかな額を予測できます。
固定資産税路線価から算出も可能
固定資産税の評価額を調べる際、もう一つの方法として「路線価」があります。
路線価は、国税庁が発表している土地の評価基準で、道路ごとに定められた1平米あたりの金額です。
この路線価を基に、土地の面積を掛け合わせることで評価額を大まかに計算することが可能です。
たとえば、路線価が1平方メートルあたり10万円の場合、100平方メートルの土地の評価額は1,000万円となります。
ただし、固定資産税評価額は路線価と一致するわけではなく、あくまで参考値と考えておきましょう。
②土地の所有状態に応じて課税標準額を調べる
次に、土地の種類に応じて課税標準額を調べます。
普通は「固定資産税評価額から税金が計算される」と考えますが、実は土地の所有状態によっては特例や控除が適用されて税金が安くなります。
固定資産税評価額に実際の所有状態を考慮した評価額を課税標準額と言います。
土地のみを所有している場合(更地など)
土地に建物が建っていない「更地」の場合、固定資産税は評価額に対してそのまま課税されることが多くなります。
住宅用地として利用されていないため、特例措置や軽減制度が適用されにくいのが特徴です。
特に都市部の土地や広大な土地を所有している場合、税額がかなり高額になることもあります。
その代わり、何も立っていない土地は「非住宅用地」となり、負担調整措置という制度が適用されます。
負担調整措置は原則70%で、課税標準額は固定資産税評価額 × 0.7となります。
また、「市街化区域で農地として使用している土地」の場合、特例が設けられており、課税標準額が固定資産税評価額 × 1/3になる場合があります。
建物がある土地を所有している場合
一方で、土地の上に住宅などの建物が建っている場合、固定資産税には軽減措置が適用される可能性があります。
住宅用地として利用されている土地には「住宅用地の特例」が適用され、課税標準額が大幅に引き下げられることが多いです。
③課税標準額と税率を計算する
課税標準額が計算できたら、最後に実際の税額を計算します。
固定資産税の計算式は、課税標準額に税率を掛けたものです。
固定資産税=課税標準額×標準税率(1.4%)
標準的な固定資産税の税率は1.4%ですが、地域によっては1.5〜1.7%の市町村もあるため、確認してから計算するのが重要です。
また、固定資産税の課税対象は課税標準額が30万円以上のもので、課税標準額が30万円未満の場合は、土地を持っていても固定資産税がかかりません。
土地にかかる固定資産税の計算シミュレーション
それでは、実際に土地(更地)にかかる固定資産税を実際に計算してみましょう。
固定資産税の計算方法
土地の保有にかかる固定資産税の計算式は以下のとおりです。
都市計画税=課税標準額×標準税率(0.3%) |
|---|
今回計算に使用した条件は次の通りです。
<計算の条件>
- 土地の固定資産税評価額:8,000万円
- 土地の面積:900m2
- 固定資産税率:1.4%
更地の場合には、固定資産税評価額に負担調整率をかけたものが課税評価額となるため、次の計算になります。
<固定資産税の計算>
固定資産税=8,000万円 × 1.4% = 112万円
今回の条件では固定資産税は112万円となりました。
都市計画税の計算方法
土地の保有にかかる都市計画税の計算式は以下のとおりです。
都市計画税=課税標準額×標準税率(0.3%) |
|---|
先述の計算条件に当てはめてシミュレーションをしてみましょう。
<計算の条件>
・土地の固定資産税評価額:8,000万円
・土地の面積:900m2
・都市計画税:0.3%
※住宅用地である前提(特例適用対象)
<都市計画税の計算>
都市計画税=8,000万円 × 0.3% = 24万円
今回の条件では都市計画税は24万円となりました。
土地にかかる固定資産税を減税する方法は?

固定資産税は毎年の負担がありますが、一定の条件を満たせば減税のための特例措置を受けることができます。
特に、住宅用地に対しては大幅な軽減措置が適用されることが多く、税額を抑えられます。
ここでは、代表的な減税方法を2つ紹介します。
住宅用地の特例
住宅用地に対しては、固定資産税の課税標準額が大幅に軽減される「住宅用地の特例」が適用されます。
この特例は、土地が住宅の敷地として使用されている場合に適用され、土地の面積や規模に応じて評価額が減額されます。
住宅用地の区分 | 特例率 (固定資産税) | 特例率 (都市計画税) |
|---|---|---|
小規模住宅用地 (200平方メートル以下の部分) | 1/6 | 1/3 |
一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) | 1/3 | 2/3 |
アパートやマンションの場合には、「戸数 × 200平方メートル」まで小規模住宅用地となり、課税標準額が1/6になります。
住宅用地の特例を受けるためには、土地が実際に住宅として使用されていることが条件となります。
空き家や一部商業用途で使われている場合には適用されないことがあるため、注意が必要です。
新築住宅による減税特例
一定の条件を満たした新築住宅を建てた場合に、建物にかかる固定資産税が軽減される特例が存在し、一定期間固定資産税が半額になります。
- 居住部分の床面積が2分の1以上の住宅(マンションの場合、居住部分が専有部分の2分の1以上)
- 床面積が50m2以上280m2以下であること
建物の種類によって軽減期間は異なり、以下のとおりになります。
ただし、1戸あたり床面積120m2相当分までが上限で、それ以上は通常の税率となります。
建物の種類 | 減額割合 | 軽減措置期間 | |
新築住宅 | 3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅 | 1/2 | 5年 |
それ以外住宅 | 1/2 | 3年 | |
認定長期優良住宅 | 3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅 | 1/2 | 7年 |
それ以外住宅 | 1/2 | 5年 | |
住宅を建てると固定資産税はどれくらい減額される?
それでは、アパート・戸建を建てた場合の固定資産税を計算し、更地の場合の112万円とどれぐらい違いがあるのかをシミュレーションしてみましょう。アパートと戸建ての条件は以下の通りとします。
- 土地の固定資産税評価額:8000万円
- 土地の面積:900m2
- 固定資産税:1.4%
- 戸建ての固定資産税評価額:4000万円
- 戸建ての床面積:190m2
- 3階建てマンションの固定資産税評価額:9000万円
- アパートの戸数:12戸
- アパート1戸の床面積:70m2
アパートの場合
アパートを新築した場合、戸数 × 200m2まで小規模住宅用地となります。
12戸 × 200 = 2400m2で900m2全てが小規模住宅用地となります。
また、1戸の床面積が70m2のため、新築住宅による減税特例が適用でき固定資産税が1/2になります。
土地の固定資産税:8000万円 × 1/6 × 1.4% = 約18.7万円
アパートの固定資産税:9000万円 × 1/2 × 1.4% = 63万円
今回の条件のアパートを建てると、18.7万円 + 63万円 = 約81.7万円で、更地の場合と比べ約30.3万円減額となりました。
戸建ての場合
戸建てを新築した場合の固定資産税は、200m2までが小規模住宅用地、残りの700m2が一般住宅用地として計算されます。
また、新築住宅のため、戸建てにかかる固定資産税は1/2になります。
土地の固定資産税:(8000万円 × 200m2 / 900m2) × 1/6 × 1.4% + (8000万円 × 700m2 / 900m2) × 1/3 × 1.4% = 約33.2万円
戸建ての固定資産税:4000万円 × 1/2 × 1.4% = 28万円
今回の条件で戸建てを建てると、33.2万円 + 28万円 = 約61.2万円で、更地の場合と比べ約50.8万円減額となりました。
固定資産税を上げてしまう2つのケース
固定資産税は、所有している土地の利用状況や状態によって増減します。
土地に建物がある場合は住宅用地の特例などにより税額が軽減されますが、逆に条件が変わると固定資産税が上がる場合があります。
ここでは、税額が上昇する可能性のある2つの代表的なケースについて紹介します。
住宅を取り壊した場合
住宅を取り壊して更地にしてしまうと、「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税は大幅に増加する可能性があります。
住宅用地の特例は、土地の評価額を6分の1や3分の1で計算する大きな減税措置ですが、住宅を取り壊してしまうとその特例が消滅します。
結果、固定資産税評価額そのままで課税され、土地の固定資産税が3〜6倍になります。
しかし、実際には建物の固定資産税が無くなるため、一般的には3〜4倍程度に増加するとされています。
また、自治体によっては「負担軽減措置」が適用され、固定資産税が翌年から急激に増加しない場合もあります。
関連記事:家の解体費用いくら?1坪当たりの目安や費用を抑える方法を紹介
空き家を放置した場合
空き家を長期間放置することで、固定資産税が増加するかもしれません。
老朽化が進んでいる空き家は「特定空家等」として認定されるリスクがあります。
この認定を受けると住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が一気に上がることになります。
さらに、特定空家等に指定された場合、自治体から修繕や解体の指示が出されることもあります。
指示に従わない場合、行政代執行が行われ、その費用が請求されることもあるため、空き家を放置し続けることは多額の負担を招く可能性があります。
まとめ
土地の固定資産税や都市計画税は、土地の評価額や所有状況に応じて税額が増減します。
特に、住宅用地の特例や新築住宅に対する減税措置を活用することで、固定資産税を大幅に抑えることが可能です。
一方、住宅を取り壊したり、空き家を放置すると特例がなくなり、税負担が大幅に増えるリスクがあります。
計算方法として、土地の評価額に税率を掛けるシミュレーションを行い、将来の負担を把握することが重要です。
税制を確認しながら賢く土地を運用していきましょう。
