不動産売却の必要書類完全ガイド!初心者でも分かる取得方法・期間・費用ガイド
最終更新日: 2025-10-22
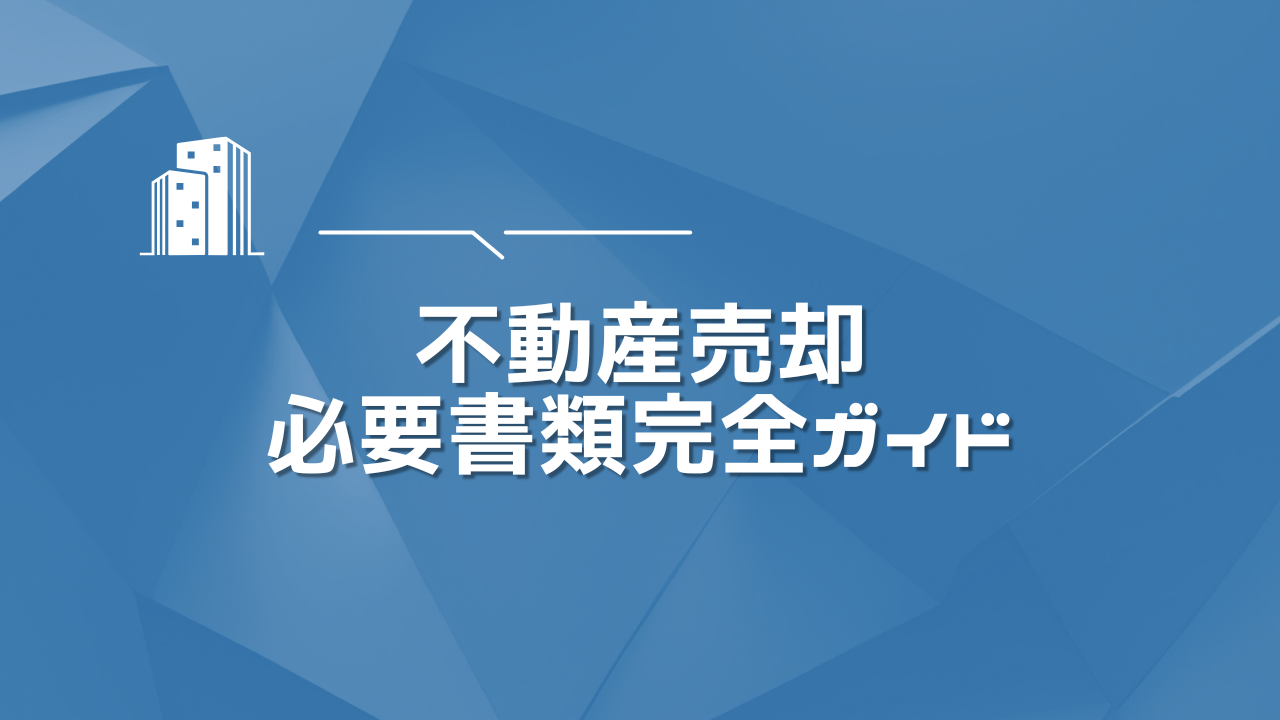
- もくじ
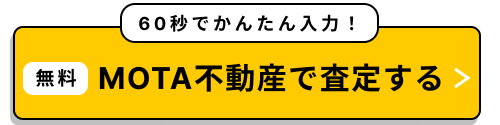
不動産売却を検討中の方にとって、「どんな書類が必要なの?」「いつまでに準備すればいい?」という疑問は最初にぶつかる大きな壁です。
書類の準備不足で契約が遅れたり、取引が破談になったりするリスクを避けるためにも、事前の準備が重要です。この記事では、2025年最新の情報をもとに、不動産売却で必要な書類を状況別に整理し、取得方法から注意点まで詳しく解説します。
あなたの状況に合わせた準備スケジュールで、スムーズな売却を実現しましょう。
不動産売却で必要な書類一覧
不動産売却で必要となる書類は以下のとおりです。
書類名 | 主な目的・役割 | 入手方法 | 取得にかかる期間・費用 |
|---|---|---|---|
登記済権利証(登記識別情報) | 所有者・売却意思の証明 | 購入時に法務局から交付済(手元保管) | 紛失時は司法書士依頼で1〜2週間(費用5〜10万円) |
固定資産税納税通知書・評価証明書 | 評価額と年間税額の確認 | 市区町村役所で即日発行 | 即日〜1日(評価証明書は3ヶ月以内のものが有効) |
建築確認済証・検査済証 | 建物が法的基準を満たす証明 | 新築時に交付済/役所で再発行可 | 紛失時の再発行に3〜5日(手数料300円程度) |
土地測量図・境界確認書 | 土地の面積・境界の明確化 | 法務局または測量会社 | 法務局で即日/新規測量は1〜2週間 |
マンション管理規約・長期修繕計画書 | 管理状況・修繕予定の開示 | 管理組合・管理会社から取得 | 3〜7日(管理会社の対応速度による) |
本人確認書類(免許証・パスポート等) | 契約者本人の確認 | 各自保有 | 即日確認可能(更新手続きが必要な場合は1週間程度) |
実印・印鑑証明書 | 契約意思の確認 | 住民登録地の役所で発行(300円程度) | 即日〜1日(発行から3ヶ月以内が有効) |
住民票 | 現住所の証明 | 役所またはコンビニ交付 | 即日(マイナンバーカードで即時発行可能) |
抵当権抹消関係書類 | ローン完済に伴う担保解除 | 金融機関から交付 | 完済手続き後1〜2週間 |
銀行口座情報 | 売却代金の振込先指定 | 各自保有 | 即日(事前に口座確認) |
各種鍵・設備保証書・取扱説明書 | 引渡し・買主の利便性確保 | 手元保管 | 即日(紛失時の複製に数日) |
売買契約書(売却・購入時) | 譲渡所得の計算根拠 | 売却時・購入時の契約書 | 紛失時は仲介会社確認に1〜3日 |
譲渡費用の領収書 | 経費(仲介手数料・印紙税など)の証明 | 各支払時に発行 | 各支払時に随時発生(保管推奨) |
不動産売却の流れと必要書類を揃えるタイミング
不動産売却は査定から確定申告まで約1年間にわたる長期プロセスです。このプロセスは4つの主要段階に分かれ、各段階で異なる書類が必要となります。
全体像を把握することで、書類準備の遅延による契約破談や手続きの滞りを防ぎ、スムーズな売却完了を実現できます。
各段階の所要期間と必要書類の種類を事前に理解し、計画的な準備を進めることが成功の鍵となります。
1.査定・媒介契約段階
この段階では物件価値の正確な把握と信頼できる不動産会社選びが中心となります。
必要書類は物件の基本情報を証明するものが中心で、登記済権利証、固定資産税納税通知書、建築確認済証などが該当します。マンションの場合は管理規約や長期修繕計画書、一戸建ては土地測量図や境界確認書の準備が重要です。
これらの書類により、不動産会社は適正な査定価格を算出し、効果的な販売戦略を立案できます。
2.売買契約段階
買主が決定し、法的拘束力のある売買契約を締結する重要な局面です。
この段階では本人確認と意思確認のための公的書類が必要となり、運転免許証などの本人確認書類、実印、印鑑証明書、住民票が中心となります。
共有名義の場合は全ての共有者の書類が必要で、相続物件では遺産分割協議書や相続関係説明図の準備が求められます。書類不備は契約締結の遅延や破談につながる可能性があるため、事前の入念な準備が不可欠です。
3.決済・引渡し段階
所有権移転と代金決済を行う売却プロセスの最終段階です。住宅ローンが残っている場合は抵当権抹消関係書類の準備が必要で、金融機関からの交付に1〜2週間要するため決済日から逆算した準備が重要です。
また、物件の完全な引渡しのため、各種鍵、設備保証書、取扱説明書などの整理も求められます。銀行口座情報の確認や司法書士との連携により、スムーズな所有権移転と代金決済を実現できます。
4.売却後の確定申告
売却完了後の税務処理を適切に行うための段階です。譲渡所得の計算根拠として、売却時と購入時の売買契約書が必要となります。
購入時の契約書を紛失した場合は、仲介会社への保管状況確認が重要です。また、仲介手数料、印紙税、測量費、解体費などの譲渡費用を証明する領収書の整理も必要です。
これらの書類により、適正な税額計算と特別控除の適用を受けることができ、税務上の不利益を回避できます。
不動産売却に必要な書類と入手方法
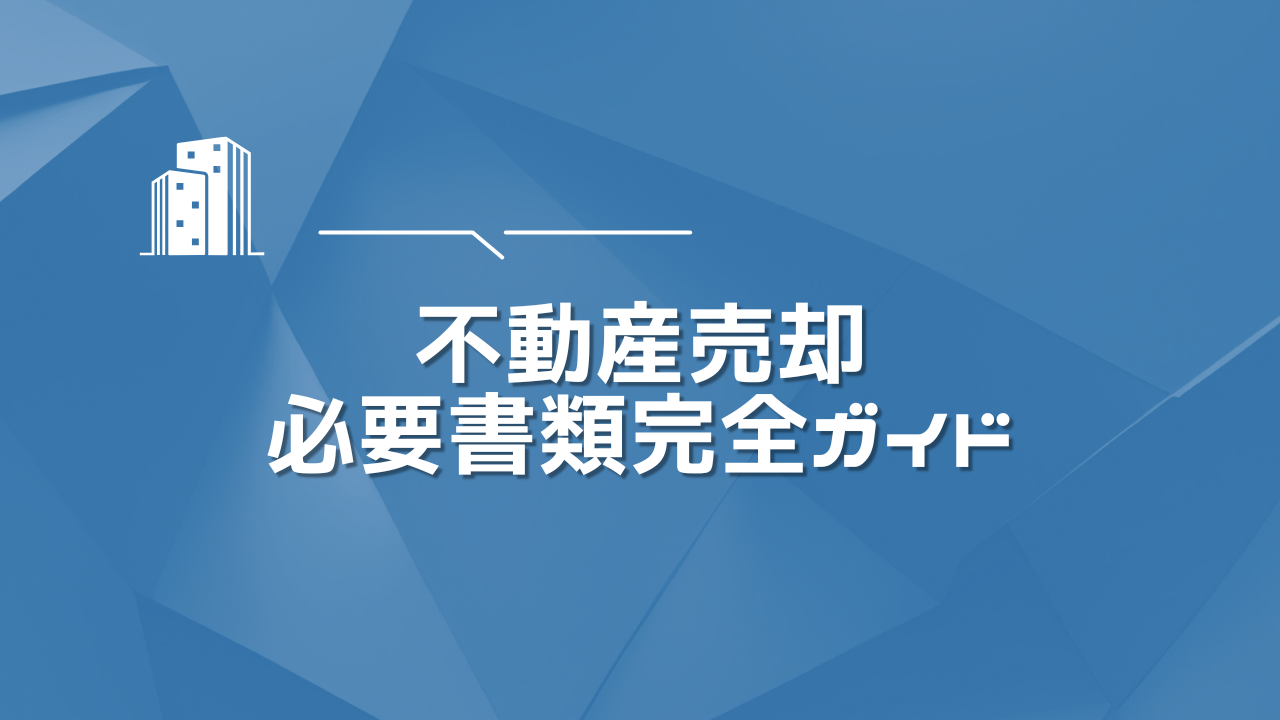
不動産売却は4つの段階に分かれ、各タイミングで必要な書類が異なります。書類の準備不足は契約の遅延や破談につながるため、段階ごとの要件を正確に把握し、計画的に準備することが重要です。
ステップ1:査定・媒介契約時の必要書類
登記済権利証(登記識別情報)
役割: 所有者であることの証明と売却意思の確認
入手方法: 購入時に法務局から交付済み(手元保管)
注意点: 紛失時は司法書士による本人確認情報で代替可能(費用5〜10万円)
登記済権利証は物件の所有者であることを証明する最も重要な書類です。2025年現在、多くの物件で登記識別情報通知書として発行されています。
この書類により、売主が真の所有者であることを不動産会社や買主に証明できます。紛失した場合でも売却は可能ですが、司法書士による本人確認情報の作成が必要となり、追加費用が発生します。
固定資産税納税通知書・評価証明書
役割: 物件の評価額と年間税額の確認
入手方法: 毎年4〜6月に市区町村から郵送 / 役所窓口で即日発行
注意点: 評価証明書は3ヶ月以内のものが必要
固定資産税納税通知書は物件の公的評価額と年間税額を確認するために使用されます。査定時の参考資料として重要な役割を果たします。
評価証明書が必要な場合は、市区町村の役所で即日発行可能ですが、有効期限が3ヶ月以内と定められているため、取得タイミングに注意が必要です。
建築確認済証・検査済証(一戸建て・新築マンション)
役割: 建物が法的基準を満たしていることの証明
入手方法: 新築時に交付済み(手元保管)
紛失時対応: 役所で「台帳記載事項証明書」を取得(手数料300円程度)
建築確認済証と検査済証は、建物が建築基準法に適合していることを証明する重要な書類です。
特に一戸建てや新築マンションの売却時には必須となります。紛失した場合は、建築確認を行った役所で台帳記載事項証明書を取得することで代替できます。手数料は300円程度と比較的安価で入手可能です。
土地測量図・境界確認書(一戸建て・土地)
役割: 土地の正確な面積と境界の明確化
入手方法: 法務局で取得 / 測量会社による新規作成
注意点: 古い測量図の場合、買主から再測量を求められる可能性あり
土地の境界を明確にするため、測量図と境界確認書が必要です。
法務局に保管されている既存の測量図を取得できますが、古い測量図の場合は精度が不十分な可能性があります。買主から再測量を求められることもあるため、事前に測量図の年代と精度を確認しておくことが重要です。
マンション管理規約・長期修繕計画書(マンション)
役割: 管理状況と将来の修繕計画の開示
入手方法: 管理組合または管理会社から取得
注意点: 最新版の入手に時間がかかる場合があるため早めの準備を
マンション売却時には、管理規約と長期修繕計画書の提示が必要です。これらの書類により、買主はマンションの管理状況や将来の修繕予定を把握できます。管理組合や管理会社からの取得に時間がかかる場合があるため、売却を検討し始めた段階で早めに準備することをお勧めします。
ステップ2:売買契約時の必要書類
本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
役割: 契約者本人であることの確認
注意点: 有効期限内のもの。住所変更がある場合は事前に更新
売買契約時には、契約者本人であることを証明する公的な身分証明書が必要です。
運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの書類が一般的です。有効期限が切れていないことを確認し、住所変更がある場合は契約前に更新手続きを完了させておく必要があります。
実印・印鑑証明書
役割: 重要な契約における意思確認
入手方法: 住民登録地の役所で発行(手数料300円程度)
注意点: 発行から3ヶ月以内。共有名義の場合は全員分必要
不動産売買契約では実印の押印が必要となります。印鑑証明書は住民登録地の役所で発行でき、手数料は300円程度です。
印鑑証明書自体には法律上、有効期限はありませんが不動産の登記申請では、発行から3カ月以内のものを添付することが義務付けられているので注意が必要です。(不動産登記令第16条)
発行から3ヶ月以内のものが有効とされています。共有名義の物件の場合は、所有者全員の実印と印鑑証明書が必要となるため、事前に全員の協力を得ておくことが重要です。
住民票
役割: 現住所の確認(登記住所と異なる場合)
入手方法: 住民登録地の役所またはコンビニ交付
注意点: 本籍地記載の有無を事前確認
登記上の住所と現住所が異なる場合、住民票の提示が求められます。
住民登録地の役所窓口での取得のほか、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付も可能です。契約書類によっては本籍地の記載が必要な場合があるため、取得前に不動産会社に記載内容を確認しておくことをお勧めします。
ステップ3:決済・引渡し時の必要書類
抵当権抹消関係書類
役割: 住宅ローン完済による担保権の解除
入手方法: 金融機関から交付(完済手続き後)
注意点: 手続きに1〜2週間要するため、決済日から逆算して準備
住宅ローンが残っている物件の売却では、抵当権の抹消手続きが必要です。
金融機関での完済手続き後に抹消関係書類が交付されますが、手続きには1〜2週間程度の時間を要します。決済日に間に合うよう、逆算して早めに金融機関との調整を開始することが重要です。
銀行口座情報
役割: 売却代金の振込先指定
注意点: 金融機関の営業時間内での決済が必要
売却代金の受け取りには、振込先となる銀行口座の情報が必要です。口座番号や支店名などの正確な情報を準備しておきます。
決済は通常、金融機関の営業時間内に行われるため、決済日の調整時には営業時間を考慮する必要があります。
各種鍵・設備保証書・取扱説明書
役割: 物件の完全な引渡しと買主の利便性確保
注意点: 紛失した鍵は事前に複製を作成
物件の引渡し時には、玄関や各部屋の鍵一式を買主に渡します。設備の保証書や取扱説明書も併せて引き渡すことで、買主の利便性を高めることができます。鍵を紛失している場合は、引渡し前に複製を作成しておく必要があります。
ステップ4:確定申告時の必要書類
売買契約書(売却時・購入時)
役割: 譲渡所得の計算根拠
注意点: 購入時の契約書紛失時は、仲介会社に保管状況を確認
不動産売却による譲渡所得の計算には、売却時と購入時の両方の売買契約書が必要です。これらの書類により、取得費と譲渡価額を正確に算出できます。購入時の契約書を紛失している場合は、当時の仲介会社に保管状況を確認し、コピーの取得を依頼することが可能です。
譲渡費用の領収書
役割: 仲介手数料等の必要経費証明
対象: 仲介手数料、印紙税、測量費、解体費など
譲渡所得の計算では、売却に要した費用を必要経費として控除できます。
仲介手数料、印紙税、測量費、解体費などの領収書を保管しておくことで、税額を適切に計算できます。2025年の確定申告時に必要となるため、売却に関連するすべての費用の領収書を大切に保管しておくことが重要です。
相続や共同名義など状況に応じて必要となる書類
不動産売却では、物件の取得経緯や所有者の状況によって、通常の書類に加えて特別な書類が必要となるケースがあります。
これらの特殊ケースでは、書類の準備により多くの時間と手続きが必要となるため、売却を検討する段階で早めの確認と準備が重要です。
相続物件の売却
相続によって取得した不動産を売却する場合、相続手続きが適切に完了していることを証明する書類が必要となります。
相続人が複数いる場合は、全員の合意と協力が不可欠で、書類の準備に数ヶ月を要することも珍しくありません。
遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
相続人全員が遺産の分割方法について合意したことを証明する重要書類です。不動産を売却する相続人を明確にし、他の相続人が売却に同意していることを示します。相続人全員の実印による押印が必要で、一人でも欠けると売却手続きを進めることができません。
相続関係説明図
被相続人と相続人の関係を図式化した書類で、相続の権利関係を明確に示します。複雑な相続関係の場合、この書類により第三者にも相続の経緯が理解しやすくなり、売買契約時の説明資料としても活用されます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の生涯にわたる戸籍を連続して取得し、相続人の確定に漏れがないことを証明します。転籍や婚姻により複数の市区町村にまたがる場合があり、すべての戸籍を収集するには相当な時間と労力が必要となります。
相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
各相続人が現在も存命で、遺産分割協議に参加する権利を有することを証明します。印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要で、売却手続きの進行に合わせて適切なタイミングでの取得が求められます。
共有名義物件の売却
複数の所有者で共有している不動産の売却では、所有者全員の同意が法的に必要となります。一人でも反対する共有者がいる場合、売却は不可能となるため、事前の合意形成が最も重要なポイントとなります。
共有者全員の同意書
共有者全員が売却に同意していることを明文化した書類です。売却価格、売却時期、代金の分配方法などについて、共有者間で事前に合意した内容を記載し、後々のトラブルを防止する役割も果たします。
共有者全員の印鑑証明書・住民票
各共有者の本人確認と現住所の証明のために必要です。印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要で、共有者の人数が多い場合は、全員分を同時期に取得するための調整が必要となります。
共有者が遠方の場合の委任状
共有者の中に遠方に居住している方がいる場合、売買契約や決済に立ち会えないケースがあります。この場合、委任状により代理人を立てることで手続きを進めることが可能ですが、委任の範囲や代理人の選定について慎重な検討が必要です。
海外居住者の売却
日本国外に居住している方が日本の不動産を売却する場合、日本の住民登録がないため、通常の公的書類に代わる特別な証明書類が必要となります。これらの書類は現地の日本領事館で取得する必要があり、手続きに時間がかかることが特徴です。
在留証明書(領事館発行)
海外居住者の現住所を証明する書類で、住民票の代替として使用されます。現地の日本領事館で発行され、申請から取得まで数週間を要する場合があるため、売却スケジュールを考慮した早めの申請が必要です。
サイン証明書(印鑑証明書の代替)
海外居住者は日本の印鑑登録ができないため、サイン証明書が印鑑証明書の代替として使用されます。領事館で本人のサインを証明してもらう書類で、重要な契約書類への署名時に必要となります。
住民票除票
日本から海外に転出した際の記録を示す書類です。いつから海外居住となったかを証明し、税務上の居住者区分の判定にも使用されます。転出から長期間が経過している場合、保存期間の関係で取得できない場合もあります。
成年後見人による売却
認知症などにより判断能力が不十分となった方が所有する不動産を売却する場合、成年後見制度を利用した売却手続きが必要となります。家庭裁判所の関与が必要で、通常の売却よりも厳格な手続きと時間を要します。
家庭裁判所の許可書
成年後見人が被後見人の不動産を売却するには、事前に家庭裁判所の許可を得る必要があります。売却の必要性や妥当性について裁判所の審査を受け、許可が下りるまでに数ヶ月を要することが一般的です。
後見登記事項証明書
成年後見人として正式に選任されていることを証明する書類です。法務局で発行され、後見人の権限の範囲や期間などが記載されています。売買契約時に買主や金融機関に提示し、売却権限があることを証明します。
後見人の印鑑証明書
成年後見人自身の印鑑証明書が必要となります。後見人が法人の場合は法人の印鑑証明書、個人の場合は個人の印鑑証明書を準備し、発行から3ヶ月以内のものが求められます。
必要書類の準備スケジュール
不動産売却を成功させるためには、計画的な書類準備が不可欠です。
売却完了から逆算して、各段階で必要な準備を整理したタイムラインをご紹介します。このスケジュールに沿って進めることで、手続きの遅延や契約破談といったリスクを回避できます。
売却開始3ヶ月前
手元にある書類の確認・整理
まず、購入時に受け取った重要書類の所在確認から始めましょう。
登記済権利証(登記識別情報)、固定資産税納税通知書、建築確認済証・検査済証、土地測量図・境界確認書など、売却に必要な基本書類が手元にあるかチェックします。この段階で書類の整理を行い、紛失や破損がないか確認することが重要です。
売却開始1ヶ月前
査定に必要な書類を完備
不動産会社による査定を受けるために必要な書類を完備します。
登記済権利証、固定資産税納税通知書・評価証明書、建築確認済証・検査済証、マンションの場合は管理規約・長期修繕計画書などを準備します。評価証明書は3ヶ月以内のものが必要なため、この時期に役所で取得しておきましょう。
不動産会社との媒介契約準備
信頼できる不動産会社を選定し、媒介契約の準備を進めます。
複数社からの査定結果を比較検討し、売却戦略について相談できる体制を整えます。この段階で、売却スケジュールや希望条件を明確にし、必要書類についても不動産会社と最終確認を行います。
売買契約前
公的書類(印鑑証明書等)の取得
買主が決まり売買契約を結ぶ段階では、本人確認書類、実印・印鑑証明書、住民票などの公的書類が必要となります。
印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要なため、契約日程が確定してから取得しましょう。住民登録地の役所またはマイナンバーカードを活用したコンビニ交付で手数料300円程度で取得できます。
共有者がいる場合の事前調整
物件が共有名義の場合は、共有者全員の同意書、印鑑証明書・住民票が必要となります。
共有者が遠方にいる場合は委任状の準備も必要です。この段階で共有者との調整を完了し、必要書類を揃えておくことで、契約手続きをスムーズに進められます。
決済1週間前
抵当権抹消書類の確認
住宅ローンが残っている場合は、決済と同時に抵当権抹消手続きを行います。
金融機関から交付される抵当権抹消関係書類の準備状況を確認し、決済日に間に合うよう最終調整を行います。この手続きには1〜2週間要するため、決済日から逆算して金融機関との調整を完了させておきます。
引渡し関係書類の最終チェック
物件の完全な引渡しに必要な各種鍵、設備保証書、取扱説明書などを最終確認します。
紛失した鍵がある場合は複製を作成し、買主の利便性を確保します。また、売却代金の振込先となる銀行口座情報も準備し、金融機関の営業時間内での決済に備えます。
不動産売却の必要書類準備でよくあるトラブルと対処法
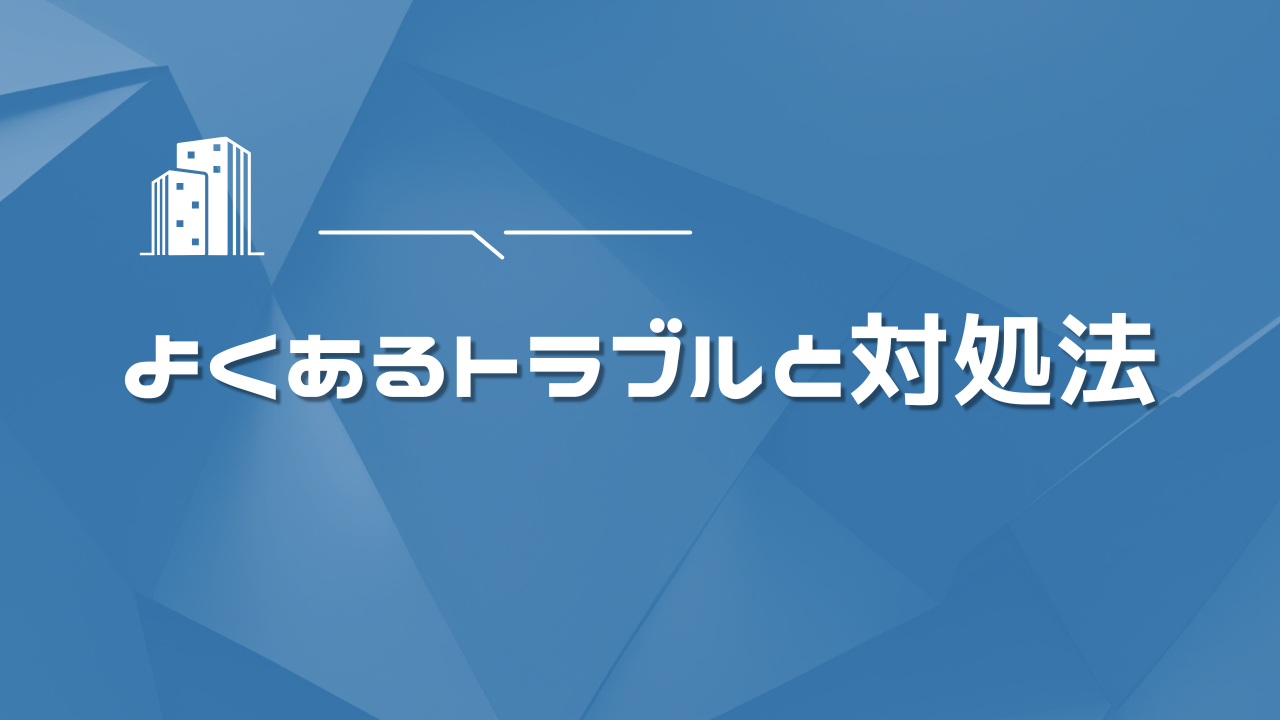
不動産売却の書類準備では、多くの売主様が同じような不安や疑問を抱えられます。
ここでは、実際によくあるトラブルとその解決策をご紹介します。これらの対処法を知っておくことで、慌てることなく適切に対応できるでしょう。
Q. 権利証を紛失しました。売却は不可能ですか?
登記済権利証や登記識別情報を紛失しても売却は可能です。司法書士による「本人確認情報」の作成で代替できます。
この手続きは司法書士が売主様の本人確認を行い、その結果を法務局に提出することで、権利証と同等の効力を持たせることができます。費用は5〜10万円程度かかりますが、売却手続きに支障はありません。
Q. 書類の名義が旧姓のままです
結婚や離婚により氏名が変更された場合、住所・氏名変更登記が必要となります。
戸籍謄本等で氏名変更の経緯を証明し、司法書士に依頼すれば手続きが可能です。この登記により、現在の氏名と登記上の氏名を一致させることができ、スムーズな売却手続きが行えるようになります。
変更登記には一定の期間が必要ですので、売却を検討される際は早めに確認し、必要に応じて手続きを開始することをお勧めします。
Q. 共有者の一人が認知症になりました
共有者の方が認知症により判断能力を失われた場合、成年後見制度の利用が必要です。
家庭裁判所への申立てを行い、成年後見人の選任を受ける必要があります。後見人が選任されれば、家庭裁判所の許可を得て売却手続きを進めることができます。
ただし、申立てから許可まで数ヶ月かかるのが一般的ですので、このような状況が予想される場合は、早めの対応が重要となります。専門家に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。
まとめ
不動産売却における書類準備は、単なる事務手続きではありません。
売却開始3ヶ月前からの計画的な準備により、手続き遅延や契約破談といったリスクを回避し、スムーズな取引を実現する重要な基盤となります。
登記済権利証や固定資産税納税通知書などの基本書類の確認から始まり、各段階で必要な公的書類を適切なタイミングで取得することが成功への第一歩です。
特に共有名義物件や相続物件の場合は、全共有者の同意書や相続関係書類など追加書類が必要となるため、早めの準備開始が不可欠です。複雑なケースや専門的な判断が必要な場面では、経験豊富な不動産会社や司法書士への相談を躊躇せず行ってください。
適切な書類準備と信頼できるパートナーとの連携により、安心・確実な不動産売却を実現し、新たなステージへの確実な一歩を踏み出すことができるでしょう。
