土地売却の税金はいくら?いつ払う?計算方法や節税方法を紹介
最終更新日: 2025-07-31
.png)
- もくじ
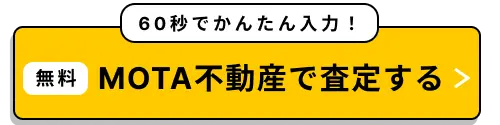
土地を売却する際には、複数の税金が発生しますが、その内容をしっかりと理解していないと、思わぬ税負担に悩まされてしまいます。
特に初めて土地を売却する場合や、税金についてあまり詳しくない場合には、税金や節税方法を把握しておくことが重要です。
今回は、土地を売却する際に余計な出費を抑えたい方に、土地売却に関連する税金の種類から、具体的な譲渡所得の計算方法、さらには節税対策まで解説します。
土地売却で発生する税金は4種類
土地を売却すると、その過程で多くの税金が発生しますが、主な税金は4種類です。
税金の種類 | 支払いのタイミング |
|---|---|
印紙税 | 売買契約書の作成時(契約締結時) |
登録免許税 | 不動産の登記申請時 |
所得税 | 不動産を売却し、利益が出た翌年度の6月以降 |
住民税 |
印紙税
印紙税は、土地売却の際にはじめに支払うことになる税金です。支払うタイミングは売買契約時です。
印紙税とは、特定の文書を作成したときに課税される税金で、不動産を売却する際に作成する『不動産売却契約書』に収入印紙(印紙税)の貼り付けが必要となります。
契約(売却)金額によって、次の通り印紙税が定められています。
なお、平成26年(2014年)年4月1日〜令和9年(2027年)3月31日までの期間は、税率が軽減されています。
不動産売却価格 | 税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
1万円以下 | 非課税 | 非課税 |
1万円超~10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超~1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円超~5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5千万円超~1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超~5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超~10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超~50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
登録免許税
登録免許税とは、不動産の売買などにより所有権を移転する際、「所有権移転登記」を法務局で行う必要があり、その登記手続きに対して国に支払う税金のことを指します。
不動産を売却した場合、登録免許税は「不動産の価額」の2%です。
ただし、土地の売買における名義変更の税金は、令和8年(2028年)3月31日までに登記を行う場合、1.5%に軽減されます。
この「不動産の価額」は、不動産の売却額ではなく、「市町村役場で管理されている固定資産課税台帳に登録された価格」である点に注意が必要です。
固定資産課税台帳に登録された価格がない場合、登記官が認定した価額が適用されます。
登録免許税は通常、不動産の所有権移転登記を行う買主が負担します。
また、住宅ローンを利用して不動産を購入する場合には、金融機関のために抵当権を設定する必要があり、その際にも別途「抵当権設定登記」の登録免許税が発生します。この費用は通常、買主が負担します。
不動産売却時に住宅ローンを完済し、抵当権の登記を抹消する際に支払うことになります。
所得税
所得税とは、個人が1年間に得た所得(利益)に対して課される税金のことです。
土地や建物などの不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合も、その利益に対して所得税が課されます。この所得税は、不動産を売却した年の翌年2月〜3月に確定申告を行い、6月頃に納付するのが一般的です。
課税対象となる譲渡所得は、「売却価格 − 購入価格 − 譲渡にかかった諸費用」で算出されます。
ここで重要なのは、土地の所有期間によって所得税の税率が異なる点です。
- 5年未満(短期譲渡所得):税率30%
- 5年以上(長期譲渡所得):税率15%
※実際には、住民税(5%)や復興特別所得税(所得税の2.1%)も加算されます。
所有期間の基準は、譲渡した年の1月1日時点で5年間を超えているかどうかで判断されます。
例えば、取得日が2020年3月で売却日が2025年4月の場合、所有期間は5年を超えていますが25年の1月時点では5年未満となるため、この場合は短期譲渡となります。
住民税
住民税も、不動産を売却した年の翌年に確定申告を行ったうえで、6月頃から各自治体より課税通知が届き、納付する流れとなります。
住民税の税率も、土地の所有期間によって異なります。
- 5年未満(短期譲渡所得):税率9%
- 5年以上(長期譲渡所得):税率5%
※このほか、所得税と同様に「復興特別所得税(所得税の2.1%分)」も加算されます。
なお、所有期間の判定基準は住民税も所得税と同じく「譲渡した年の1月1日時点」で判断されます。
土地売却における譲渡所得の計算方法

土地を売却する際、発生する税金は譲渡所得をもとに計算されます。
譲渡金額の計算方法は次の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 |
|---|
- 売却価格:不動産を売却した金額
- 取得費:不動産を購入した際に支払った金額、仲介手数料、登記費用などの合計
- 譲渡費用:不動産を売却する際に支払った仲介手数料、広告費、司法書士費用などの合計
購入額が不明な場合や、土地の所有期間によって計算方法や支払う税金が変わってきます。
購入額が不明な場合
土地の購入額が不明な場合、「売却額の5%相当を取得費とすることができる」と定められています。
この計算方法だと、売却金額の95%相当が利益となるため、多額の税金を支払うことになってしまいます。
このため、実際には「合理的に説明できる購入額(査定額)」をもとに購入額の計算が認められることもあります。その算出方法は次の3つがあります。
- 公示地価、基準地価
- 市街地価格指数
- 不動産鑑定評価
公示地価は国土交通省が毎年公表する土地の価格で、基準地価は都道府県が公表する7月1日時点の地価で、平方メートル当たりの価格が示されます。
実際の土地価格との乖離が起きにくいため、購入年近くの公示地価・基準地価を参考に、近隣相場を推定することができます。
市街地価格指数とは、「一般財団法人 日本不動産研究所」が毎年2回、全国主要都市の中から宅地価格を調査して指数化したものです。
不動産鑑定評価は、不動産鑑定士が客観的に鑑定する方法です。
客観的な根拠となるため、税務調査で否認される可能性が低い傾向があります。
しかし、土地の取引事例を調べられないほど取得日が古い場合は、鑑定できないといったケースがあります。
ただし注意点として、これらを根拠に決定した購入額は、税務調査で否認されてしまうケースがあります。
とくに市街地価格指数による推計取得費のみで申告すると、合理性がないと判断され税務署に否認されることがあるようです。
税務署または税理士と相談のうえで、妥当な購入額の算定をおこなうのが良いでしょう。
土地の所有期間が5年超か以下で税率が変わる
土地の所有期間によって、譲渡所得にかかる所得税と住民税の税率が変わってきます。
その基準は1月1日時点で5年を超えているかどうかで、5年以下が「短期譲渡」、5年超が「長期譲渡」に分けられています。
それぞれの場合の譲渡所得にかかる税金は次の通りです。
住民税 | 所得税 | 復興特別所得税 | 合計税率 | |
短期譲渡所得 | 9% | 30% | 0.63% | 39.63% |
長期譲渡所得 | 5% | 15% | 0.315% | 20.315% |
土地売却にかかる税金シミュレーション
実際の土地売却における税金の負担を具体的にするため、売却価格をもとにした税金シミュレーションをおこないました。
シミュレーションを通じて、短期譲渡と長期譲渡の税負担の違いを理解し、売却のタイミングを検討する参考にしてください。
今回はわかりやすく、譲渡所得が1000万円になるような例を紹介します。
売却価格が2,000万円の土地にかかる税金
売却価格が2,000万円で短期譲渡に該当する場合の税金を計算してみましょう。
取得費が900万円、売却にかかった費用が100万円と仮定します。
- 譲渡所得=2000万円-900万円-100万円=1000万円
- 所得税(復興税含む)=1000万円 × 30.63%=約306万円
- 住民税=1000万円 × 9%=90万円
税金は約306万円+90万円=約396万円になります。
売却価格が3,000万円の土地にかかる税金
売却価格が3,000万円で長期譲渡に該当する場合の税金を計算してみましょう。
取得費が1900万円、売却にかかった費用が100万円と仮定します。
- 譲渡所得=3000万円-1900万円-100万円=1000万円
- 所得税(復興税含む)=1000万円 × 15.315%=約153万円
- 住民税=1000万円 × 5%=50万円
税金は約153万円+50万円=約203万円になります。
所有期間が5年以下と5年超で約190万円の差が出ます。
土地売却における節税方法について

土地売却による税負担を軽減するためには、いくつかの節税方法があります。
ここでは、代表的な方法を3つ解説します。
3,000万円の特別控除の特例を適用する
土地を売却した場合に、一定の要件を満たせば、3,000万円の特別控除を受けることができます。
この控除を受けることで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
3000万円の控除は正確には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といい、マイホームを売却した際に受けられる控除です。
マイホームを解体している場合も土地売却が解体後1年以内の場合には、この控除が受けられます。
土地を5年以上所有してから売る
税金シミュレーションでの計算の通り、譲渡期間が5年以下と5年超では支払う税金が大きく変わります。
土地を所有していることで固有資産税が発生しますが、5年近く土地を所有している場合には、5年を超えてから売却することで大幅な節税ができます。
相続税を支払った人は3年以内に土地を売却する
相続した土地を売却する場合、「取得費加算の特例」を利用できます。
譲渡所得の取得費に加算できる特例で、相続後の土地売却をおこなう場合に重要な節税手段となります。
その適用には次の条件があります。
- 相続や遺贈により財産を取得した土地であること
- 相続税を支払った本人であること
- 相続開始日から3年10か月以内にその土地を売却すること
※相続税の申告期限が10か月、申告期限の翌日から3年以内が要件のため
取得費に加算できる金額は、相続した土地に対して支払った相続税額のうち、譲渡資産である土地に対応する部分です。
例えば、相続税として1,000万円を支払った場合、そのうち500万円が土地に関する金額であれば、その500万円を取得費に加算できます。
まとめ
土地売却は、高額な取引となるため税金対策は非常に重要です。
土地の売却は、所得税、住民税、印紙税、登録免許税など、さまざまな税金がかかります。
特に譲渡所得にかかる所得税は、土地の所有期間や売却価格によって大きく変わります。
節税対策としては、3,000万円の特別控除、5年以上の長期保有、相続税を支払った場合の取得費加算の特例など、さまざまな方法があります。
しかし、これらの方法は、個々の状況によって適用できるかどうかが異なります。
土地の売却を検討される際には、不動産業者や税理士などの専門家に相談して上手に節税しましょう。
また、不動産売却にかかる税金について詳しく知りたい方は下記記事もご覧ください。
