5000万の新築・中古マンションの固定資産税はいくら?目安や計算例を紹介
最終更新日: 2025-10-06
.png)
- もくじ
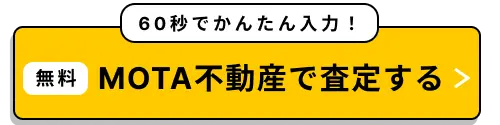
マンションの固定資産税は、購入後の負担として見逃せない費用です。「どれくらいかかるのか?」と考える方も多いでしょう。
本記事では、マンションの固定資産税の目安や、新築・中古でのシミュレーション、さらに節税方法についてわかりやすく解説します。
マンション購入を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
マンションの固定資産税の目安は年間10〜30万円ほど

マンションの固定資産税は、自治体が決定する「固定資産評価額」をもとに計算されます。
この評価額はマンションの購入価格とは異なり、築年数や物件の状態、周辺の土地価格などを総合的に考慮して決定されます。
マンションの固定資産税は、一般的に年間10万円から30万円程度とされています。
しかし、これはあくまでも平均的な金額であり、固定資産評価額や自治体の税率など、さまざまな要素によって大きく変わってきます。
例えば、高額なマンションを購入した場合や、都心部など地価が高い地域に住んでいる場合は評価額が高いため、固定資産税も年間30万円を超えることがあります。
一方、地方の中古マンションでは、評価額が下がるため、年間の税額が10万円以下になることもあるでしょう。
新築マンション・中古マンションの固定資産税をシミュレーション
マンションの固定資産税は新築か中古かによっても大きく変わります。
新築マンションの場合、初年度の評価額が高く設定されるため、固定資産税も高額になりますが、築年数が経つごとに評価額が下がり、それに伴って税額も減少します。
中古マンションの場合は、すでに評価額が減少しているため、新築に比べて税額が低く抑えられることが多いです。
固定資産税は、「固定資産評価額×1.4%〜1.7%※」ですが、さまざまな条件によって軽減措置等があります(市町村によって異なる)。
今回は5000万円のマンションを例に、どの程度の固定資産税がかかるのかシミュレーションを紹介します。
東京のマンションをモデルケースとして、条件は次の通りとします。
- 評価額は土地が1500万円で建物が3500万円
- 一戸当たりの専有面積が120m2以下で、長期優良住宅ではない
- 土地の評価額は変わらない
- 鉄筋コンクリート製
(※建物は120m2以上の場合や長期優良住宅は計算が異なります)
5,000万円の新築マンションの場合
新築マンションの場合、次の軽減措置が適用されます。
- 新築より5年間は建物の固定資産税が1/2になる
- 小規模住宅用地(120m2以下)のため、土地の固定資産税が1/6になる
この軽減措置を含めた土地と建物の固定資産税は以下のとおりです。
土地 1500万円 × 1.4% × 1/6 = 35000円
建物 3500万円 × 1.4% × 1/2 = 245000円
35000円 + 245000円 = 280000円
5000万円の新築マンションの場合、1年間の固定資産税は28万円となります。
5,000万円の中古マンションの場合
築25年の中古マンションの場合、次の軽減措置が適用されます。
- 建物の経年劣化による価値減少分として「経年減価補正率」に沿って減額される
- 小規模住宅用地(120㎡以下)のため、土地の固定資産税が1/6になる
築25年の経年減価補正率は0.3992で、軽減措置を含めた土地と建物の固定資産税は以下のとおりです。
土地 1500万円 × 1.4% × 1/6 = 35000円
建物 3500万円 × 1.4% × 0.3992 = 195608円
35000円 + 195608円 = 230608円
築25年の5000万円の中古マンションの場合、1年間の固定資産税は約23.1万円となります。
築年数ごとマンションの固定資産税の目安
固定資産税は5年間の軽減措置や経年減価補正率があるため、マンションの築年数によって変わっていきます。
モデルケースとした5000万円のマンションの場合の、築年数ごとの固定資産税の目安を一覧で紹介します。
年数 | 土地の固定資産税 | 建物の固定資産税 | 合計 |
新築 | 3.5万円 | 24.5万円 | 28.0万円 |
5年 | 3.5万円 | 21.0万円 | 24.5万円 |
6年 | 3.5万円 | 40.8万円 | 44.3万円 |
10年 | 3.5万円 | 36.2万円 | 39.7万円 |
15年 | 3.5万円 | 30.5万円 | 34.0万円 |
20年 | 3.5万円 | 24.8万円 | 28.3万円 |
25年 | 3.5万円 | 19.6万円 | 23.1万円 |
30年 | 3.5万円 | 15.0万円 | 18.5万円 |
40年 | 3.5万円 | 10.2万円 | 13.7万円 |
新築の建物に対する軽減措置の適用がなくなる6年目が最も固定資産税が高くなります。
その後は、経年劣化分の減価補正率が考慮されるため、築年数の経過とともに固定資産税が安くなっていきます。
マンションは戸建てよりも固定資産税が高い
マンションと一戸建ての固定資産税を比較すると、マンションの方が固定資産税が高くなる傾向があります。
その大きな理由は、物件価格に対する土地と建物の比率が大きく違うためです。
一般的には、一戸建ての場合は土地7割・建物3割、マンションの場合は土地3割・マンション7割がおおよその比率とされています。
固定資産税の計算式でもわかる通り、土地よりも建物の方が固定資産税が高いため、マンションの方が固定資産税の方が高額になるでしょう。
もうひとつの理由として、木造か鉄筋コンクリート(木造以外)かで「経年減点補正率」が違う点です。
建物の耐用年数は一戸建て(木造)が22年、マンション(鉄筋コンクリート)が47年です。それに合わせて「経年減点補正率」が設定されています。
例えば20年の経年減点補正率は、木造一戸建ては0.26、マンションは0.5054と倍近い差があります。
マンションの方が償却期間が長い(経年劣化が遅い)ため、固定資産税の低下が緩やかで、結果的に固定資産税が高くなります。
固定資産税の支払方法・支払時期
固定資産税の支払時期は、一般的に4期に分けて納付します。
地方税法で「固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める」と決まっています。
しかし、各期の納付期限は市町村によって異なり、以下のスケジュール内になっています。
- 第1期:4~6月
- 第2期:7~9月
- 第3期:10~12月
- 第4期:1~2月
また、第1期に一括納付できる市町村もありますので、確認してみましょう。
支払方法としては、納付書による支払い(金融機関・コンビニ)、口座振替、インターネットバンキング、クレジットカードなどがあります。
口座振替にすると、支払い忘れを防げるため便利です。
クレジットカード払いが可能な自治体も多くあり、ポイントを貯めることができますが、手数料がかかることがあるため注意が必要です。
また、最近ではPayPay、LINE Pay、au PAYなどのスマホ決済アプリを利用して支払える市町村も増えました。
手数料はかかりませんが、ポイント還元がない場合もあります。
マンションの固定資産税を軽減させる方法

固定資産税は毎年支払うため、負担を少しでも軽減したいと考える方も多いでしょう。
実は、いくつかの方法で固定資産税を軽減することが可能です。
その中でも、特に有効なのが「省エネリフォーム」や「バリアフリーリフォーム」です。
これらのリフォームを行うことで、税額の一部が軽減される制度があります。
省エネリフォーム
省エネ性能を有する住宅へのリフォーム工事をおこなった場合、工事翌年度の固定資産税額の1/3を減額(120㎡分まで)する制度があります。
以下に示す条件を満たしたリフォームの場合、省エネリフォーム税制を受けることができます。
(1)平成26年4月1日以前に建てられた住宅である
(2)居住部分の割合が当該家屋の1/2以上ある
(3)令和8年3月31 日までの間に、現行の省エネ基準を満たしたリフォーム工事をおこなう
①窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)※必須
②床の断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事
(4)家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下である
(5)改修工事に要した費用の額が以下のどちらかに当てはまる
①断熱改修に係る工事費が60万円超である
②断熱改修に係る工事費が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超である
(6)耐震基準適合住宅に係る減額等の適用中でない
耐震基準適合住宅の減額と併用ができない点は注意が必要です。
また、工事後3か月以内の申告が必要となるため、必ず行うようにしましょう。
バリアフリーリフォーム
バリアフリー改修工事をおこなった場合にも固定資産税の減額を受けられる制度があります。
以下に示す条件を満たしたバリアフリーリフォームの場合、工事翌年度の固定資産税額(100㎡分まで)の1/3が減額されます。
(1)新築より10年以上経った住宅である
(2)居住部分の割合が当該家屋の1/2以上ある
(3)令和8年3月31 日までの間に、バリアフリー改修工事をおこなう
(4)工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下である
(5)地方公共団体からの補助金等を除く工事費が50万円超である
(6)以下のいずれかの方が住んでいる
①65歳以上の方
②要介護認定又は要支援認定を受けている方
③障碍のある方
(7)以下のいずれかのバリアフリー改修工事であること
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化
(8)耐震基準適合住宅に係る減額等の適用中でない
こちらの減額制度も、耐震基準適合住宅の減額と併用ができない点、工事後3か月以内の申告が必要となる点は同じであるため注意が必要です。
まとめ
マンションの固定資産税は、物件の評価額や築年数、立地条件により大きく異なります。
新築マンションでは初年度の税額が高く、中古マンションでは築年数に応じて徐々に評価額が下がるうえ税額も減少します。
マンションの購入や保有にあたって、事前に固定資産税の負担を把握し、適切な対策を講じることで、安心して長期的な住まいづくりを進めていきましょう。
固定資産税について、さらに詳しく知りたい方は下記記事もご覧ください。
固定資産税はいくら?戸建て・マンションの計算シミュレーションと賢い軽減方法
また、土地の固定資産税が気になる方は下記記事もご覧ください。
