固定資産税はいくら?戸建て・マンションの計算シミュレーションと賢い軽減方法
最終更新日: 2025-08-01
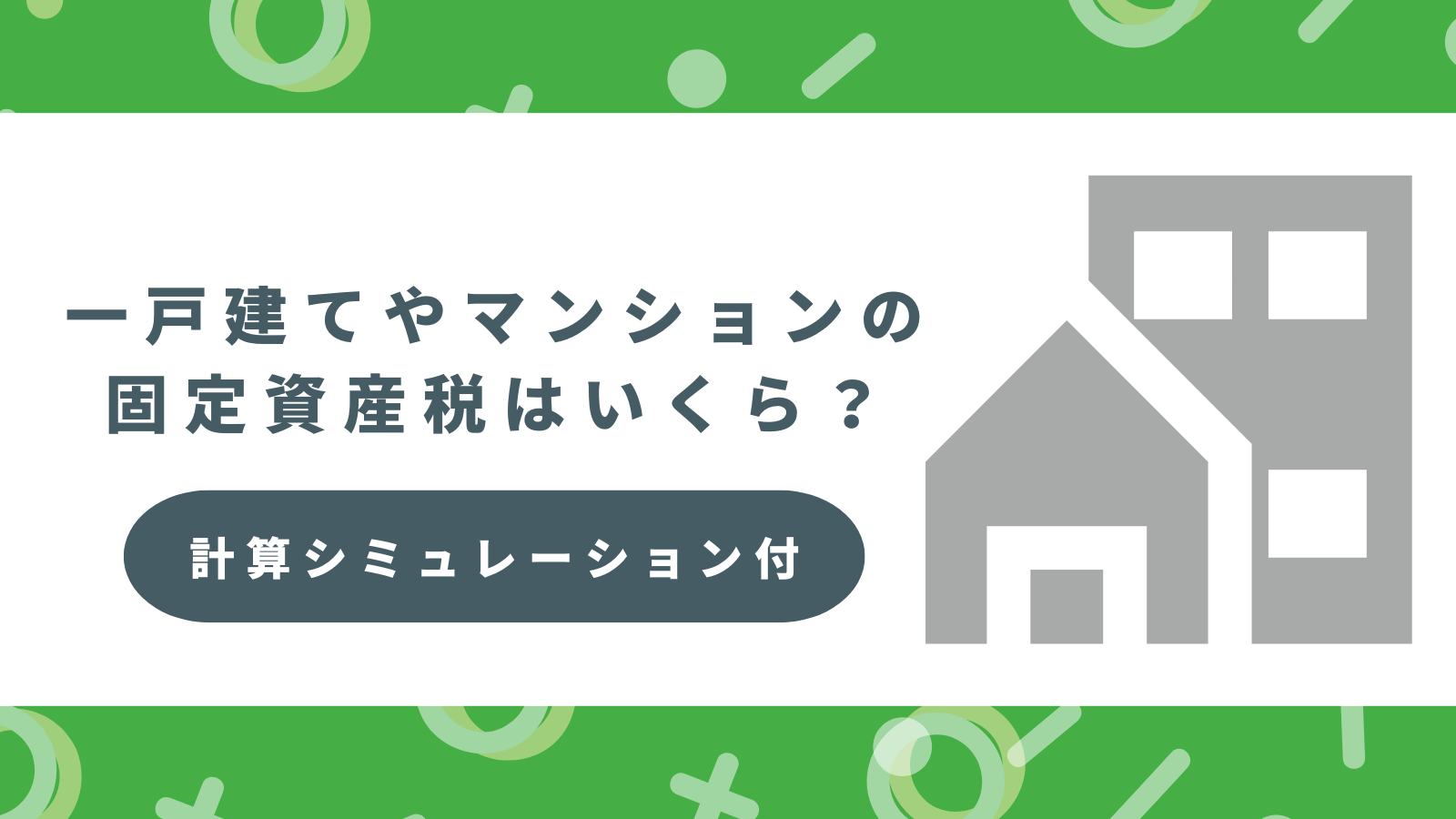
- もくじ
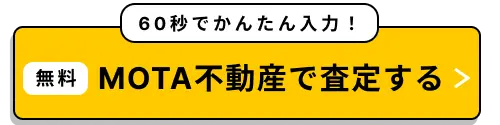
マイホームの購入などを機に、毎年支払うことになる「固定資産税」。言葉は聞いたことがあっても、「具体的にどんな税金なの?」「なぜ支払う必要があるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、固定資産税の基本的な仕組みから、具体的な税額の計算方法、一戸建てとマンションのシミュレーション、税負担を軽くするための軽減措置まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。ご自身の税額がどのように決まるのかを理解し、賢く納税するための第一歩としましょう。
そもそも、固定資産税とは?
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地、家屋、そして事業用の機械や設備などの「償却資産」(これらを総称して「固定資産」と呼びます)を所有している人に対して、その資産が所在する市町村(東京23区の場合は東京都)が課税する地方税です 。
私たちが納める固定資産税は、教育や福祉、消防・救急、道路や公園の整備といった、地域住民の暮らしを支えるための様々な行政サービスの重要な財源として活用されています。これは、資産を所有することで地域から便益(サービス)を受けているという考え方(応益原則)に基づくものであり、安心して快適に暮らすために地域社会を皆で支える税金なのです 。
固定資産税の目安はいくら?

固定資産税は、住宅を所有するすべての人が毎年支払う必要がある税金です。課税の対象となるのは、土地や建物といった「固定資産」で、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、以下のような計算式で算出されます:
課税標準額 × 税率(原則1.4%) |
|---|
ここでいう課税標準額とは、「固定資産税評価額」をもとに自治体が算出した金額です。固定資産税評価額とは、家や土地の価値を自治体が評価したもので、実際の購入価格ではありません。おおむね市場価格の70%程度が目安とされています。
税率と地域差
標準的な税率は1.4%ですが、再開発地域や特定の地区では最大2.1%まで引き上げられるケースもあります。自治体によって課税の方針が異なるため、同じような家でも、立地や地域によって税額に差が出ることがあります。
固定資産税の支払い例
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の住宅を所有している場合、
2,000万円 × 1.4% = 年間28万円 |
|---|
が固定資産税として課税されます。
このように、固定資産税は不動産を所有している限り毎年支払いが必要なため、評価額や税率の仕組みを理解しておくことが大切です。
都市計画税
また、エリアによっては都市計画税がかかることもあります。
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%(該当エリアのみ)
都市計画税は、都市計画区域内に所在する土地や建物に対して課されるものです。このため、固定資産税と都市計画税を合わせた支払い額は、評価額によってはかなりの額になることがあります。
正確な税額を知るためには、市区町村の固定資産税評価証明書で確認できます。
一戸建ての固定資産税の計算方法

一戸建て住宅を所有する場合、固定資産税は毎年発生する重要な支出項目です。
この税金は土地と建物の評価額に基づいて計算され、市区町村に納めることが求められます。
しかし、土地や建物の種類、地域による差異、さらには築年数など、多くの要因が影響するため、正確な金額を知るには細かな計算が必要です。
1. 土地の固定資産税評価額の計算
- 基準:公示価格の70%程度
- 固定資産税評価額に影響する要素:
・土地の形状・広さ
・駅・バス停・学校・病院などへのアクセス
・周辺環境や用途地域(住宅地、商業地など)
- 見直し:3年に一度の評価替え
- 都市計画区域内の場合は、都市計画税(0.3%)も発生
- 利用目的によっても差があり、住宅用地は商業用地より評価額が低くなることも
駅やバス停に近い、学校や病院が徒歩圏内にあるといった好条件の土地は、評価額が高くなる傾向にあります。
また、土地が都市計画区域内にある場合は、都市計画税が別途課されることがあります。
さらに、土地の評価額には、その土地の利用形態も影響を与えます。
例えば、住宅用地として利用される土地は、商業用地や工業用地に比べて評価額が低めに設定されることがあります。
これにより、同じ広さの土地であっても、利用目的によって税額が異なることがあります。
このように、土地の評価額には多くの要素が絡み合っており、固定資産税の計算にはそれらを総合的に判断する必要があります。
2. 建物の固定資産税評価額の計算
- 基準:新築価格 × 減価償却率
・木造住宅:築10年で約50%まで減価償却
・鉄筋コンクリート造:減価がゆるやか
- 影響する要素:
・耐震性・断熱性などの建物性能
・エコ設備(太陽光、断熱材、高効率給湯器 など)
・リフォームや増築による再評価
リフォームや増築を行うと評価額が再計算され、固定資産税が増減する可能性があります。
一方、建物が老朽化し、修繕が行われていない場合や設備が古くなっている場合は、評価額がさらに下がる可能性があります。
また、大規模なリノベーションや増改築が行われた場合、その工事内容に応じて評価額が再計算されることがあります。
例えば、建物の一部を増築したり、内部設備を大幅に改修した場合には、その分評価額が上がり、固定資産税も増加することが考えられます。
一戸建ての固定資産税シミュレーション【計算例】
想定条件
・土地の公示価格:2,000万円
・建物価格(新築時):3,000万円(築10年の木造住宅)
・税率:固定資産税 1.4%、都市計画税 0.3%
項目 | 評価額 | 税率 | 税額 |
|---|---|---|---|
土地 | 1,400万円 | 1.4% | 19.6万円 |
建物 | 1,500万円 | 1.4% | 21.0万円 |
土地(都市計画税) | 1,400万円 | 0.3% | 4.2万円 |
建物(都市計画税) | 1,500万円 | 0.3% | 4.5万円 |
合計 | - | - | 49.3万円/年 |
※土地評価額:2,000万円(公示価格)× 70%(評価基準)= 1,400万円
※建物評価額:3,000万円(新築価格)× 50%(築10年)= 1,500万円
したがって、固定資産税と都市計画税の合計額は49.3万円となり、これが年間で支払うべき総額となります。
計算の詳細は下記の通りです。
土地の評価額
まず、土地の評価額を計算します。土地の公示価格が2,000万円の場合、評価額は公示価格の70%が基準となります。
・2,000万円×0.7=1,400万円
これが、固定資産税の計算基準となる土地の評価額です。
- 建物の評価額
次に建物の評価額を計算します。
建物の新築価格が3,000万円で、築10年が経過した木造住宅の場合、一般的には新築時の価格から50%程度の価値が残ると考えられます。
・3,000万円×0.5=1,500万円
これが、固定資産税の計算基準となる建物の評価額です。
- 固定資産税の計算
次に、土地と建物それぞれに対して税率1.4%を適用して、固定資産税を計算します。
・土地:1,400万円×0.014=19.6万円
・建物:1,500万円×0.014=21万円
これらを合計すると、年間の固定資産税は次のようになります。
・19.6万円+21万円=40.6万円
- 都市計画税の計算
都市計画区域内にある場合、都市計画税が別途かかります。
都市計画税の税率は一般的に0.3%です。土地と建物それぞれに対して計算します。
・土地:1,400万円×0.003=4.2万円
・建物:1,500万円×0.003=4.5万円
これらを合計すると、年間の都市計画税は次のようになります。
・4.2万円+4.5万円=8.7万円
- 総支払い額
最後に、固定資産税と都市計画税を合計して、年間の支払い総額を算出します。
・40.6万円+8.7万円=49.3万円
これが、所有者が毎年支払うべき固定資産税および都市計画税の合計金額となります。
この計算例により、具体的な固定資産税の額をイメージすることができます。
実際には、土地や建物の条件によって評価額が異なるため、個々のケースで正確な計算を行うことが重要です。
マンションの固定資産税の計算方法

マンションを所有する場合も、固定資産税は毎年発生する重要な支出のひとつです。
固定資産税はマンションの評価額に基づいて計算され、土地部分と建物部分に分かれています。
1. 土地の固定資産税評価額の計算
- 基準: 公示価格の約70%(自治体により異なる)
- 特徴:
・マンション全体の土地の評価額を「専有面積割合」で按分
・住戸の専有面積が広いほど負担額は大きくなる
・評価額には周辺環境やインフラ整備の状況も反映される
- 評価額に影響する要素:
・駅、商業施設へのアクセス
・建物の立地や形状(角部屋、階層など)
・用途地域(住宅地、商業地など)
- 注意点:
・同じマンション内でも評価額は一律ではない
・都市計画区域内であれば、都市計画税(0.3%)も課税対象
2. 建物の固定資産税評価額の計算
- 基準: 新築価格 × 減価償却率(築年数に応じて価値が下がる)
- 減価の例:
・築10年のマンション → 新築価格の約50%
・RC造は価値減少が緩やか(木造より評価が下がりにくい)
- 評価額に影響する要素:
・建物構造(鉄筋コンクリート造など)
・エレベーター、オートロック、共用ラウンジなどの設備
・管理状況や修繕履歴
- ポイント:
・専有部だけでなく、共用施設(エントランス、会議室など)も評価に含まれる
・評価額が高い=税負担も大きくなる
また、エレベーターやオートロックなどの設備が充実しているマンションは、その分評価額が高くなる傾向があります。つまり、自分の専有部分だけでなく、建物全体の設備や共用施設も評価の対象になっていることを把握しておきましょう。
マンションの固定資産税シミュレーション【計算例】
想定条件
・物件価格:5,000万円
・土地価格:2,000万円(マンション全体の公示価格)
・建物価格:3,000万円(新築時価格)
・築年数:10年(建物評価額は50%に減価)
・所有割合:全体の10%の専有面積を所有している前提
・税率:固定資産税 1.4%、都市計画税 0.3%
項目 | 評価額 | 税率 | 税額 |
|---|---|---|---|
土地 | 1,400万円 × 10% = 140万円 | 1.4% | 1.96万円 |
建物 | 1,500万円(※) | 1.4% | 21.0万円 |
土地(都市計画税) | 140万円 | 0.3% | 0.42万円 |
建物(都市計画税) | 1,500万円 | 0.3% | 4.5万円 |
合計 | - | - | 27.88万円/年 |
※土地評価額:2,000万円 × 70% × 10%(所有割合)= 140万円
※建物評価額:3,000万円 × 50%(築10年)= 1,500万円
したがって、固定資産税と都市計画税の合計額は27.88万円となり、これが年間で支払うべき総額となります。
計算の詳細は下記の通りです。
土地の評価額
マンション全体の土地の公示価格が2,000万円であり、評価額はその70%です。
・2,000万円×0.7=1,400万円
各部屋の専有面積に応じた評価額は、例えば専有面積が総面積の10%であれば、
・1,400万円×0.1=140万円
これが、その部屋に対する土地部分の評価額となります。
土地の評価額は、マンション全体の位置や周囲のインフラ状況に大きく依存します。
例えば、駅近や商業施設へのアクセスが良好な場合、土地の評価額は高くなる傾向があります。
建物の評価額
建物の新築価格3,000万円を基に、築10年で50%の減価を考慮します。
・3,000万円×0.5=1,500万円
この評価額は、建物の材質や耐久性、管理状況などによっても影響を受けます。
例えば、鉄筋コンクリート造のマンションは木造のものに比べて価値が下がりにくく、評価額が高く維持されることがあります。
また、マンションの設備や共用部分の充実度も、建物の評価額に影響を与えます。
エレベーターの数やオートロックシステム、駐車場の有無などが評価に反映されるため、これらの要素が高評価であれば、建物全体の評価額も高くなる傾向があります。
固定資産税の計算
土地と建物それぞれの評価額に税率1.4%を掛けます。
・土地:140万円×0.014=1.96万円
・建物:1,500万円×0.014=21万円
合計で、年間の固定資産税は以下のようになります。
・1.96万円+21万円=22.96万円
さらに、都市計画税が適用される場合、土地と建物それぞれの評価額に対して0.3%の税率を掛けます。
・土地:140万円×0.003=0.42万円
・建物:1,500万円×0.003=4.5万円
合計で、年間の都市計画税は以下のようになります。
・0.42万円+4.5万円=4.92万円
総支払い額
固定資産税と都市計画税の合計支払い額は以下の通りです。
・22.96万円+4.92万円=27.88万円
この金額が、所有者が年間で支払うべき税金の総額となります。
これは、物件の評価額や場所によって異なりますが、マンション所有者にとっては重要な経済的負担となるため、事前に計算し、資金計画を立てることが大切です。
このように、マンションの固定資産税は土地と建物の評価額に基づいて計算され、築年数や減額措置の適用により変動します。
正確な税額を知るためには、市区町村の固定資産税評価証明書を確認するか、専門家に相談することをおすすめします。
固定資産税は、マンションを所有するうえで重要な要素であり、適切な理解と管理が求められます。
関連記事:5000万の新築・中古マンションの固定資産税はいくら?目安や計算例を紹介
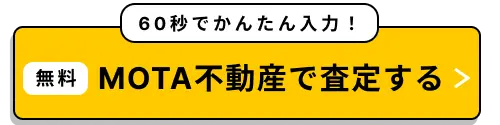
固定資産税は築年数や性能などに応じて減額される
住宅を所有すると毎年発生する固定資産税ですが、築年数や住宅の性能、工事内容に応じて減額される制度があります。これらを理解・活用することで、賢く節税することが可能です。
築年数と減額の関係
新築の建物は、固定資産税評価額が高く設定されますが、一定年数ごとに評価額が下がっていくのが一般的です。
木造住宅の場合:
・新築から3年経過で約20%減額
・その後も定期的に減額が進み、
・築20年を超えると、最大70%程度の減額が適用されることもある
鉄筋コンクリート造(RC造)などの場合:
・耐久性の高いため、減額のペースは緩やか
・同じ築年数でも評価額の下がり方は比較的抑えられる傾向がある
特例措置による減額制度もある
一定の条件を満たす住宅には、建物の評価額が下がる以外にも減額制度(特例措置)が適用される場合があります
たとえば:
- 長期優良住宅
- 耐震性能の高い住宅
これらの住宅については、一定期間、固定資産税が減額される措置が自治体によって設けられています。具体的な減額内容や適用条件については、各自治体の定める基準に従うため、詳細は市区町村の窓口で確認することが求められます。
リフォーム・改修による減額の可能性
さらに、リフォームや住宅の改修工事によって、評価額が見直されることもあります。特に以下のようなケースでは、減額措置の対象となることがあります。
- 省エネ性能を高める工事(断熱材の導入、二重サッシなど)
- バリアフリー改修(手すり設置、段差解消など)
- 耐震改修工事
こうした工事を検討する際は、事前に自治体の窓口に相談し、対象となる条件や申請方法を確認しておくことが大切です。このように、固定資産税は築年数や建物の状態に応じて減額される仕組みがあるほか、特例措置を利用することでさらなる負担軽減も可能です。
減減額措置の手続きと注意点
額措置を受けるためには必ず所定の手続きを行い、建築確認通知書や住宅性能証明書などの必要書類を自治体に提出する必要があります。申請を忘れてしまうと、本来受けられるはずの減額を受けられない場合もあるので注意が必要です。
新築住宅の場合、建物部分の固定資産税が最初の3年間(長期優良住宅は5年間)、半額になる特例もあります。
リフォームや耐震補強工事の後も、減額措置が適用される可能性があるため、必ず自治体に確認し、必要に応じて申請を行いましょう。
最新の情報を把握し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることで、賢く節税につなげることができます。
住宅にかかる固定資産税の軽減方法

住宅を所有する際、固定資産税は大きな負担となりますが、さまざまな軽減措置を利用することで税負担を減らすことが可能です。
これらの軽減措置は、土地や建物の種類、新築やリフォームなどの状況に応じて異なります。
住宅用の土地に対する軽減措置
住宅用の土地に対する固定資産税の軽減措置は、土地の広さや用途に応じて適用されます。
主な軽減措置には以下のようなものがあります。
小規模住宅用地の特例
小規模住宅用地とは、住宅1戸あたり200平方メートル以下の土地を指します。
この場合、固定資産税の評価額が6分の1になります。
例えば、評価額が600万円の土地であれば、軽減後の評価額は100万円となります。
これは大きな軽減効果があり、多くの住宅所有者にとって非常に有効な措置となるでしょう。
小規模住宅用地の特例は、多くの自治体で適用されており、申請することで誰でも利用可能です。
この特例の利用により、住宅所有者は長期的に税負担を大幅に削減することができます。
一般住宅用地の特例
小規模住宅用地を超える部分については、一般住宅用地として扱われ、評価額が3分の1に軽減されます。
例えば、評価額が1,200万円の土地であれば、軽減後の評価額は400万円となります。
これは広い土地を所有している場合に特に効果的です。
この特例を利用することで、広い土地を持つ住宅所有者も固定資産税の負担を軽減できます。
都市計画税の軽減
小規模住宅用地に対しては、都市計画税の評価額も3分の1に軽減されます。
一般住宅用地の場合も同様に軽減措置が適用されます。
この軽減措置により、都市計画税の負担も大幅に少なくなります。
都市計画税は、都市計画区域内に所在する土地や建物に課される税金であり、固定資産税と合わせて支払うことが求められます。
このため、都市計画税の軽減措置は非常に有効です。
住宅用地の特例適用条件
これらの特例措置を受けるためには、土地が実際に住宅用として使用されていることが条件です。
空き地や駐車場として利用されている場合は、特例措置の適用外となることがあります。
したがって、住宅用地としての利用が明確であることを証明する書類を準備することが重要です。
新たに住宅を建てた場合や用途変更を行った場合には、早めに適用申請を行いましょう。
手続きと申請
軽減措置を受けるためには、市区町村の窓口で適用申請を行う必要があります。
申請には、住宅の登記簿謄本や居住証明書などの書類が必要となる場合があります。
定期的に見直しが行われるため、継続して軽減措置を受けるためには、更新手続きも忘れずに行いましょう。
これにより、長期間にわたり軽減措置を享受することができます。
手続きが煩雑な場合は、専門家に相談することも有効です。
新築戸建て購入時の軽減措置
新築戸建て住宅を購入する際にも、固定資産税の軽減措置が適用されることがあります。
主な軽減措置には以下のようなものがあります。
新築住宅の減額措置
新築住宅の場合、固定資産税が一定期間減額される措置があります。
具体的には、新築から3年間(長期優良住宅の場合は5年間)、住宅部分の固定資産税が2分の1に減額されます。
例えば、固定資産税が年間10万円の住宅であれば、減額期間中は5万円となります。
この減額措置は、新築住宅を購入する際の大きな魅力となります。
新築住宅の購入を検討している方は、この減額措置を活用することで、初期の税負担を大幅に軽減することができます。
耐震・省エネ性能による減額
耐震性能が高い住宅や省エネ性能が優れた住宅については、さらに減額措置が適用されることがあります。
これらの条件を満たす住宅は、通常の減額期間に加えて追加の減額が適用されることがあります。
例えば、省エネ性能を証明する書類や耐震基準を満たすことを証明する書類が必要となります。
これらの性能を持つ住宅を購入することで、環境に優しく、かつ経済的なメリットを受けることができます。
バリアフリー改修による減額
高齢者や障害者が居住する住宅については、バリアフリー改修を行うことで、固定資産税の減額措置を受けることができます。
改修費用の一定割合が減額対象となるため、事前に自治体に確認し、適用条件を満たすように改修を行うことが重要です。
この減額措置は、住宅の居住環境を改善しながら税負担を軽減する有効な方法です。
特に高齢者や障害者が安心して暮らせる住環境を整えるためには、この改修と減額措置の活用が不可欠です。
申請手続きと必要書類
新築住宅の減額措置を受けるためには、所定の申請手続きを行う必要があります。
申請には、新築時の建築確認通知書や性能評価書などが必要となる場合があります。
これらの書類を揃えた上で、市区町村の窓口で申請を行います。
申請の際には、期限が定められているため、忘れずに早めに手続きを行うことをお勧めします。
早めに申請手続きを行うことで、スムーズに減額措置を受けることができるでしょう。
これらの軽減措置を適切に利用することで、住宅にかかる固定資産税の負担を大幅に軽減することができます。
各種軽減措置の詳細や申請方法については、市区町村の窓口や専門家に相談してみてください。
固定資産税の支払方法や納税時期について
固定資産税は、住宅や土地を所有している場合に毎年支払う必要がある重要な税金です。
この税金は、市区町村が提供する公共サービスの財源となっており、その支払方法や納税時期について理解しておくことが大切です。
固定資産税の支払方法
固定資産税の支払い方法は、複数の選択肢が用意されています。
一般的には、以下の方法がよく利用されます。
納付書での支払い
市区町村から送付される納付書を使用して、指定された金融機関、コンビニエンスストア、または郵便局で支払う方法です。
納付書には、支払うべき金額や納期限が記載されているため、その内容に従って支払います。
この方法は、現金での支払いが主となり、領収書が発行されるため支払いの確認が容易です。
口座振替
事前に市区町村と金融機関で手続きを行うことで、指定した口座から自動的に税金が引き落とされる方法です。
口座振替の利点は、納期限を気にせずに確実に支払いが完了する点です。
また、支払忘れのリスクを防ぐことができるため、忙しい方や不在が多い方に適しています。
口座振替の申込は、金融機関や市区町村の窓口で手続きが必要です。
クレジットカード支払い
最近では、クレジットカードでの支払いも可能になっています。
市区町村のウェブサイトからクレジットカード情報を登録し、オンラインで支払いを完了する方法です。
ポイント還元を狙いたい方や、支払いを分割にしたい方には便利な方法です。
ただし、クレジットカード払いには手数料がかかる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
電子マネーやQRコード決済
一部の市区町村では、電子マネーやQRコード決済にも対応しています。
スマートフォンを利用して手軽に支払いができるため、若い世代を中心に人気があります。
ただし、利用可能な決済サービスは自治体によって異なるため、事前に対応しているかどうかを確認しましょう。
このように、固定資産税の支払い方法は多様化しており、自分に合った方法を選ぶことが可能です。
固定資産税の納税時期は?
固定資産税の納税時期は、市区町村によって異なりますが、一般的には年に4回の分割払いが可能です。
通常、4月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて納付するのが一般的です。
4月(第1期)
新年度が始まる4月に、第1期の納付が求められます。
この時期には、市区町村から納税通知書が送付され、その年の固定資産税の総額が明示されます。
この通知書には、納付期限や支払方法が記載されているため、内容を確認して早めに準備を進めましょう。
7月(第2期)
第2期の納付は7月に行われます。
この時期は、夏のボーナスと重なることもあり、一括払いを選ぶ人も少なくありません。
なお、口座振替を利用している場合、この時期に自動引き落としが行われるため、残高不足にならないよう注意が必要です。
12月(第3期)
年末の12月に第3期の納付が行われます。
年末は何かと出費が多くなる時期ですので、固定資産税の支払いを忘れないように注意しましょう。
クレジットカードで支払う場合は、ポイントが貯まりやすい時期でもあります。
翌年2月(第4期)
最後の納付は翌年の2月です。この納付をもって、その年度の固定資産税の支払いが完了します。
特にこの時期は確定申告の準備と重なることが多いため、早めの支払いを心がけると良いでしょう。
分割払いではなく、一括払いを希望する場合は、第1期の納付時に全額を支払うことも可能です。
一括払いの場合、場合によっては早期納税特典がある市区町村もあるため、確認してみると良いでしょう。
また、納付期限を過ぎると延滞金が発生する可能性があるため、納税スケジュールをしっかりと把握しておくことが大切です。
まとめ
固定資産税の支払いは、住宅を所有するうえで避けては通れません。
支払いの方法や納税時期を正しく理解し、自分に合った方法で確実に納税を行いましょう。
口座振替やクレジットカード、電子マネーなど、さまざまな支払い方法を活用することで、利便性を高めることができます。
また、納税時期をしっかりと把握し、計画的に資金を準備することで、無理なく支払いを完了させることができます。
納税は法律で定められた義務であり、適切な対応が求められます。
延滞金の発生を避けるためにも、期限内の納税を徹底しましょう。
関連記事:土地にかかる固定資産税はいくら?種類や計算方法、節税対策を紹介
