家の解体費用はいくら?相場と内訳、安く抑えるコツを徹底解説
最終更新日: 2025-08-04
.png)
- もくじ
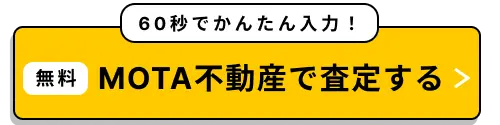
家の解体は、老朽化や建て替えを考えている方にとって避けられないことです。
一般的に解体費用は、1坪当たり木造で3〜5万円、鉄骨造で4〜8万円、鉄筋コンクリート造で6〜10万円程度とされています。
しかし初めて家の解体を依頼するとなった場合、解体費用が適正な価格かどうか素人には判断がつきません。
また、その内訳や相場、助成金など知らないことばかりで不安に感じる人も多いことでしょう。
そこで今回は、家の解体費用の内訳や相場について詳しく解説するとともに、解体費用を抑える方法や解体までの流れ、さらには注意すべきポイントをまとめて紹介します。
【構造・坪数別】家の解体費用の相場シミュレーション

家の解体を考えたとき、誰もが最初に気になるのが「一体いくらかかるのか?」という費用面でしょう。解体費用は、建物の構造や大きさ、立地条件によって大きく変動しますが、おおよその相場を知ることで、資金計画や業者選びの目安になります。
ここでは、建物の構造と一般的な坪数(延床面積)をもとに、解体費用の目安をシミュレーションしてみましょう。
はじめに:解体費用の基本的な考え方
解体費用の概算は、以下の式で算出できます。
解体費用の概算 = 坪単価 × 延床面積(坪) |
|---|
ただし、この計算でわかるのは、あくまで建物本体を解体するための費用です。実際には、後述するブロック塀の撤去や庭木の伐採などの付帯工事費や、重機の運搬費などの諸経費が別途加わります。
また、費用は地域によっても異なり、人件費や廃棄物処理費用が高い首都圏や都市部では、地方に比べて坪単価が高くなる傾向があります。
これからご紹介するシミュレーションは、あくまで一般的な目安として捉え、正確な金額は必ず複数の業者から見積もりを取って確認するようにしてください。
【構造別】費用シミュレーション
木造住宅の解体費用相場
日本の戸建てで最も多い木造住宅は、他の構造に比べて解体がしやすく、費用も比較的安価です。
- 坪単価の目安: 30,000円~50,000円
延床面積 | 費用シミュレーション(目安) |
|---|---|
20坪 | 60万円~100万円 |
30坪 | 90万円~150万円 |
40坪 | 120万円~200万円 |
50坪 | 150万円~250万円 |
60坪 | 180万円~300万円 |
※上記は建物本体の解体費用の目安です。付帯工事費、諸経費は別途発生します。
鉄骨造(S造)住宅の解体費用相場
鉄骨造は、骨組みに使われる鉄骨の厚みによって「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」に分かれ、坪単価も異なります。木造に比べて頑丈なため、解体費用は高くなります。
坪単価の目安:
- 軽量鉄骨造 (鋼材厚6mm未満): 35,000円~70,000円
- 重量鉄骨造 (鋼材厚6mm以上): 45,000円~80,000円
この区別は費用を見積もる上で非常に重要です。プレハブ住宅や一部のハウスメーカーの住宅に多い軽量鉄骨造と、3階建て以上の住宅や店舗・倉庫などに用いられる重量鉄骨造では、解体の難易度とコストが大きく異なります 。
鉄骨造住宅の解体費用シミュレーション
延床面積 | 軽量鉄骨造(S造)の費用目安 | 重量鉄骨造(S造)の費用目安 |
|---|---|---|
30坪 | 105万円~210万円 | 135万円~240万円 |
50坪 | 175万円~350万円 | 225万円~400万円 |
70坪 | 245万円~490万円 | 315万円~560万円 |
100坪 (小規模倉庫等) | 350万円~700万円 | 450万円~800万円 |
※上記は建物本体の解体費用の目安です。付帯工事費、諸経費は別途発生します。
鉄筋コンクリート造(RC造)の解体費用相場
マンションやビルに多い鉄筋コンクリート造は、最も頑丈な構造です。解体には大型の重機や特殊な工法が必要となり、騒音や振動も大きくなります。また、コンクリートガラの処分費用も高額なため、解体費用は最も高くなります。
坪単価の目安: 60,000円~100,000円
RC造の解体は専門性が高く、安全対策にもコストがかかるため、坪単価は木造の約2倍に達することもあります 。
鉄筋コンクリート造(RC造)建物の解体費用シミュレーション
延床面積 | 費用シミュレーション(目安) |
|---|---|
30坪 | 180万円~300万円 |
50坪 | 300万円~500万円 |
70坪 | 420万円~700万円 |
100坪 (小規模ビル等) | 600万円~1,000万円 |
- ※上記は建物本体の解体費用の目安です。付帯工事費、諸経費は別途発生します。
家の解体費用の内訳を解説

家の解体費用は、大きく分けて「①建物の取り壊し費用」「②廃棄物などの処理・運搬費用」「③建物本体以外にかかる費用(付帯工事費)」の3つがかかります。
それぞれ詳しく紹介します。
①建物の取り壊し費用
解体費用の中で最も大きな割合を占めるのが、建物を壊すための費用です。これには、作業員の人件費や重機のレンタル・リース費に加えて、足場の設置や、騒音・粉塵を防ぐための養生シートの設置といった「仮設工事費」も含まれます。
② 廃棄物などの処理・運搬費用
取り壊しに伴って発生する木材、コンクリートガラ、鉄くずなどの廃材を、法律に基づいて適切に分別し、処理場まで運搬・処分するための費用です。「建設リサイクル法」により分別が義務付けられており、その手間も費用に含まれます。
産業廃棄物として処理する場合、廃材の種類や量によって処理費用は大きく変わります。
アスベストなどの有害物質が含まれている場合、その処理には特別な手続きと技術が必要で、追加の費用がかかる可能性もあるでしょう。
また、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」により、手作業で分別することが定められている工程もあるため、費用がかかる場合もあります。
③建物本体以外にかかる費用(付帯工事費)
見積もりを見落としがちなのが、建物以外の構造物を撤去する「付帯工事」の費用です。これらは基本的に本体工事費には含まれず、別途費用が発生します。
- 仮設トイレや工事現場の整備費用
- 解体に使用する重機のレンタル費用
- 作業員の人件費
- 隣接する建物や道路を保護するための養生費用
- 騒音や粉塵対策の費用
これらの費用も解体全体のコストに大きく影響を与えるため、事前に業者に確認しましょう。
家の解体費用の相場はどう決まる?
家の解体費用の相場は、どのように決まるのでしょうか。
ここからは主にかかわってくる要素を5つ解説します。
立地条件
家の立地条件は解体作業の効率に直結するため、解体費用に大きく影響します。
重機が入りやすいなど作業がしやすい立地の場合は問題ないです。
しかし、隣家との距離が近い場合や、大きな重機が入りにくい道路に家がある場合、小さな重機での作業や手作業が増えるため、解体費用が上がるでしょう。
解体後には整地もおこなうため、地盤状況次第では改善が必要だったり、木々の伐採や石の撤去が必要だったりの費用も発生します。
屋根や基礎部分の大きさ
家の解体では、家の屋根や基礎部分の解体が大変なため、大きな費用がかかります。
一般的に建物が大きければ大きいほど解体作業には時間と労力がかかり、その分費用も増加します。
屋根は二重屋根や瓦屋根など、家によって解体の労力も異なり、費用の幅が大きくなる部分です。
基礎部分も家により異なり、次のような場合は手間がかかるため、費用が大きくなります。
- 基礎部分を頑丈な作りにしている
- 床下全面をコンクリートで覆うベタ基礎になっている
- 基礎部分が深い
- 地下室がある
- 基礎部分の構造が特殊である(古い家に多い)
- 劣化が進んでいる
- 家を建てる際に地盤改良工事をおこなっていて、杭を抜く必要がある
廃材の量
解体時に発生する廃材の量も、解体費用を左右するポイントです。
解体工事で発生した廃材は、分別して処分もしくは業者に買取をしてもらうことになります。
処分する場合、リサイクル法にしたがって分別する必要があり、人件費がかかる原因になります。
買取をしてもらう場合は、資源として売却できることもあるため、コスト削減につながる可能性もあります。
例えば、木材の場合は古民家1件で30〜50万程度、コンクリートがらは4000〜6000円(トン)など、廃材により金額は変わります。
近隣状況
近隣状況も、解体費用に直接影響を与える要因のひとつです。
住宅が密集しているエリアでは、隣接する建物や道路を保護するために、養生シートや防音対策が必要となります。
特に隣の建物が非常に近い場合には、解体時に振動や破片が飛び散らないようにするため、より厳重に養生が求められるため、そのぶん設置費用がかかるでしょう。
また、解体作業中に発生する騒音や粉塵については、近隣住民に配慮した対応が必要であり、そのための特別な防音・防塵設備を導入するケースもあります。
さらに、作業中に近隣住民への影響を最小限に抑えるため、作業時間や日程を調整する場合もあり、全体の費用が増加する可能性もあります。
壁材や床材の状態
壁材や床材の状態も解体費用に影響します。
特に古い建物の場合、壁や床にアスベストなどの有害物質が含まれていることがあります。
このような有害物質は、適切な処理手続きと専門的な技術が必要であり、通常の解体費用に加えて、特別な処理費用がかかることがあります。
また、建物の状態が著しく劣化している場合や、腐食が進んでいる箇所が多い場合には、解体作業が通常よりも手間取るでしょう。
それに伴って作業時間が長引き、費用が増加することがあります。
家の解体費用をできる限り安く抑える4つの方法

家の解体には確かに費用がかかりますが、できるだけコストを抑えたいと考える方も多いでしょう。
ここでは、解体費用を抑えるための具体的な方法をご紹介します。
①複数の解体業者から相見積もりを取る
最も重要かつ効果的な方法です。必ず3社程度の業者から見積もりを取り、費用と内容を比較検討しましょう。料金体系は業者によって異なり、数十万円の差が出ることも珍しくありません。
価格の安さだけで業者を選ぶと、不法投棄や近隣トラブルなどのリスクがあります。以下のポイントを参考に、信頼できる業者を選びましょう。
- 許可・登録があるか確認する
- 工事保険に加入しているか確認する
- 見積書の内訳が明確で丁寧か
- 担当者の対応が誠実か
②事前に庭の手入れや不用品を処分しておく
解体前に庭や家の中の不用品を自分で処分することで、業者にかかる処分費用を減らすことができます。
特に大型の家具や家電などを処分しておくと、解体時の廃棄物量が減り、その分コスト削減につながります。
また、庭木やフェンス、物置なども自分で取り除いておけば、業者に依頼する際の費用を削ることができるでしょう。
さらに、自治体が提供する粗大ごみ回収やリサイクルセンターを活用することで、コストを抑えながら不要物を処分できます。
リサイクルショップやフリマアプリを活用して、まだ使えるものは売却するのもひとつの方法です。
事前にこれらの作業をしっかりとおこなうことで、解体の見積もりも低く抑えられることが期待できます。
③住宅ローンに組み込む(建て替えの場合)
解体費用を抑えるために、住宅ローンに解体費用を組み込む方法もあります。
家の建て替えの場合、その住宅ローンに解体費用を加えることで、まとまった資金の管理がしやすくなります。
多くの金融機関では、建物の建て替えにともなう解体費用を住宅ローンの一部として認めているため、金利の低いローンの活用で支払総額を抑えられるかもしれません。
一度に大きな出費を避けたい場合には、有効な方法です。
ただし、ローンの条件や利息については事前に十分確認し、長期的な返済計画を立てましょう。
無理のない範囲でローンに組み込むことで、資金負担を軽減しながら解体を進められます。
④助成金を利用する
特定の条件を満たす場合に、家を解体する際に国や自治体から助成金を受け取ることができます。
受けられるおもな助成金や補助金を一覧で紹介します。
- 老朽危険空き家の解体補助金
- 木造住宅解体工事補助金
- ブロック塀等撤去費補助金
- 建て替え工事助成金
- 空き家対策補助金
- 危険廃屋解体撤去補助金
- アスベスト除去に関する補助金
- 空き家再生等推進事業
- 特定空き家対策補助金
- 地域活性化補助金
助成金や補助金は自治体によってさまざまなため、お住まいの自治体の情報を確認してください。
また、助成金の申請には、解体業者からの見積書や現地調査の結果が必要となるため、早めに自治体へ相談して準備を進めることが重要です。
家の解体を依頼してから完了するまでの流れ

実際に家を解体する際の具体的な流れと、各ステップの目安期間を紹介します。
STEP1:業者探し・相談・現地調査
目安期間:1〜2週間
複数の業者に連絡し、現地調査を依頼します。建物の状態や周辺環境を確認してもらい、要望を伝えます。
現地調査の結果をもとに、見積もりや解体方法が決まるため、業者としっかりとコミュニケーションを取り、疑問点や不安な点をこの段階で解消しておくとよいでしょう。
STEP2:見積もり提示・業者決定・契約
目安期間:1〜2週間
提示された見積書を比較検討し、依頼する業者を決定。工事内容、金額、工期などを確認し、工事請負契約を結びます。
STEP3:各種届出
着工前に、業者が必要な届出(建設リサイクル法の届出など)を自治体に行います。
STEP4:近隣への挨拶
工事開始の1週間前までには、業者が近隣住民へ工事の概要(期間、内容など)を説明し、挨拶回りを行います。施主も一緒に回ると、より丁寧な印象を与えられます。
STEP5:ライフラインの停止
電気、ガス、水道、電話、インターネットなどの停止手続きを、施主自身で行います。
STEP6:解体工事
目安期間:1週間〜1ヶ月程度
足場と養生シートの設置後、内装→屋根→建物本体→基礎の順に解体を進めます。工事中は騒音や振動、粉塵が発生します。
STEP7:廃材処理・整地
発生した廃材を分別して搬出し、敷地を平らにならして(整地)、工事は完了です。
STEP8:建物滅失登記
建物を取り壊した後、1ヶ月以内に法務局へ「建物滅失登記」を申請する必要があります。これを怠ると10万円以下の過料に処せられる可能性があるため、忘れずに行いましょう。
家の解体で注意すべき点
家の解体を進める際には、解体費用や工期以外にも、いくつか重要な注意点を理解しておく必要があります。
特に解体後の土地の固定資産税の扱いや土地の活用方法、さらには法的な手続きに関しては事前に把握しておくことが重要です。
更地のままだと土地の固定資産税が上がる
家が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大で1/6に軽減されています。しかし、家を解体して更地になるとこの特例が適用されなくなり、翌年から固定資産税が3〜4倍に跳ね上がるケースがあります。
土地をしばらく更地のまま保有する場合には、固定資産税が増加することを見越して資金計画を立てる必要があります。
そのため、解体後にどのように土地を活用するかを事前に考えおきましょう。
解体後に土地活用が可能か確認する
解体後の土地に家を建て替える予定がある場合、その土地が「再建築不可物件」でないか事前に確認が必要です。建築基準法上の道路に2m以上接していない土地などは、一度更地にすると新しい建物を建てられない可能性があるため、注意しましょう。
特に、古い住宅地や都市部では、近隣との調整が必要な場合もあり、これにより次の建築が予定通りに進まないケースもあります。
また、土地を売却する場合にも、土地の用途や地域の規制が売却価格に影響を与えるため、これらを十分理解したうえで売却戦略を立てる必要があります。
まとめ
家の解体は、解体費用の内訳をしっかりと理解し、適切な手順を踏めば、スムーズに進めることが可能です。
解体費用は建物の構造や立地、廃材の量などによって大きく変動するため、事前に複数の業者から見積もりを取り、費用を比較することが重要です。
また、助成金制度を活用することで、費用を抑えることもできるでしょう。
さらに、解体後の固定資産税の上昇や土地活用についても、早めに計画を立てておく必要があります。
専門業者に相談したうえで、しっかり解体計画を立て、損のない家の解体をおこないましょう。
関連記事:
土地売却の完全ガイド|流れ・費用・税金対策から高く売るコツまで徹底解説
土地にかかる固定資産税はいくら?種類や計算方法、節税対策を紹介
