不動産売却後の確定申告ガイド|いつ必要?やり方は?節税の特例まで徹底解説
最終更新日: 2025-07-31
.png)
- もくじ
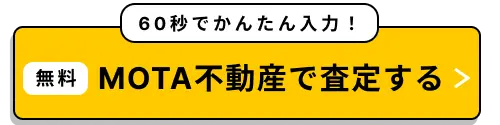
「不動産を売却したけど、自分も確定申告は必要?」
「もし利益(譲渡益)が出たら、税金はいくらになるんだろう?」
「申告しなかったら、何か罰則はあるの?」
不動産売却後、こうした疑問が次々と浮かんでいませんか?
本記事では、そんなあなたの疑問に一つひとつお答えします。
確定申告が必要・不要なケース分けから、使えると非常にお得な税金の特例、そして申告の具体的な手順まで、この記事を読めば全てがわかります。
一緒に確定申告の全体像をつかんで、漠然とした不安を解消しましょう。
不動産売却後に確定申告は必要?

不動産売却後に確定申告が必要かどうかは個人の状況によりますが、「譲渡所得」として利益が出た場合は確定申告が必要です。
しかし、売却益がゼロまたは損失となった場合には、『確定申告をしなくてもよい』場合もあります。
それぞれのケースについて見ていきましょう。
そもそも譲渡所得とは?
譲渡所得とは、不動産を売却して得た「儲け(利益)」の部分です。売却価格そのものではなく、そこから購入にかかった費用などを差し引いた金額を指します。
この譲渡所得は以下の式で計算できます。
不動産売却による譲渡所得=不動産売却による収入金額-(取得費-譲渡費用) |
取得費とは、不動産の購入費用や改良費・設備費、購入時の手数料などを指します。
不動産の取得費がわからない場合や取得費が売却価格の5%未満の場合は、売却金額の5%相当を取得費とできます。
譲渡費用とは、不動産の売却にかかった費用のことで、不動産仲介手数料や土地の測量費などです。
確定申告が必要になる場合(譲渡所得がある)
不動産を売却して利益が発生した場合、その利益は「譲渡所得」として課税対象となります。
不動産を売却した際の譲渡所得は「申告分離課税」にあたるため、給与所得の税金とは別に計算されます。
このため、通常の確定申告書とは別に、分離課税用の確定申告書を作成する必要があります。
確定申告が不要な場合(譲渡所得がない、または損失がある)
不動産を売却した際に、利益が出なかった場合は確定申告をおこなわなくてもよいです。
譲渡所得の計算式でゼロまたはマイナスになるケースです。
たとえば、収入金額が4000万円あっても取得費と譲渡費用の合計が5,000万円だった場合は、-1,000万円となり確定申告は必要ありません。
特別控除を受ける場合は確定申告が必要な場合も
ただし、たとえば「居住用財産の3,000万円特別控除」を利用することでゼロになる場合は、自動的に計算される訳ではありません。
控除を受けるために確定申告が必要となります。
また、マイナスとなった場合でも、次に紹介する「損益通算」により税金の軽減措置があるため、確定申告することをおすすめします。
不動産売却後の確定申告はいつまで?
不動産売却後に確定申告の期限は、売却をおこなった翌年の2月16日から3月15日で、通常の確定申告と同じ期間です。
確定申告の期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があり、余計な費用がかかることになります。
売却益が発生し、課税対象となる場合はもちろん、売却損が発生した場合でも損益通算の特例を利用するために確定申告が必要です。
特に、適用できる控除や特例がある場合、必要な書類を揃えるまでに時間がかかることが多いため、早めに準備を始めましょう。
確定申告が遅れてしまった場合でも、申告自体は可能ですが、遅延による罰則を避けるためにも期限内の申告を心がけましょう。
税理士に依頼する場合も、申告期限が迫ってからでは十分なサポートを受けられないこともあるため、早めに相談をおこないましょう。
譲渡益・譲渡損失の特例
不動産売却において利益が発生した場合や、逆に損失が出た場合に、それぞれ税務上で特例が適用されることがあります。
譲渡所得を計算した後、特別控除額分を譲渡所得から差し引くことが可能です。
不動産売却による譲渡所得 = 不動産売却による収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 |
このような特例を活用することで、譲渡益に対する税負担を軽減したり、損失をほかの所得と相殺して節税効果を得られます。
譲渡益が出ている場合(譲渡益の特例)
不動産売却で利益が出ている場合に、適用できるおもな控除を紹介します。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
最も有名な控除で、マイホームを売却した際に最高3000万円が控除されます。
譲渡所得が3000万円未満の場合には、譲渡金額分が控除されゼロになります。マイナスにはならないことを知っておきましょう。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
売却年の1月1日時点で10年を超えるマイホームを売却した場合は、「軽減税率の特例」が適用できます。
譲渡所得金額 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
6,000万円以内の部分 | 10.21% | 4% | 14.21% |
6,000万円を超える部分 | 15.315% | 5% | 20.315% |
※所得税に別途復興特別所得税2.1%がかかっています。
たとえば1億円の譲渡所得が出た場合の計算は以下になります。
6,000万円 × 14.21% + (1億円 - 6,000万円)× 20.315 = 1,665.2万円
特定の居住用財産の買換えの特例
マイホームを買い替える際に一定の条件を満たした場合に、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることのできる特例です。
下の図の1回目の売却の際にこの特例を適用すると、2000万円に対する税金は買い換えたマイホームを売却するまで支払わないことになります。
ただし、あくまで繰り延べただけですので、将来マイホームを売却した際に発生した譲渡益1500万円と合わせて3500万円に対して税金がかかることになります。
この特例は非常に多くの条件を満たす必要があるため、国税局のサイトを確認しましょう。
譲渡損失が出ている場合(譲渡損失の特例)
不動産を売却して損失が発生した場合、確定申告をおこなうことで「損益通算」および「繰り越し控除」の特例を受けられる場合があります。
これに該当するケースは次の2つのケースです。
- 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
この2つの特例の内容とその違いを下記の表で紹介します。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | |
|---|---|---|
新しいマイホームを購入する必要 | なし(購入してもよい) | あり |
売却した不動産のローン残高の有無 | 売却金額以上の残高がある | なし(残っていてもよい) |
損益通算可能額 | 売却損益、もしくは売却金額を引いたローン残高の小さい方 | 売却損益額 |
特例には、1月1日現在で5年以上所有しているなど、それぞれの特例に一定の条件を満たす必要があります。
特例を適用できると売却損益を給与所得や事業所得と損益通算し、税金の軽減ができます。
損益通算してもまだ損益が残っている場合は、翌3年間にわたって繰り越し控除がおこなえます。
参考:
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例|国税庁
マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁
不動産売却で認められる経費について
不動産を売却した際、売却価格から差し引ける「経費」を適切に計上することで、譲渡所得をおさえ、結果的に支払う税金を軽減することが可能です。
しかし、すべての費用が経費として認められるわけではなく、国税庁の定める基準に基づいて、計上できる経費とそうでないものを明確に区別する必要があります。
経費計上が認められるもの
経費として計上できる費用は、大きく分けて「譲渡費用」と「取得費」に分類されます。
これらの経費は譲渡所得から差し引くことができ、結果として課税対象となる金額をおさえられます。
譲渡費用への計上が認められる費用
譲渡費用とは、不動産の売却に直接かかわる費用のことです。
たとえば、不動産を仲介業者を通じて売却した場合に支払う仲介手数料が代表的です。
このほか、物件の測量費や、建物を取り壊して土地だけを売却する際の解体費用も譲渡費用として計上することができます。
さらに、売却の際に発生した登記費用や、契約書に貼る印紙代も譲渡費用に含まれます。
また、買い主との交渉で必要になった境界確定費用など、売却に直接結びつく支出は譲渡費用として認められる場合が多いです。
取得費にできる費用
取得費とは、不動産を購入した際にかかった費用の総称です。
購入時の不動産価格のほかに、仲介手数料や、購入時の登記費用、契約書の印紙代などが含まれます。
また、購入後におこなったリフォームや改修工事の費用も、取得費として計上できるケースがあります。
ただし、リフォームや改修が資産価値を向上させるためのものであることが条件です。
相続や贈与で取得した不動産の場合は、相続時の評価額が取得費として扱われるため、購入時と異なる点に注意が必要です。
経費計上が認められない費用
不動産売却に関連して発生するすべての費用が経費として認められるわけではありません。
たとえば、売却にともなう引っ越し費用や、物件の掃除・クリーニング費用は経費として計上できません。
そのほか、経費として認められないものを紹介します。
- 相続登記費用
- 引っ越し費用
- 物件の掃除・クリーニング費用
- 修繕費用
- 固定資産税
- 税理士費用
- 火災保険料
など
不動産売却における確定申告の手順・やり方

不動産を売却した際の確定申告は、通常の所得税の申告とは異なり、譲渡所得の計算や、必要な書類の準備が必要です。
特に、売却価格から「取得費」や「譲渡費用」を差し引いた譲渡所得額を正確に算出する必要があります。
1.取得費・譲渡費用を計算する
まず初めに、譲渡所得を算出するために必要な取得費と譲渡費用について詳しく見ていきましょう。
取得費
取得費とは、不動産を購入した際に支払った代金や、その購入にともなう各種費用の総額で、以下のものが該当します。
- 不動産を購入する際に支払った費用
- 建物を新築や増築する際にかかった費用
- 不動産業者に支払った仲介手数料
- 不動産に付随する設備の費用
- リフォームや改修にかかった費用(資産価値が上がる場合)
- 不動産を取得する際の登記費用(登記免許税を含む)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
- 土地の埋立てや土盛り、地ならしにかかった費用
- 測量にかかった費用
- 建物を取り壊すためにかかった費用
- 不動産を購入するために借り入れた資金の利子(実際に不動産を使用するまでの期間分)
など
取得費は多くのものが該当し、売却価格から差し引くことで譲渡所得を減らせるため、記録をしっかりと保存しておくといよいでしょう。
譲渡費用
譲渡費用とは、不動産を売却する際にかかった費用のことで、以下のものが該当します。
- 不動産仲介業者に支払った仲介手数料
- 不動産を取得する際の登記費用(登記免許税を含む)、印紙税
- 建物を取り壊すためにかかった費用
- 測量にかかった費用
など
売却にかかった費用のすべてが譲渡費用として計上できるわけではない点に注意が必要です。
たとえば、物件のクリーニング費用や、引っ越し代などは譲渡費用には含まれません。
2.課税譲渡所得金額の計算を行う
取得費と譲渡費用の計算ができたら、課税譲渡所得金額の計算をしましょう。
まず、売却価額から取得費と譲渡費用を引き譲渡所得を計算します。
次に、「3,000万円特別控除」や「買換え特例」など適用できる控除を引くことで、課税譲渡所得金額が計算できます。
この課税所得金額に、所得税と住民税が課されます。
短期間で不動産を売却した場合、所得税の税率が高くなるケースもあるため、売却タイミングによっては税額が大きく異なることに注意が必要です。
3.確定申告の準備・申告を行う
譲渡所得の計算が終わったら、その結果を国に報告し、納税額を確定させるための「確定申告」を行います。
確定申告の手続きでは、まず不動産売却の詳しい内容を記した「譲渡所得の内訳書」という書類を作成します。その後、確定申告書に、算出した譲渡所得の金額や税額を転記します。会社員の方などで給与所得がある場合も、その情報と合わせて一つの確定申告書として提出します。
申告期間は、売却した翌年の2月16日から3月15日までが基本です。ただし、この日程は年によって変動する可能性があるため、国税庁の公式サイトで確認するのが最も確実です。申告書の提出先は、お住まいの地域を管轄する税務署となります。
一連の手続きを前に、「聞き慣れない書類も多く、思ったより複雑そうだ」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。この確定申告は自分自身で対応すべきか、それとも税の専門家である税理士に任せるべきか、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
確定申告は自分でやる?税理士や会計士に任せる?

不動産売却時の確定申告は、適用される控除や計算方法が複雑なため、自分で申告するのが難しいと感じる方も少なくありません。
その一方で、申告手数料を節約したいという理由から、自分で手続きをおこなうという方もいます。
それぞれのメリットとデメリットについて紹介します。
確定申告を自分でやる場合
メリット
確定申告を自分でおこなう最大のメリットは費用をおさえられることです。
売却益が少額であったり、特別控除を受けることで納税額がゼロになる場合には、自分で申告する方が経済的です。
また、e-Taxを利用すれば、自宅からインターネットを通じて申告が可能です。
税務署の職員に相談することもできるため、初めての方でも安心して手続きを進められるでしょう。
デメリット
ただし、受けられる控除や取得費に含むことができる費用に気がつかない場合もあります。
また、書類の準備や計算に時間がかかることがあり、ミスが発生すると追徴課税のリスクもあります。
税理士や会計士に任せる場合
メリット
税理士や会計士に確定申告を依頼する場合、専門家の知識と経験に基づいた正確な申告がおこなわれます。
不動産売却にともなう税務は、一般的な確定申告とは異なり、取得費や譲渡費用の計算、特例の適用などが非常に複雑です。
プロに任せることで書類のミスを未然に防げ、安心して確定申告ができるでしょう。
また、税理士や会計士は、申告後の税務調査に対応してくれる場合が多いため、安心感があります。
デメリット
ただし、税理士や会計士への報酬が発生するため、費用面での負担があります。
報酬は一般的には10〜20万円と言われていますが、譲渡所得額に応じて変動することが一般的のため、事前に料金やサービス内容を確認することがおすすめです。
まとめ
不動産売却後の確定申告は、適切な手続きをおこなうことで税金の負担を軽減することができます。
譲渡所得の計算や特例の適用など、複雑な手続きが必要となるため、事前にしっかりと準備をおこなうことが重要です。
特に、取得費や譲渡費用の計上、特別控除の適用など、細かな点を見逃さないように注意しましょう。
確定申告の期限を守ることも大切です。
初めての方や手続きに不安がある方は、税理士や会計士などの専門家に依頼することで、安心して確定申告をおこなえます。
専門家のサポートを受けてスムーズな確定申告をおこないましょう。
不動産売却に関するおすすめ記事もぜひご覧ください。
不動産売却の基本ガイド|流れ・注意点・成功のコツをわかりやすく解説
